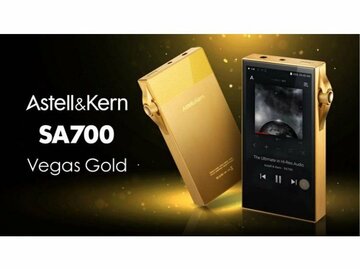2017年1月のCESに試作機が出品され、注目を集めていたソニー初のトゥルーワイヤレスイヤフォン「WF-1000X」が、10月7日に発売される。すでに小売店では2万6870円で予約を受け付けている。
デザインはCESで展示されていた試作機、ほぼそのまま。密閉カナル型のオーソドックスなスタイルだが、そこにノイズキャンセリングシステムを内蔵しているのが新しい。BluetoothのペアリングにNFCが使えるのもソニーらしいところだ。

このWF-1000Xは、同日発売予定のオーバーヘッドバンド型「WH-1000XM2」、ネックストラップ型「WI-1000X」とともに「1000X」シリーズの一角を成し、新登場のスマートフォンアプリ「Headphones Connect」にも対応している。
注目は、AppleのAirPodsが圧倒的強さを持つこの市場に、割って入るポテンシャルがあるのかどうか。ごく短い間だったが触れることができたので、その印象をレポートしたい。
意外と普通なスペックに驚き
イヤフォンデザインは密閉タイプのカナル型で、ドライバーは専用開発と言われる6mm径のダイナミック型。イヤフォン本体片側の重さは約6.8g。ヘッドセットとして通話やクラウドAIの呼び出し操作にも対応する。
BluetoothのオーディオコーデックはSBCとAACに対応。低遅延コーデックのaptXや、ハイレゾ相当と言われるソニーのLDACには対応しない。機器間の接続と同時に、左右ユニット間の通信も必要なこのタイプでは、大きなデータ量の対応は厳しかったのかもしれない。

バッテリーの持ち時間はごく標準的で、イヤフォン本体の音楽連続再生が約3時間。これはNCがオンでもオフでも変わらない。イヤフォンの充電には、付属のバッテリー内蔵ケースを使って約1.5時間というのが公式発表値。
そのバッテリー内蔵ケースのフルチャージには約3時間で、これでイヤフォン本体が2回チャージできる。つまりスタンドアロンで使えるのは約9時間ということ。


ノイズキャンセルとNFCの搭載を除けば、トゥルーワイヤレスイヤフォンのスペックとしてはごく標準的なものだ。それで使いにくいということはないが、AppleはAirPodsの売り文句として、重さ4g、連続再生5時間、バッテリーケース併用で24時間使えることをうたっている。対して、普段はスペックで押してくる印象のソニーの製品、しかも初物のそれとしては、ちょっと意外なくらい普通に思える。
本体のデザインと装着性はさすがとしか
イヤフォン本体の外観でまず目を引くのが、透明樹脂に覆われたU字型パーツ。これがBluetoothのアンテナで、通常は筐体の内側に隠してしまうパーツを、デザインの一部として使うアイデアは新しい。また、このアンテナを覆う透明樹脂パーツには、動作インジケーターのLEDが組み込まれていて、透過光で青や赤に光るところもおもしろい。

装着時の違和感のなさも素晴らしい。ある程度大きく、外側にぶら下がるマスの大きなイヤフォンとしては、装着安定性を確保するためスタビライザーも必要になる。ソニーでは「フィッティングサポーター」と呼ぶらしいが、WF-1000Xは最初から込みでデザインされている。

スタビライザーは小さなU字型で、耳の後ろ内側のくぼみにハマる珍しい形状。上向き加減に耳に押し込み、そのまま下向きに回すと安定したポジションが見つかる。スタビライザーは取り外し可能で、M/Lの2サイズを選べるが、回転方向に調整することはできない。しかし、まったく困らない。標準装着のイヤーピースも、通常のものよりスリーブ部分が長く、これも装着性に影響しているかもしれない。



音の良さを引き立てるノイズキャンセル
トゥルーワイヤレスイヤフォンは、左右イヤフォン間も無線で通信しなければならない構造から、レイテンシーの影響は避けられない。問題になるのは動画の音ズレ、そして左右に定位が動くフェージングのような現象だが、いずれも問題は感じなかった。ステレオオーディオ装置として成立する最低限のスペックは、確実にクリアしている。
そして、とにかく出音がとても好ましい。Bluetoothで6mm径のドライバーと聴けば、ローとハイが物足りなかったり、DSPで盛られたダイナミックレンジの狭い音をイメージしがちだが、無駄にワイドレンジを狙った嫌な感じはしない。自然な低域の量感から音場の空気感をイメージさせるチューニングは、トゥルーワイヤレスでは貴重だ。
それには、もちろんノイズキャンセルも一役買っている。ノイズキャンセルと言えば、音質劣化の元凶のように言われていた時期もあったが、小型の筐体でここまでやれるのかと感心する程度に効くし、劣化も感じられない。カナル型であっても 低い帯域の騒音成分は侵入するので、バランスのいい音で聴くためにノイズキャンセルはあったほうがいい。
ただ気になったのは、音楽の再生を始めて信号が入ると「プツッ」というノイズがいちいち入ること。これは気障りだ。X1000シリーズの他機種では確認できなかったので、トゥルーワイヤレスの仕組みに由来するものかもしれない。そして頻度は多くないとはいえ、右チャンネルのドロップは、室内であってもたまに起きる。
外音を取り込む機能を自動化するアダプティブサウンドコントロール
WF-1000Xには、装着状態でも外の音が聞こえる「アンビエントサウンドモード」がある。遮音性の高いカナル型でノイズキャンセル搭載のイヤフォンでは、安全性のためにもあった方がいい仕組みだ。
これには3つのモードがあり、外音をそのまま取り込む「ノーマルモード」、人の声を聞きやすくフィルタリングした「ボイスモード」、そして外音取り込みオフでノイズキャンセルがフルに効くモード。しかし状況に応じて切り替えるというのでは、せっかく機能として付いていたとしても、ちょっと面倒だし宝の持ち腐れになる可能性も高い。
それを自動でやってくれるのが「アダプティブコントロール」という仕組み。Android/iOS向けアプリ「Headphones Connect」と組み合わせると、スマートフォンの加速度センサーを利用し、止まっている、歩いている、走っている、乗り物に乗っているという4つの状態を認識し、自動でモードを切り替える。
たとえば止まっているときはボイスモード。オフィスなどでは空調の騒音は抑えつつ、人が呼びかける声はしっかり聞こえる。立ち上がって歩きはじめるとノーマルモードになり、近づいてくるクルマのエンジン音もはっきり聞こえるようになる。そして周囲の騒音レベルが上がってくると、乗り物に乗ったものと判断され、外音取り込みオフでノイズキャンセル全開、という具合。いずれも、そろそろかなと思ったところで、スパッと切り替わるのでおもしろい。


ただし、トゥルーワイヤレスはイヤフォン内に組み込めるパーツに限りがあるせいか、ほかのX1000シリーズに比べると、アプリで操作できる機能は絞られている。たとえばWI-1000X、WH-1000XM2の場合は、外音取り込みのレベルは20段階で調整できるが、WF-1000Xはオンオフの組み合わせのみ。サラウンドやサウンドポジションコントロールも省略されている。
デモ機を試した9月上旬の段階ではイコライザーも未実装だったが、これは10月中旬以降のアプリケーションアップデートで対応する予定らしい。
密閉カナル型としてイチオシ
さて、WF-1000XがAirPodsの向こうを張れるのかと言えば、開放型のAirPodsに対して、密閉カナル型ノイズキャンセルのWF-1000Xというポジションで定着するのではないか。
まず価格設定がおもしろい。AirPodsが1万円台後半で登場して以降、トゥルーワイヤレスの主戦場は1万円台後半になったが、AirPods以外は密閉カナル型で、どこもノイズキャンセルは載んでいない。
ここに差額6000~7000円程度でノイズキャンセルが付き、ほかの密閉カナル型より品質感のある製品が登場すれば、それだけで結構なインパクトになる。いま3万円台前半で予約を取っているEARIN M3が、いかに高性能であっても、もうノイズキャンセルは付けられない。
イヤフォンのスペックや機能は必要最小限に絞り、あとはほかの新興ブランドにない技術で押す。もう少しバッテリーは持ってくれても良かったとは思うが、あれこれ読み切った商品企画には納得しかない。トゥルーワイヤレス、どれがいい? という方には、カナル型でよければ、いまのところWF-1000Xがイチオシだ。
次回はいまどきネックストラップなのか? と思いきや、実際使ってみたら大傑作だった「WI-1000X」について。