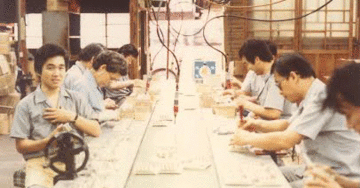経理部門の社員に、次のステップを歩んでもらうための人材育成策とは。普遍的なノウハウの継承が重視される仕事だが、上司のコピーをつくってはダメだ(写真はイメージです) Photo:PIXTA
経理部門の社員に、次のステップを歩んでもらうための人材育成策とは。普遍的なノウハウの継承が重視される仕事だが、上司のコピーをつくってはダメだ(写真はイメージです) Photo:PIXTA
経理部員に次のステップを歩んでもらうための人材育成策には、どんなものがあるでしょうか。ある程度の規模の企業であれば、職務ごとの人材育成カリキュラムなどが整備され、外部講師による研修受講、Eラーニング、実践を重視しながらのOJTなどを取り入れるなど、工夫を凝らしているところも多いでしょう。
しかしながら、これまでの指導スタイルに何ら改善すべきところがなく、十分に機能していると言い切れる人は稀ではないでしょうか。なかには、日々の仕事に邁進することで精一杯なため、経理部員の育成策の見直しまでやる余力がない人もいるでしょうが、これまでの方法を再考してわずかでも刷新することで、個々人ならではの能力を生かすことができる可能性があります。
今回は、自社の経理部・部下育成策を再考しながら、メスの入れどころを探り、さらに良い方法を実践できる方法を説いていきます。多忙な日々を過ごす経理マネジャーやスタッフ、そして経営層の読者も参考にしてください。
経理部員が育たないのは
上司のバイアスが邪魔している?
「上昇志向のある若手など、あまりいないですよ。もちろん、一生懸命業務にはあたっているようですが……。経理部に配属されるような人たちは、大人しくてあまり意見を言わないですし。“育成策”と言ってもね……」
こう語るのは、システム開発企業の経理部に勤務するAさん(部長職・50代・男性)です。何ともネガティブな物言いですが、ひょっとしたら、この話に共感する人もいるのではないでしょうか。
筆者も経理部員の育成策をどのように進めているのかについて、何社かの企業を取材したことがありますが、「経理部に上昇志向がある人など稀だから、難しい」「彼らはスキルアップや出世に対して消極的。だから経理など事務職を選ぶのでしょう。あまり力を入れていません」というように、Aさんと同様の意見を漏らす人が少なくありませんでした。