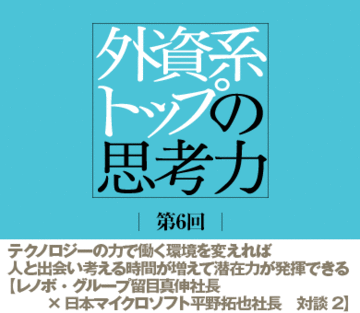「全ての人にテクノロジーに対する理解が必須となった時代――しかし、テクノロジスト以外のノン・テクノロジストが知り、身につけるべきはテクノロジーそのものではない。テクノロジー思考である。」
この刺激的なメッセージとともに、シンガポールからイノベーション投資を通じて世界を見渡すVC(ベンチャーキャピタリスト)・蛯原健氏の初の著書『テクノロジー思考』が発売となりました。同書はまさに、文系ビジネスマンを中心とする「ノン・テクノロジスト」たちに、新たな視点を与えてくれる1冊です。
同書の一部を再編集した本連載の第1回として、「序章」の一部をお届けします。
エンパワーメントの時代
その朝、私はいつものようにシンガポールの自宅からインドネシアの首都ジャカルタへと、日帰りの出張フライトに旅立った。2時間弱のフライトを終え、スカルノハッタ国際空港に最近できたばかりの巨大な第3ターミナルに降り立つと、多大なる流血をともなう死闘の結果Uber(ウーバー)をこの地から蹴散らすことに成功した東南アジアのローカル産ライドシェア・アプリ、Grab(グラブ)を使って市街地までの車を呼ぶことにした(無論両者が流したのは本当の血ではない、投資家が投じた莫大な資金である)。
ジャカルタは栄えある世界第1位の渋滞都市だ。運が悪ければ呼んだドライバーと2、3時間のドライブを覚悟せねばならない。配車ボタンをタップして数秒でマッチングが成立し、アプリに表示されたドライバーの顔写真を見てみると、頭部にヒジャーブと呼ばれるイスラム教の伝統スタイルの巻物を纏ったうら若き女性だった。ほどなくして乗車指定場所にやって来たトヨタ・アバンザに乗り込み、若きムスリム女性ドライバーと、いつも通り「ハーイ」とお互いひと言ふた言だけ。すぐに彼女は運転に、私はスマートフォンに集中する。
これは1年の半分ほどを国外出張で過ごす私の、ごくありふれた日常風景だ。しかし考えてみると、なかなかに感慨深い。イスラムの戒律が厳しい中東サウジアラビアでは、つい先日まで女性による車の運転は法律で禁じられていた。見ず知らずの他人を同乗させる、いわんやそれでお金まで稼ぐなどということは、それまでのイスラム教社会においては想像すら難しかったはずである。
ライドシェアというイノベーションの登場によって、それまで職探しすら覚束なかったような人々が生活の糧を手にする。のみならず片言の英語で外国人相手にコミュニケーションに興じる。
テクノロジーとイノベーションによって個の力、個の人生が拡張される、エンパワーメントの時代の好例である。

ライドシェアだけではない。それまで銀行口座すら持たなかった十数億人の人々が、アリペイ、ウィーチャットら電子ウォレットの登場によりマネーを自在に使いはじめている。同様にアフリカではM-PESA(エムペサ)、インドはPaytm(ペイティーエム)、フィリピンではCoins.ph(コインズ)という人気ウォレットアプリが使われている。
バングラデシュでは極貧の農民がAIの力によって収穫高を増やし、そのおかげで子どもを学校に通わせることができるようになった。
中国の片田舎の小さなパパ・ママ雑貨店が電子決済と監視カメラと最新マーチャンダイジングを導入し、一夜にしてインテリジェント・ストアに変身する。
インドの地方部では幼な子が深夜に腹痛を訴え激しく泣いても、1時間かけて病院に行ったあげくに2、3時間待たされていた。それならまだ良いほうで無医村も少なくない─といった状況だったところ、今ではモバイルアプリを通じて医師にかかることができる。スマートフォンで送信された処方箋をもってドラッグストアに走り、薬をもらって事なきを得る。その間45分そこそこだ。
先進国はもとより、アジアやアフリカを含めた地球上の都市にテクノロジーが染み出し、人々の生活を大きく変えている。
「イノベーションか、死か」「テクノロジーか、死か」
人に対してだけではない。国家も地方自治体も軍隊も、教育機関や非営利組織、家庭から宗教に至るまで、もはやあらゆる組織や物事の背景にはテクノロジーがその大きな存在感を発揮している。世界はテクノロジーによる恩恵(そして時に弊害)に溢れている。テクノロジーが物事を良い方向にも悪い方向にも大きくレバレッジする。テクノロジーが企業や個人はもとより、国家や地方自治体をも富ませ、そして時に貶める。テクノロジーが政治を動かし、テクノロジーが戦争すら起こす。あるいはそれを抑止する。
企業活動においても言わずもがな、あらゆる産業がデジタルトランスフォーメーション、すなわちテクノロジーによる産業革新という激流のまっただなかにある。製造業、素材、化学、エネルギー、教育、例外なくすべての産業がテクノロジーによって再定義されるという、パラダイムシフトが全世界において進行している。
「イノベーションか、死か」「テクノロジーか、死か」
そういう時代を今、我々は否応なしに生きている。
「私はどうも技術音痴なもので……」などと言って薄笑いを浮かべて後頭部をかいていれば許された、そんな時代は残念ながらとうに終わっている。好むと好まざると、あらゆる組織の構成員、とりわけそのリーダーや次世代リーダー候補にとって、テクノロジーに対する正しい理解は「better to have」ではなく「must have」となった。
◆先の米国大統領選挙はテクノロジーによって勝敗が決した。
◆世界で最も難関と言われる大学はキャンパスを持たず、オンライン上に存在する。
◆テクノロジーに強い都市は決まって軍事産業都市である。
たとえばこのような事柄はあまり知られていない。あるいは知識として知ってはいても、その背景にある本質までは理解されていない。
ビジネスのみならず世界情勢を分析する際にも、テクノロジーと人間社会の関係性についての正しい認識の有無によって、結果は大きく異なってくる。たとえば中国やインドなど近年において台頭著しい国家が自らの組織や仕事に与える影響について、それらが有するテクノロジーの現実を知らないがゆえに軽視し、あるいは過剰評価する、逆にいつまでたってもシリコンバレー礼賛の向きがある我が国においてはその地盤沈下傾向について見逃すといった可能性もあるだろう。
現代の二大スーパーパワーたる米中の関係性の本質は何か、それを受けて日本の正しい産業政策は何か、あらゆる意思決定の質がテクノロジーと人間社会の関係性についての正しい認識の有無により大きく変わる。
このような事柄、そしてそれらに通底する本質は、日々流れてくるニュースをただ眺めていても、あるいは従来型の思考アプローチで考えるだけでもなかなか見えづらい。あるいは何となくぼんやりと感じることができたとて、それを明示的に言語化、体系化して理解し、仕事に役立てることは難しい。
ノンテクノロジストのための思考法
そこにおいて欠けているものは何だろうか。何をもってすればテクノロジーの本質と社会へのインパクトがはっきりと浮かび上がり、正しく認識され、明日からの行動に役立てることができるのだろうか。
その欠けているものを表すために名付けた言葉が、「テクノロジー思考」である。言い換えると、テクノロジー思考とはこうなる。
近年において世界のあらゆる事象、組織、そして人間にテクノロジーが深く関与し、また支配的な存在として強い影響を与えている事実に焦点をあてた、新しい思考アプローチ
機械工学やコンピュータサイエンスを体系的に学んだうえで設計やコーディング等に職業として携わる者をテクノロジストと呼ぶとして、テクノロジストのようにテクノロジーそのものを理解することは万人にとっては不可能であるし、またその必要もない。
したがって本書では、テクノロジーそのものの詳細については、まったくと言ってよいほど論じていない。そのようなことを目的としていないからである。
むしろノンテクノロジスト、すなわちテクノロジストではない者にこそ必要なのがテクノロジー思考である。リベラルアーツに通じ、産業に通じ、人間に通じ、マネジメントに携わる者こそテクノロジーの在り方を正しく理解すべきである。
本書においてテクノロジーの在り方を正しく理解するとはすなわち、テクノロジーの歴史やそこから演繹される未来、あるいはテクノロジーの人間社会に対する可能性や適用手法、インパクトを正しく理解することである。
本書はまさに私が普段実践しているテクノロジー思考をもって世界を眺めるプロセスそのものを記述し、1冊の本にまとめたものである。
本論となる第1章から第8章までは、産業、政治、国際関係分析等々の今日的なテーマについて、テクノロジー思考を用いて論じている。
また終章においては、テクノロジー思考そのもの、すなわちテクノロジーと人間社会の接点を紐解く際の思考アプローチについてまとめている。本書で展開している論理や分析を実際に筆者がどのようにして生み出したかについて、その思考様式の一部を記述している。
筆者はアジアのレッド・ドット(地図上に刺さる赤いピン、つまり小さいながらもアジアの中核的な場所という意味)と言われるシンガポールを拠点として、世界各国のテクノロジーやイノベーションに投資をすることを職業としているベンチャーキャピタリストである。

その仕事柄、世界のさまざまな国籍の起業家や投資家、職業人と日々接し、彼らが生み出すテクノロジーやイノベーション、あるいは新市場の誕生を目撃してきた。
世界各国におけるミクロの実体験とそこから得られる一次情報、そして各国のメディアや情報機関が日々膨大に発するマクロ情報との間を行き来し、それらに通底するコンテクストをあぶり出し、思考を重ね、系統立てて言語化する。それがベンチャーキャピタル、とりわけ世界をトランスボーダーに活動する著者の日常である。
そういう日常を何年も過ごしているうちに、ごく自然な形でこの「テクノロジー思考」というコンセプトが浮上してきた。
私自身、テクノロジストではない。ノンテクノロジストとしてこの四半世紀にわたって第一線のテクノロジーを目の当たりにし、ともに歩んできた。その道程においてテクノロジーの人間社会に対する大きなインパクトを身に染みて痛感し、テクノロジーを仕事や生活に適切に取り入れそれをマネジメントする者とそうでない者、そもそもテクノロジーを理解する者とそうでない者の間において生じる、大きな差を認識するに至った。そのギャップを埋めること、そのために人間社会とテクノロジーとの接点を解き明かすこと、それが本書執筆の動機でもある。
テクノロジストはそのマネジメントを必ずしも得意としない。それは一流のアスリートが一流のコーチであるとは限らないように、一流の芸術家や音楽家がその良き指導者であるとは限らないように、専門家は没頭することで成果をあげ、それを伝導する者は別の者である場合が多いというのが世の常である。
本書が良き伝道者となり、新規事業開発や海外事業展開に携わる企業人、起業家、投資家、あるいは政策立案や外交に従事する官公庁職員、政治家、コンサルタント等、あらゆる職業人や生活者にとって、普段の仕事や生活に役立つ実践的な思考様式を得られることを期待してやまない。そして読者各位の、あるいはその所属組織の、輝かしい未来のためのほんの一助にでもなれば幸いである。
1994年、横浜国立大学経済学部を卒業し、(株)ジャフコに入社。以来20年以上にわたり一貫してスタートアップの投資及び経営に携わる。2008年、独立系ベンチャーキャピタルとしてリブライトパートナーズ株式会社を創業。2010年、シンガポールに事業拠点を移し東南アジア投資を開始。2014年、バンガロールに常設チームを設置しインド投資を本格開始。現在シンガポールに家族と在住し、インドと東京の3拠点にて事業を行う。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。本書が初の著書となる。