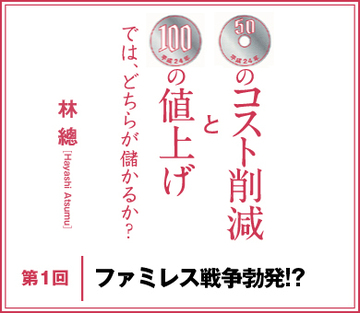安曇は満足げにアールグレイを飲んで、話を続けた。
「ボクは若いときに気管支肺炎にかかったことがあってね。体温が40度を超えて体中から湯気が立ったほどだ。体温計が壊れるんじゃないかと思ったよ。恐ろしくなって救急車を呼んだ。2週間ほどで退院したが、体力はなかなか戻らなかった。もっと早く医者に診てもらうべきだったんだ」
ヒカリは安曇が何を言おうとしているのか、見当がつかなかった。
「会社が赤字というのは、病気にかかって熱が37度を超えている状態と考えていい。熱が出たからといってすぐに命を落とすわけではない。だが、軽く考えて肺炎にでもなったら話は別だ。ボクがそうだったようにね。つまり、赤字が続いたら、その原因をはっきりさせることが大切なんだ。早めに治療しないと、会社の寿命を縮めることになりかねない」
ヒカリは安曇が言ったことの意味が、何となくわかった気がした。
「赤字だけでは必ずしも危険とは言えないけど、赤字をそのままにしておくと、後で取り返しのつかないことになる、ということでしょうか」
「そのとおり。それに、昨日まで健康だった人が突然亡くなることがあるように、黒字会社であっても突然倒産するのは珍しくはない」
「それって『黒字倒産』のことですか」
ヒカリは授業で勉強したことを思い出した。
「会社の中を流れるお金は血液と同じなんだ。お金の流れが止まれば会社は一瞬で潰れてしまう。赤字か黒字かが問題ではない。お金が回っているかが問題なんだ。利益が出ていても、必ずしもお金が回っているワケではない。利益と儲けは別物なんだよ。とはいえ、赤字が続けば会社の体力は落ちる。早く治療するに越したことはない。君の頭の中にある赤字会社がどこか想像もつかないけどね」
そう言うと、安曇はニコッと笑った。