『独学大全──絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法』を推してくれたキーパーソンへのインタビューで、その裏側に迫る。
今回は特別編として、日本最高峰の書評ブロガーDain氏と読書猿氏のスゴ本対談「経済学編」が実現。「経済学の悪口を言おう」と集まった二人に、『独学大全』とあわせて読みたいおすすめの本を挙げながら縦横無尽に語ってもらった。(取材・構成/谷古宇浩司)
 photo:Adobe Stock
photo:Adobe Stock
経済学の出自は「倫理学」
Dain:実は、私は経済学について、あまり良い考えを持ってないんですよね。経済学って、やってもよくわからないのが正直なところです。学べば学ぶほど、「おかしいんじゃね?」という不信な気持ちになっています。
若い頃、会社の先輩が「日本経済新聞をスミからスミまで読め」と言っていたのを鵜呑みにして、何年も実践したことがありますが……、よく分からなかった。
たとえば、ある日の第1面に「円安は日本経済にダメージを与える」とあって、何ページかめくると、「この円安は奇貨となる」と書いてある。「どっちやねん」と投げ捨てたことを覚えています。
今なら、円高にも円安にもメリット/デメリットがあることが理解でき、くだんの記事は、「ピンチをチャンスに」という意味あいで書かれたものだと汲み取ってあげることはできる。でもどこかに無理があるように思える。
読書猿:今回の経済学対談では、私なりの悪口を言いながら(笑)Dainさんに経済学と和解してもらいたいなと思っています。そもそもですが、経済学が嫌われる理由の根本は、この学問が実は「倫理学」を出自とするところにあるのではないか、と思うんですよね。
Dain:出自が倫理学。どういうことですか?
読書猿:有名なのは、経済学の父といわれるアダム・スミスが、グラスゴー大学でスコットランド啓蒙の中心人物であった哲学者フランシス・ハッチソン(1694 - 1746)の下で道徳哲学を学び、自身も『道徳感情論』なんて本を書いて、グラスゴー大学で道徳哲学を教えた人です。さらに、それ以前から、のちに経済学としてまとめられる様々なアイデアは、「儲けを出すのは良いことか」「利子を取るのは許されるのか」といった倫理上の問題に取り組んだ人達によって蓄積されてきたものなのです。
あと、経済学はよく、単純なモデルから結論を導いて「これこれはムダ」「これこれすべきでない」という強い主張をやってひんしゅくをかいますが(笑)、倫理学もまた簡単なモデル、というか思考実験から結論を導いて「ヒトを殺すのはよくないことだ」みたいな強い主張をする。
ここでのポイントは、倫理学は別に世の中の実情を扱っているわけではないことです。ヒトを殺す人は実際いるわけですが、だからといって倫理学の結論が間違っている(事実によって反証される)わけではない。同じように、完全な競争なんてほぼあり得ないけれど、それをもって経済学の市場理論は無益だというわけではない。
倫理学は、例えば、人を傷つけることまで自由だとして認めてしまうと、いつ誰にやられるか分からなくなって、むしろ様々な自由が損なわれてしまうことを、シンプルなモデルを使った推論で示す(我々もそれを聞いてなるほどと思う)。けれど、そういう社会が本当に実現するのか、実現するとしたらどのような社会で、具体的に何が必要なのか、といったことまでは倫理学だけでは予想できない。そういう具体的な予測をするには、倫理学の使うモデルはシンプル過ぎる。
経済学もまた、不景気な時に増税したらひどいことになることは推論できるし、主張もするのだけれど、実際のインフレ率を予想させてもまず当たらない。そういう目的には、経済学のモデルもシンプルすぎるんです。まあむやみに複雑にしても、過剰にフィッティングするだけで、予測性能が上がらない気もしますが。
経済学に足りないのは「慎み」?
読書猿:さらにルーツを深堀りしながら、あえて「経済学では扱えていない経済の領域はどこか」という論点で話ができればと思います。先日買った本、薄いんだけど、そういうネタが満載なんです。
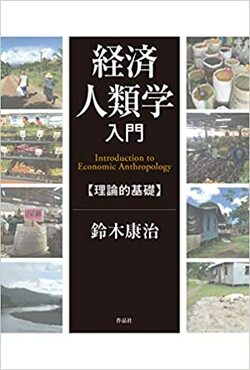 鈴木康治『経済人類学入門』(作品社)
鈴木康治『経済人類学入門』(作品社)
『経済人類学入門』(作品社)という本。この本だけでご飯を何杯も食べられる。早稲田大学の助教の鈴木康治さんという方が書いた教科書らしいんですが、めちゃくちゃ網羅的に暴れている(笑)。
内容は、まず「経済(エコノミー)とは何ぞや」から始まるんですが、僕たちがいわゆる経済学として考えるような狭い領域の話ではなくて、それこそ人類学者は出てくるし、社会学者も出てくるし……。具体的に「エコノミーのうち、経済学はここは扱っているけど、ここは扱っていない」という話をしている本なんです。
Dain:先に結論を聞いてしまいますが、僕らがこれまで学んできた「経済学」には、何が足りないんでしょうか?
読書猿:「足りないもの」は一言で言えないくらいいろいろあるんですが、また怒られそうなことを言うと、経済学に足りないのは「慎み」かな、と。
ただそれを補っても経済学が今より良くなる訳じゃない(笑)。むしろ経済学の良さがなくなるんです。経済学の良さって、あまり仮定を置かずに、人間の好き勝手な行動から推論をスタートして断定的な「強い主張」ができるまでいけるところなんですが、これは経済学が嫌われる主要因でもあります。一方で、現実の社会を見ると、個々人の行動はいろんな内的外的なものに制約されていて、ポジションとシチュエーションが決まれば、ほとんどの場合、取り得る行動はごく少数に絞られてしまう。
面白いのは、個々人の行動はそれくらいパターン化しているのに、そういう行動を重ね合わせると、社会全体では何が起こるか分からない「びっくり箱」であるところです。経済学に欠けているのは、こういう社会のわからなさにつきあう忍耐というか、慎み深さではないか、と。ただ経済学が「うちのモデルではこうなりますが、社会って複雑だから、やっぱりよく分かりません」みたいなことを言い出したら、人気下がると思うんです。
エコノミーには「家のこと」という意味もある
読書猿:ちょっと話を戻して、経済学より手前の話をしようか、と。
つまりエコノミクスじゃなくてエコノミーについてですが、『経済人類学入門』では、いきなり辞典を引くんです(笑)。僕らは経済=エコノミーだと思っているけど、実は「エコノミー」にはいろんな意味がある。大きな辞書を引くと、「倹約」とか「経済活動」の他に、(自然の)「秩序」とか(神の)「摂理」なんて意味が書いてあって、ものすごく広い意味の言葉だと分かる。あまりに広すぎるんで元々は何なんだと、語源を見てみると、ギリシャ語で「オイコノミア」という言葉があって、これは「オイコスのこと」ぐらいの意味なんです。
「オイコス」とは「家(ホーム)」のこと。ホームを扱うのがオイコノミア。家政学とも訳す。対して都市とか国家がポリスで、ポリスのことをやるのが「ポリティア」。こっちはポリティクス、政治の語源になっています。
古代ギリシャでは、「ポリス」と「オイコス」は対立概念でした。アリストテレスは、現代の観点からすると、ちょっと炎上しそうなことを言ってます。「男性はポリスのことに専念して、オイコスは奴隷と女に任せておけ」みたいな。ここではポリスとオイコス、ポリティアとオイコノミアが水と油だってことを覚えといてください。
Dain:面白そうな本ですね。「男は政治、女は家事」なんて昭和のノリで今だと確実に炎上案件ですね。奇妙なのは、「政治(ポリス)」と「家事(オイコス)」が対立概念だったところです。現代では「政治経済」と一体化して使われてるのに、ルーツを遡ると、水と油だったとは……!
経済学のルーツ①:政治と経済は、どのように結びついたのか?
読書猿:今の時代に「エコノミー」と聞くと、僕らはもはや「家(オイコス)」に限った話だと思わない、もっと社会全体に関わるものだと思いますよね。その理由は、僕らが思う経済学がヨーロッパに生まれた「ポリティカル・エコノミー」というものの流れをくむからです。これが今回のテーマである経済学の直接の先祖になる。「オイコスとポリスを分けろ」と言っていた、アリストテレスが聞いたら怒りそうだけど……。
では、ポリティカル・エコノミーはどのような経緯で生まれてきたのでしょうか。
この辺の事情は、百科事典ではフワっと書いてあって「元々家だけのことだったものが、拡大して国全体に及んだ」みたいな調子でよくわからない。
で、もう少しわかる話をフーコーがしてくれるんです。単なる拡大ではなくて、異質なもの、ギリシャ由来のオイコスの知に、非ギリシャ的なもの、具体的にはユダヤ教やキリスト教由来のものが入ってきて、そいつがポリスとオイコスの知を結びつけたんだ、と。
『ミシェル・フーコー講義集成〈7〉安全・領土・人口(コレージュ・ド・フランス講義1977~78)』(筑摩書房)に「生権力」というキーワードが出てきます。
フーコー曰く、権力の本質は、禁止や暴力である、と。つまり「逆らったら殺す、掟に違反したら殺す」というのが、権力の本来のあり方。この権力の対象は領土です。敵を殺したり追い出して領域を占拠する。敵が入ってきたら排除する。
これに対して生権力とは、人間の生命をケアし、管理する権力です。今でいうと衛生行政がイメージしやすいですね。これがどこから来たかというと、キリスト教やユダヤ教なんだと。牧師と訳されるpastorはラテン語の羊飼いという単語から来ています。「羊飼い」→「群れの世話をする者」→「魂の案内人」みたいな感じでしょうか。羊飼いにとって羊は財産であり、増えればうれしい。故に自分たちの繁栄のために世話をする。
キリスト教やユダヤ教の影響を受けて、こういうタイプの権力、生権力が広がっていく。生権力の対象は、人口です。エコノミーとは家(オイコス)のことをやる何かでした。これを広い意味での家政学、家の財産を管理し増やすことと考えると、これを国(ポリス)全体についてやるのが、ポリティカル・エコノミー。家の財産である「羊」を増やすみたいに、国の財産である人口を増やそうとするわけです。これが、ギリシャ以来、対立するものだったオイコスとポリスの知を合体させ、ポリティカル・エコノミーが成立する前提になったんだ、と。
Dain: 羊飼いが羊を飼育するように、教会が人を養育するわけですね。経済が政治権力と合体するのはイメージが湧きます。economyの訳語で経済の語源となった「経世済民」という言葉に、「人を治める」という政治寄りのニュアンスがあるので、ポリティカル・エコノミーの意味と重なりますね。
経済学のルーツ②:神と経済は、どのように「折り合い」をつけたのか?
読書猿:ポリティカル・エコノミーにはもう1つのルーツがあって、それは商売をやる人の実践知です。
さっき「儲けるのは良いことか」「利子は許されるのか」という倫理的な議論から、のちに経済学にまとめられるアイデアが蓄積されたと言いましたが、そういう議論に先鞭をつけたのが、13世紀に台頭したスコラ哲学です。
スコラ哲学が興隆してきた時代は、都市が繫栄した時代でもありました。都市とは、経済活動の拠点となる場所です。経済活動が盛んになって、それでビジネスの経験知を持った人がたくさん出てきた。
実は、スコラ哲学という精緻の学問大系も、托鉢修道院という、都市を拠点に都市経済の発展を前提にした、新しいタイプの修道院によって可能となりました。それまでの修道院は田舎にあって、農地を持っていて自給自足が基本。修道士は畑を耕したり労働が必須だったんですが、托鉢修道院は、豊かな都市市民からの寄付で成り立つ。だから労働から解放された分、学問に専念できる。
一方で、「キリスト教の美徳は清貧だから、儲けるなんて、けしからん」という問題が出てきます。そういう神学上の考えと、経済が発展してきた社会の現実とを、どのように結び付けていくか。ぶっちゃけると、社会の現実をどう神学的に正当化するかが、スコラ哲学が取り組んだ問題のひとつでした。
まず正当化しなきゃならないのは「富」です。
清貧の反対でダメなものとされた富をどのように理屈付けをするか。トマス・アクィナスは神学の知恵にギリシャ由来の哲学の知恵を「悪魔合体」させて(笑)、成り立たせた。
アリストテレスはいろんな学問をやっていますが、彼によると、倫理的な徳はいろいろあるけれど、「中庸」という考えで整理できるんだ、と。たとえば、勇気という徳は無謀と臆病の中間です。こんな風にどちらかに偏らない「中庸である」ことが徳の成り立ちだ、と。スコラ哲学はアリストテレスの中庸の考え方を使って、吝嗇と放逸の中庸に徳を見つける。それが「リベラルティ」。リベラルというのは、言うなれば経済学的な徳なんです。まったく一銭も出さないケチと、「宵越しの金は持たねえ」浪費家の間に徳はある。無駄遣いはしないけど、使うときには使う、という徳。これで経済活動が部分的にであれ、正当化される。
次は利子。
これには二通りあって、以前は利子を取ると地獄に行くと決まっていた。そこで煉獄という概念を発明する。煉獄とは何かというと、そこで頑張ったら確率は低くても天国に行けるかもしれないという場所。地獄と天国の中間。利子を取れば地獄に落ちるという前提だけど、頑張ったら天国に行けるかも……と肯定するわけです。これで当時の都市経済は正当化できる。こうしたスコラ哲学の理屈で中世末期までなんとかやっていくのだけど、近代に入るには、さらに飛躍した議論が必要になる。ここで出てくるのがマックス・ウェーバーがいう、カルヴァンの予定説なんです。
Dain: 富と利子は、資本主義の基本ですね。
もともと清貧を良しとしていたキリスト教なのに、人々が富を追い求めて繁栄したのが現実。教義を現実に合わせるために、がんばって解釈をこねくり回す努力が涙ぐましい……。
アリストテレスの中庸を「富」に当てはめる発想が面白いですね。ケチすぎてもダメ、財布が緩すぎてもダメ。「ほどほどに使いなさい」というのは、ある意味正しいかもしれません。
すごく強引だなぁと思うのが、利子を正当化するために、わざわざ煉獄という世界を発明したところ。おそらく、教会を始め、社会全体が、利子をあたりまえのものとして成り立っているので、いまさら利子を否定できない。でも「利子を取ると地獄行き」は変えられない。現実と教義がずれるとき、新しい用語を作り出して、無理やりこじつけているように見えます。
読書猿:そうですね(笑)。さっき、ヒトはいろんな制約の中にいて、経済学が前提するみたいに自由じゃない、という話をしましたけど、いろんな制約まみれだからこそ、その制約をひとつ外すだけでも大げさな理論立てというか、こじつけを動員しなきゃならなくなる。そういう人間の度し難いところ、僕は嫌いじゃないです(笑)。
で、近代に入るのに加えて必要だったのは、儲けた分をいかに再投資に結びつけるか、という議論です。スコラ哲学が導入した「リベラルティ」と「煉獄」という理論武装だけだと、これは出てこない。超過利潤は教会に寄付するのが正しい、となってしまう。「儲けた金を、さらに儲けるために自分のために使うなんて!」とんでもない、と。
まあスコラ哲学の本拠地である托鉢修道院は寄付によって成り立っているので、それがなくなるような理屈をスコラ哲学はつくらない。しかし、それでは資本主義(経済)が登場しない。資本主義は「資本が資本を生む」ことで成立するので。再投資できるか、できないかは大きな問題なんです。
で、カルヴァンの予定説だと、誰が救われるかはあらかじめ決まっている、と。この理屈がどういうことになるかというと、「富が富を増やすこと」を神が許さないなら、(そういうことをしているやつは)どこかで失敗するだろう、と。だったら、再投資を続けて経済的に成功しているということは、神が認めていることだ、と(笑)。カルヴァンの予定説をひっくり返したような話だけど、プロテスタントもそういうようなことができて、再投資でビジネスを大きくしていくことがOKになる。
富、利子、そして再投資。このように3つくらい、経済とキリスト教との和解の契機があるんです。
面白いのは、トマス・アクィナスの弟子筋にあたるサマランカ学派なんかが、のちの経済理論の基本になるようなアイデアをいろいろ検討したりとかしている。さっきの「再投資」と「カルヴァンの予定説」の話のように、こじつけというか言い訳のようにも見える議論はあるけど、そういう風にしながら人間は神と経済の関係に折り合いをつけてきたんです。
Dain:それが正しいかどうかは置いといて、お金はお金が大好きだから、富が富を呼ぶのは現実ですね。現実を聖書の教えとすり合わせ、正当化させてきた経緯が、経済とキリスト教の和解の歴史なんですね……。
経済学って、現実に合わせて理論を伸び縮みさせたり、後付けで継ぎ足してきたという印象があります。そういう「現実とのすり合わせ」は、聖書がやってきたことを踏襲しているのかもしれませんね。
書評ブログ「わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる」管理人
ブログのコンセプトは「その本が面白いかどうか、読んでみないと分かりません。しかし、気になる本をぜんぶ読んでいる時間もありません。だから、(私は)私が惹きつけられる人がすすめる本を読みます」。2020年4月30日(図書館の日)に『わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる』(技術評論社)を上梓。



