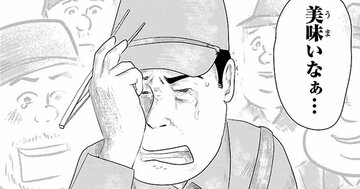1942年6月6日、キスカ島に上陸後、帝国軍旗を掲げた日本軍(ファイル:JapaneseKiska.jpg/Wikimedia Commons)
1942年6月6日、キスカ島に上陸後、帝国軍旗を掲げた日本軍(ファイル:JapaneseKiska.jpg/Wikimedia Commons)
日本軍兵士たちは、どのようにして死んでいったのか。戦場における兵士の死といえば、戦闘による死をまず思い浮かべるのが普通だが、一橋大学名誉教授の吉田裕さんによると、アジア・太平洋戦争の特徴として「戦病死者が異常に多いこと」という――。※本稿は、吉田 裕『日本軍兵士―アジア・太平洋戦争の現実』(中公新書)の一部を抜粋・編集したものです。
戦病死者が異常に多い…
太平洋戦争の異常な実態
日本軍兵士たちは、どのようにして死んでいったのだろうか。
戦場における兵士の死といえば、戦闘による死をまず思い浮かべるのが普通だろう。しかし、この常識が通用しないのがアジア・太平洋戦争、特に絶望的抗戦期の戦場の現実だった。
まず指摘できることは戦病死者が異常に多いことである。戦闘による死者と病気による死者の両方をあわせて戦死者という場合もあるが、ここでは、両者を区別して、戦闘による死者を戦死者、病気による死者を戦病死者と呼ぶことにする。
近代初期の戦争では、常に伝染病などによる戦病死者が戦死者をはるかに上まわった。それが、軍事医学や軍事医療の発達、補給体制の整備などによって戦病死者が減少し、日露戦争では、日本陸軍の全戦没者のうちで戦病死者の占める割合は26.3%にまで低下した。日露戦争は戦死者数が戦病死数を上まわった史上最初の戦争になった(「アジア・太平洋戦争の戦場と兵士」)。
ある部隊の1944年以降の
戦病死の割合は73.5%にもなる
ところが、日中戦争では、1945年11月に第一復員省が作成した資料によれば、戦争が長期化するにしたがって戦病死者数が増大し、1941年の時点で、戦死者数は1万2498人、戦病死者数は1万2722人(ともに満州を除く)、この年の全戦没者のなかに占める戦病死者の割合は、50.4%である(『近代戦争史概説(資料集)』)。
アジア・太平洋戦争期に関しては、包括的な統計がほとんど残されていない。しかし、のちに詳しく見てゆくように、アジア・太平洋戦争が日中戦争以上に苛酷な状況のもとで戦われたことを考慮するならば、前者の戦病死の割合が後者のそれを下まわるとは、とうてい考えられない。
戦病死の実相にせまるために、初めに部隊史を検討してみたい。部隊史のなかには自らの調査に基づいて作成した戦没者名簿を掲載しているものがあり、そのなかには、戦死・戦病死の区別を明確にしたものが数は少ないものの存在しているからである。
支那駐屯歩兵第一連隊の部隊史を見てみよう。日中戦争開始以降、一貫して中国戦線で戦ったこの連隊の日中戦争以降の全戦没者は、「戦没者名簿」によれば、2625人である。
このうち絶望的抗戦期にほぼ重なる1944年以降の戦没者は、敗戦後の死者も含めて戦死者=533人、戦病死者=1475人、合計2008人である(戦没年月日不明者=14人、不慮死=2名を除く)。
戦病死者が全戦没者のなかに占める割合は、1944年以降は実に73.5%にもなる(『支那駐屯歩兵第一連隊史』)。