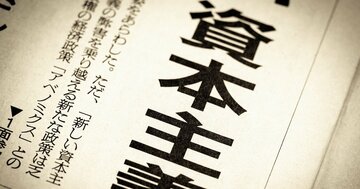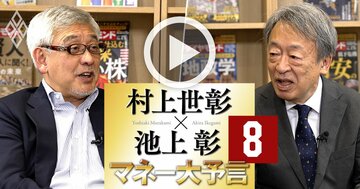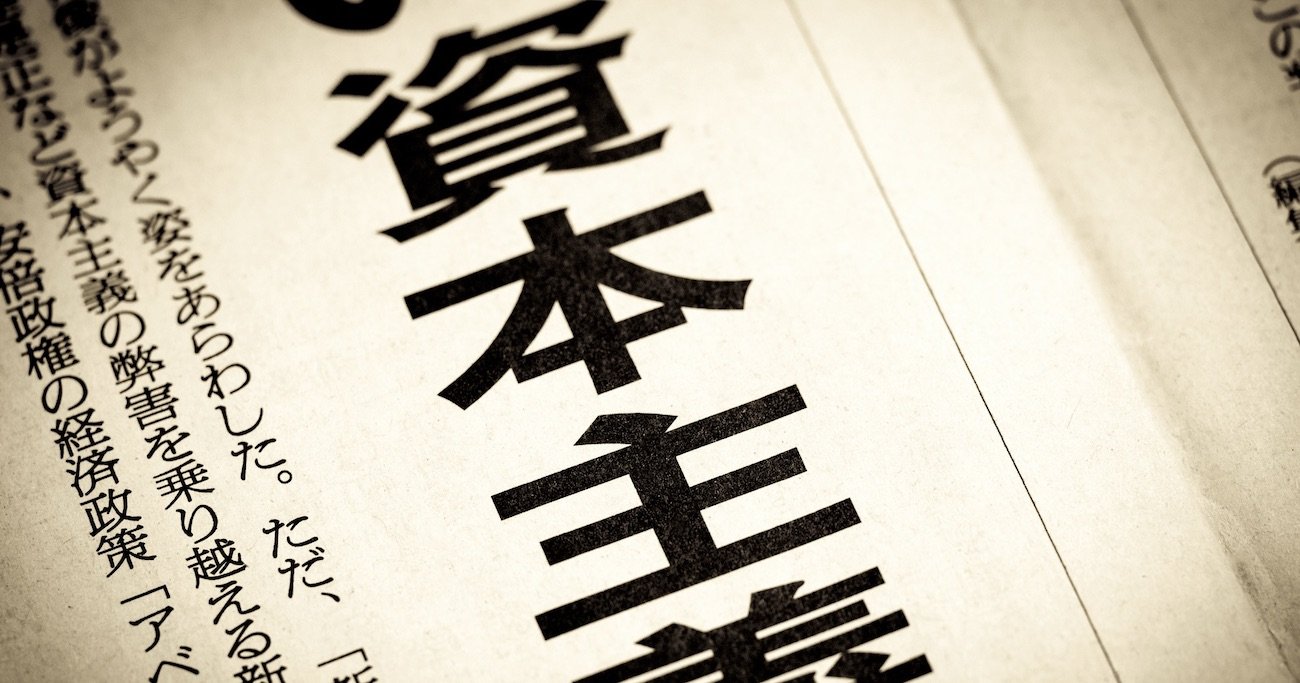 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
岸田文雄首相の看板政策とされた「新しい資本主義」は、もともと中身がなかったが、「異次元の少子化対策」という言葉に取って代わられた。そこで「新しい資本主義」という言葉を正式に「オワコン」にしてしまおうという提案を考えたところ、「資本主義」という言葉もなるべく使わないように自制した方がいいという考えに至った。その理由をお伝えしたい。(経済評論家、楽天証券経済研究所客員研究員 山崎 元)
忘れられた看板政策
「新しい資本主義」
岸田文雄氏が首相就任時に掲げた看板政策である「新しい資本主義」の影が薄い。正確には、政策として力の入った看板だったというよりは、言葉として調子のいい「フレーズの看板」だったのだろう。それでも、岸田首相は、昨年中は思い出したように、「新しい資本主義」を口にしていた。
ところが「異次元の少子化対策」という、中身は分からないものの勇ましい響きの言葉を思いついて、岸田首相はすっかりこのフレーズが気に入ってしまったようだ。官僚をはじめとする彼の周囲の人々も予算を引き出す理由に使えそうなこちらのフレーズに感心してみせるのだろう。
今や、「新しい資本主義」は言葉としての“現役感”を失いつつあるようだ。それならば、もともと中身がなかった「新しい資本主義」という言葉を正式にオワコンにしてしまおうではないかというのが本稿の提案なのだが、よく考えると、理由が二つあることに気が付いた。
一つは、日本の現実が「資本主義」という言葉でイメージされる制度では語れないことであり、もう一つはどうやら「資本主義」という言葉を使うことでわれわれは適切に経済を考えることができなくなっているのではないかということだ。
「資本主義」という言葉がつくづく曲者であるようだ。