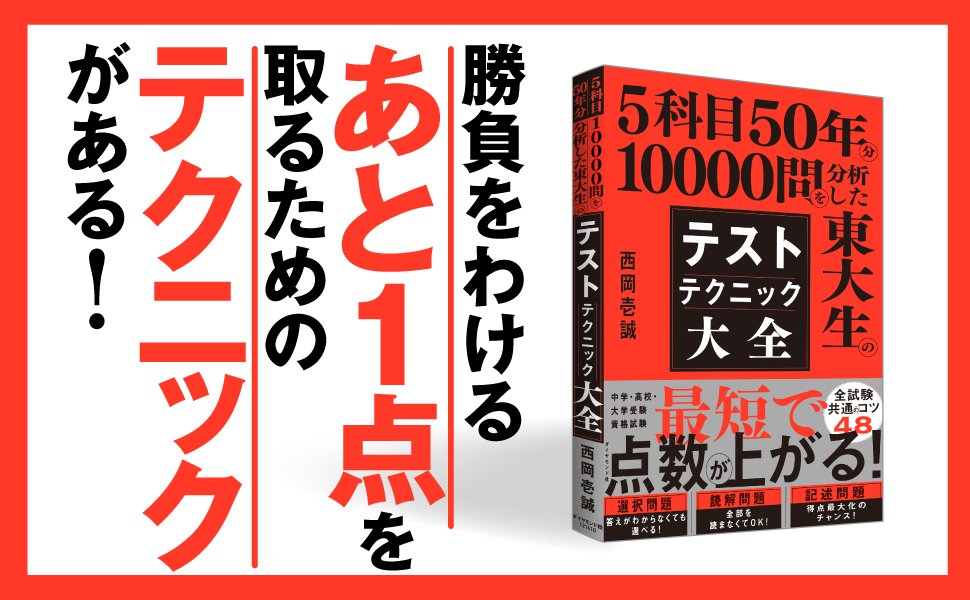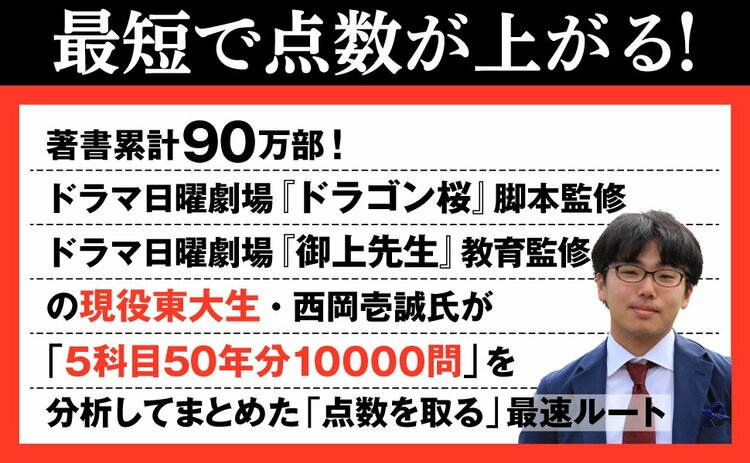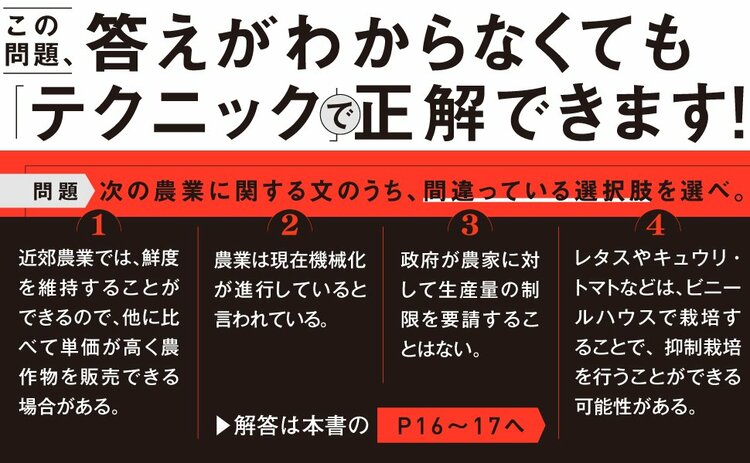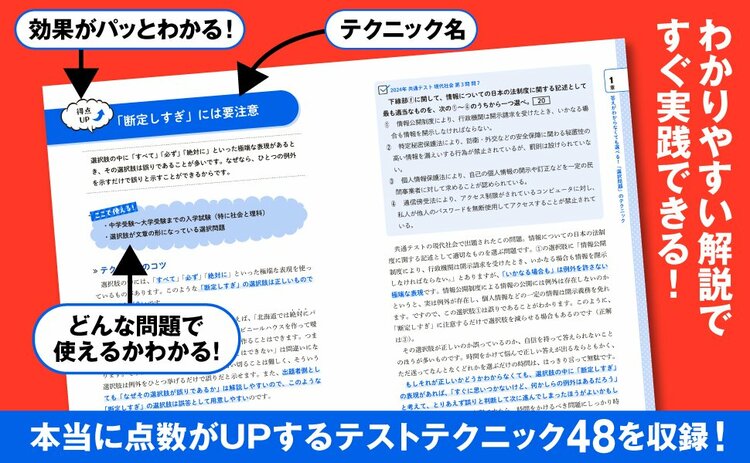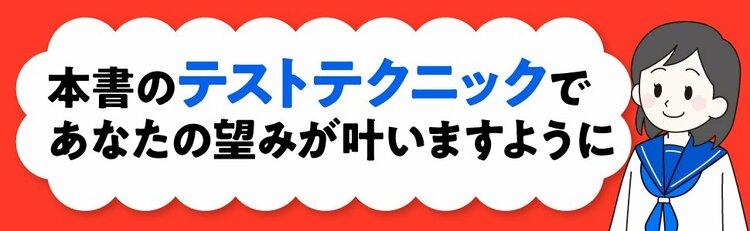勉強は「やさしさ」を学ぶもの
――なるほど。他にはどのようなことを生徒さんに伝えていますか?
辻:最近同僚の先生とお話ししていたときに、『国語だけでなく、すべての勉強が、「やさしさ」を学んでいるのなのではないか』という話になりました。たとえば、人に優しくなれないときというのは、多く相手のことを理解できていないときなのではないでしょうか。
それが何故なのかと言えば、相手がどう出てくるかが推測できないという不安にあるわけです。相手のことがわからないから不安になる。その不安を解消すること、理解できていない相手(世界)を少しでも理解しようとすること、それが勉強であれば、やはり勉強をするということは、知らない相手に歩み寄る「やさしさ」なのではないか、と。
――ということは先生は、国語という科目は、人にやさしくなれる作用があると考えているということですか?
辻:はい。たとえば、AくんとBくんが喧嘩をしたとします。原因を聞くと、Aくんは『Bくんにバカにされた』と答え、Bくんは『そんなことをしていない』と答えたとします。よくよく聞いてみると、BくんはAくんに『そんなことで悩んでいるなんて、バカみたいだな』と言っていたことがわかります。BくんはAくんの悩みを笑い飛ばしてあげようとしていて、それをAくんはバカにされたと解釈した、と。
このように、事実と解釈は違うものです。『バカみたい』という言葉を言ったのは事実でも、それを『バカにされた』と考えるのは解釈です。
――ああ、国語では「この登場人物がこう発言したときの気持ちとして正しいものを選べ」みたいな問題が多いですもんね。
辻:そうです。国語という教科は、『事実』と『解釈』の違いを学ぶものであると思っています。
たとえば雨が降っていたとして、その雨を嫌がってどんよりした気持ちになる人もいれば、雨によって気分が晴れやかになる人もいるでしょう。事実として雨が降っていても、その雨を『うれしい』と解釈することもできるわけです。
1つの事実に対して、解釈は多様です。そして、やさしい人というのは、事実と解釈を切り分けることができ、そしてさまざまな解釈ができる人だと思います。そうできると、恐れや不安、怒りなどの感情はなくなるのではないでしょうか。
――国語以外の科目でも、『人にやさしくなれる』という側面があるのでしょうか。
辻:私は国語の教員なので他の科目については門外漢ですが、他の科目の先生と話していて、そう感じます。たとえば地理であれば、その地域に住む人のバックグラウンドを知ることができるという作用がありますよね。世界史も併せて勉強していれば、その国の人がどんな歴史的背景の中で育ってきたのかを学べば、初対面であっても相手に寄り添うことができます。
学ぶということは、人にやさしくなることだと思います。