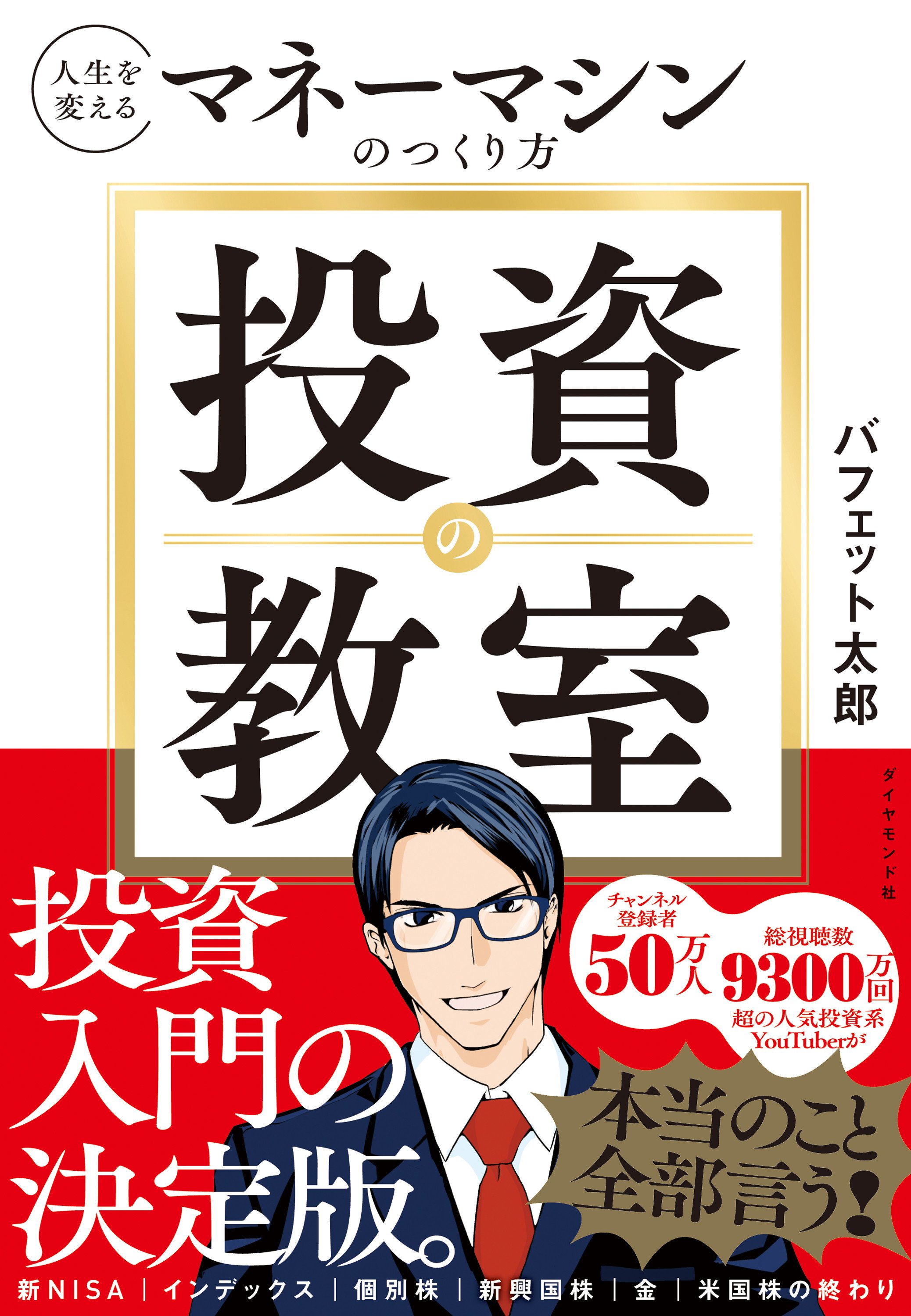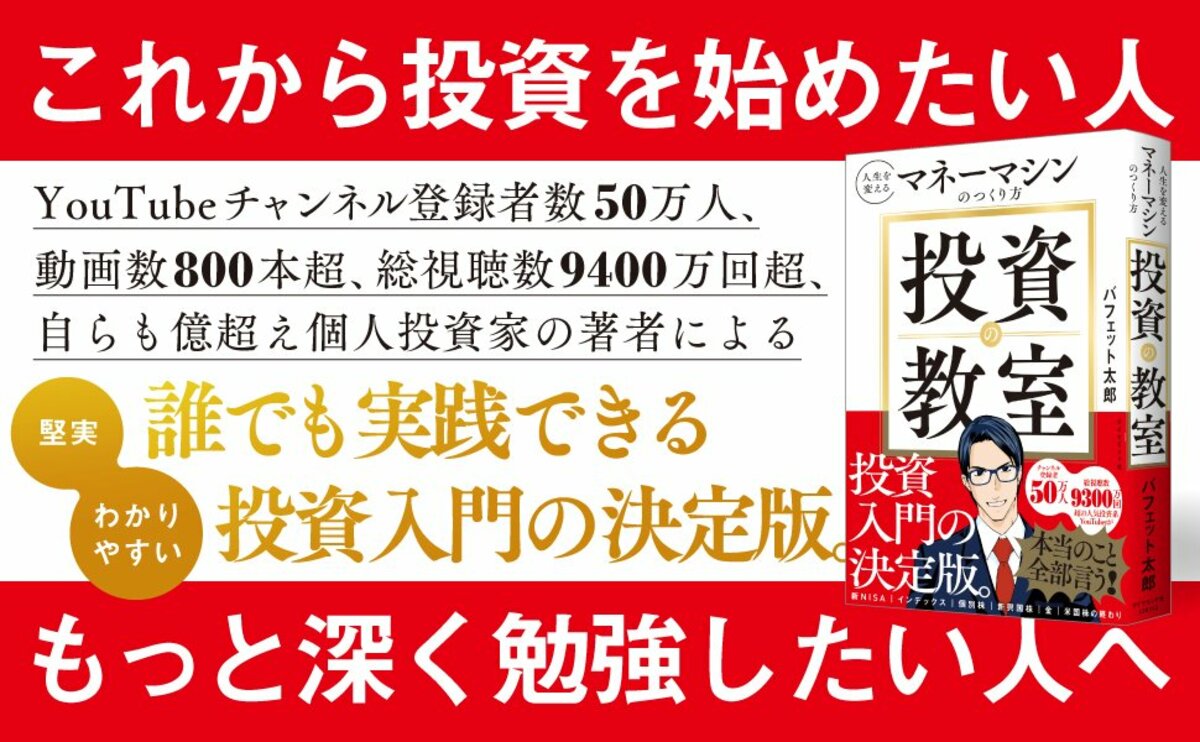いわゆる「トランプ関税」の影響で、世界各国の株式市場が急落している。
こうした「米国株インデックス投資ブームの終わり」をいち早く予見していたのが、チャンネル登録者数50万人、総視聴数9700万回の人気投資系YouTuber・バフェット太郎氏だ。
投資に役立つ世界の経済ニュースを独自の視点からわかりやすく解説し、冷徹な市場分析と鋭い舌鋒で予想を次々に的中させる一方で、その投資スタイルは堅実で実践しやすいと投資初心者から経験者まで幅広い支持を集めている。
そんな同氏の新刊『投資の教室 人生を変えるマネーマシンのつくり方』(ダイヤモンド社)は、お金を生み続ける「マネーマシン」のつくり方と考え方、新NISAの鉄則や個別株や新興国株、金やビットコインなどの投資の基本を凝縮した一冊だ。その一部を抜粋・編集し、お届けする。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
投資ブームには必ず“終わり”がある
ぼくはこれまで、長期的な資産形成を成功させたいだけなら、米国株への積立投資が良いと主張してきましたが、それはあくまで長期的に見ればの話であり、常に最高の投資成果が約束されているわけではありません。
とりわけ、投資ブームというのは景気後退局面を乗り越えて続くことは稀で、ほとんどの場合、米経済の景気後退とともに終わりを迎える傾向がありますから、2009年6月から始まった米国株の時代は、これから訪れる景気後退とともに終わりを迎え、次の景気拡大局面では全く別の投資対象がブームになる可能性が高いです。
1970年代:金の時代
たとえば、歴史を振り返ると1970年代は金がブームになりました。
1971年8月、当時のニクソン大統領がドルと金の交換を停止すると発表したことで、ブレトンウッズ体制が崩壊しました。
ブレトンウッズ体制とは、国際通貨制度のことで、各国の通貨を米ドルに対して一定の交換比率で固定し、米ドルは金1オンス35ドルで固定するというものでした。
ブレトンウッズ体制の崩壊により、ドルは金の裏付けがない不換通貨となり、米国は保有する金の量に関係なく、「好きな時に好きなだけ」ドルを発行できるようになりました。
しかしその結果、高インフレによって金が高騰し、35ドルだった金価格は1980年に875ドルと25倍になったのです。
その一方で、1970年代のS&P500はわずか17%の上昇に留まりました。
1980年代:日本株の時代
1982年11月から始まった景気拡大局面では日本株がブームになりました。これは高度経済成長期が続く中で、日銀が金融緩和策を実施したことから景気が過熱したためです。また、85年のプラザ合意により円が急騰し、内需が拡大したことも日本経済の追い風になりました。
1980年1月、6569円だった日経平均株価は1989年12月末にかけて3万8915円とおよそ6倍に、ドル建てではおよそ10倍にもなりました。
その一方で、S&P500はおよそ3倍の上昇に留まり、前回の景気拡大局面でブームだった金はピークから半値になりました。
1990年代:米国株の時代
1991年3月、米経済は湾岸戦争に伴う景気後退局面が終わりを迎え、その後、120か月にわたる長期景気拡大局面と、ハイテク株を中心とした米国株の時代が始まりました。
当時、FRBの高金利政策を背景に、1994年のメキシコ通貨危機、1997年のアジア通貨危機、1998年のロシア危機と、新興諸国が相次いで通貨危機に陥りました。こうした中、世界の投資マネーは相対的に金利の高い米国に一極集中し、ドットコムブームが加速しました。
1990年1月、454.82だったナスダック総合指数は、2000年3月に一時5132.52と、およそ10年で11倍超値上がりしました。
また、S&P500も1553.11と、1990年1月の353.4からおよそ4倍値上がりしました。
その一方で、前回の景気拡大局面でブームになった日本株は同じ期間に48%下落し、ドル建てでは27%下落しました。
2000年代:新興国株の時代
2000年にドットコムブームが崩壊し、2001年11月から始まった景気拡大局面では、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)をはじめとした新興国株がブームになりました。
投資家はドットコムブーム崩壊のトラウマから米ハイテク株を避け、「長期投資をするなら成熟した先進国株よりも、成長余地の大きい新興国株の方が大きなリターンが期待できる」と考えるようになりました。
その結果、新興国株にまとめて分散投資をすることができるiシェアーズ・MSCI・エマージング・マーケットETF(EEM)は、2001年11月から2007年10月までのわずか6年間で5倍超値上がりしました。
その一方で、前回の景気拡大局面でブームだったナスダック総合指数は、同じ期間に約7割の上昇に留まったほか、2000年のピークからは4割超値下がりしたままでした。
2010年代:米国株の時代
そして、2009年6月から始まった景気拡大局面では、AppleやAmazon、Googleをはじめとした米国株がブームになり、その後、投資家はGAFAを永久保有するだけでお金持ちになれると信じるようになりました。
2020年のコロナ危機にわずか2か月の景気後退局面があったものの、それを除けば、2009年6月から2024年6月末にかけて、S&P500はおよそ6倍に、ナスダック総合指数はおよそ10倍にもなりました。
その一方で、2000年代の景気拡大局面でブームになったiシェアーズ・MSCI・エマージング・マーケットETF(EEM)は2024年6月末時点で42.59ドルと、2007年10月のピークからわずか9%の上昇に留まりました。
このように、投資ブームというのは景気後退局面を乗り越えて続くことは稀で、ほとんどの場合、米経済の景気後退とともに終わりを迎える傾向があります。
そのため、米経済が景気後退入りすれば、マグニフィセント・セブンを中心に米国株は停滞局面を迎え、次の景気拡大局面では、全く別の国や地域、投資対象がブームになる公算が大きいです。
そのため、個人投資家が次の景気拡大局面で資産を大きく増やしたいなら、米国株だけではなく、全く別の国や地域、投資対象にも注目しなければなりません。
(本稿は、『投資の教室 人生を変えるマネーマシンのつくり方』を抜粋、再構成したものです)
バフェット太郎(ばふぇっと・たろう)
投資に役立つ世界の重要な経済ニュースを厳選し、独自の視点からわかりやすく解説する、登録者数50万人のYouTubeチャンネル「バフェット太郎の投資チャンネル」管理人。冷徹な市場分析と鋭い舌鋒で、次々と予想を的中させる投資系インフルエンサー。Xフォロワー35万人。noteフォロワー1.4万人。
個人投資家としては、20代から投資を始め、数百冊の投資本をむさぼり読み、10年間さまざまな試行錯誤を積み重ね、米国株投資にたどり着く。ブロガー・YouTuber活動と並行して堅実な投資を続け、それから数年で数億円の金融資産を築く。
著書に『投資の教室 人生を変えるマネーマシンのつくり方』(ダイヤモンド社)、累計20万部のロングセラー『バカでも稼げる「米国株」高配当投資』(ぱる出版)がある。
・YouTube youtube.com/@buffett_taro
・X x.com/buffett_taro
・note note.com/buffett_taro