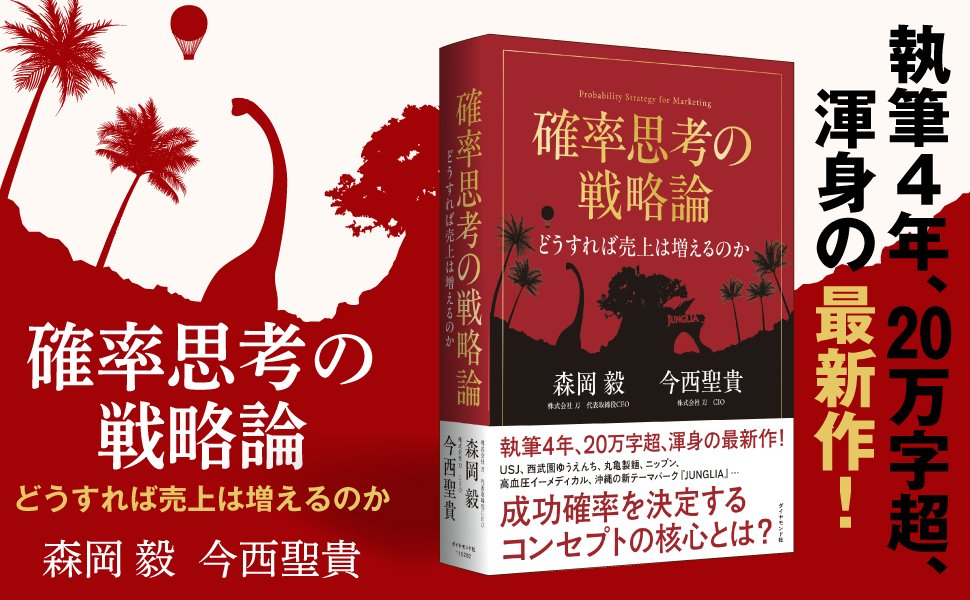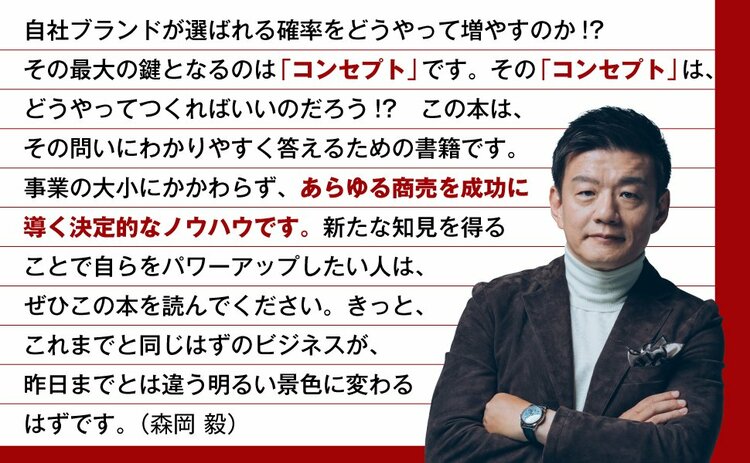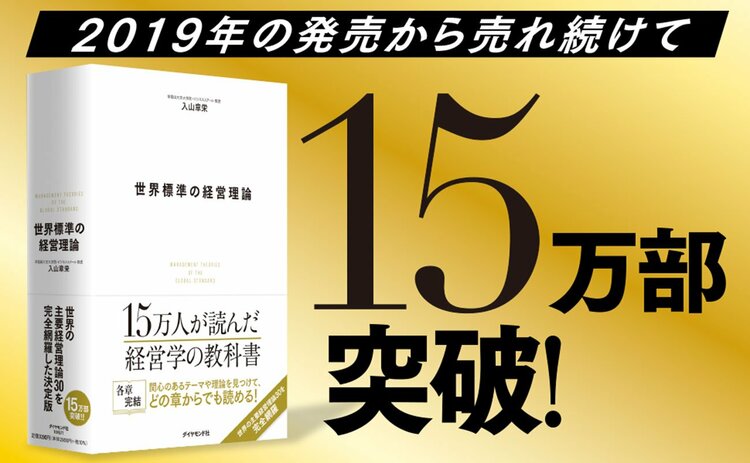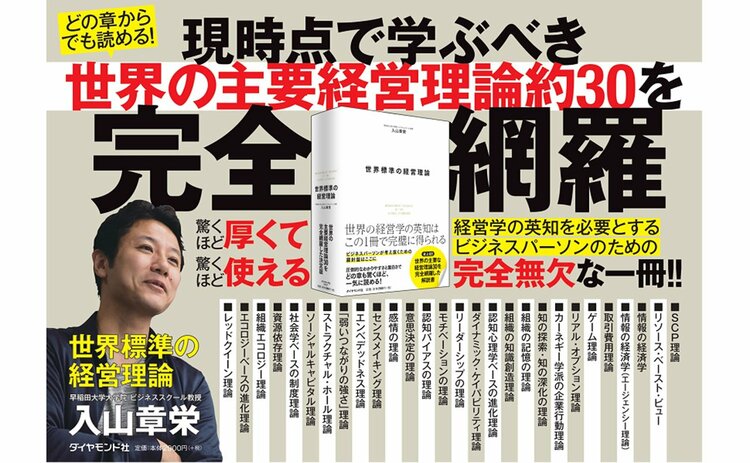マーケティングをアートよりも科学に近づけたい
入山 またちょっと脱線しますが、経営学というのは「人ってなんなの?」を突き詰める学問だと私は思っていまして、実際に認知心理学や神経科学、社会学などの考え方を取り入れるようになってきてますよね。この先、経営学はもう一段発展すると思っていて、おっしゃるような生理的な知見や遺伝子の構造や原理も取り入れていくことになるだろうなと。森岡さんはすでに、そこに到達されてるわけですね。
森岡 確率を考えるとき、サイコロがどこで振られるかというと、人間の脳なんですよね。脳が物事を選択するとき人間の神経回路の構造がどうなっているのかを、人の行動を実測して統計的に処理して仮説を立てるというアンドリュー・アレンバーグ(著書『Repeat Buying: Theory and Applications』等でも知られる数学者であり経営学者)の実績に、私は非常に感銘を受けました。彼のモデルが美しいと思って、自分のビジネスにどう当てはまるかをやってきたんです。人が頭の中で何かを判断するとき、人間の神経回路の構造自体に大きな違いがあるわけではないから、そこには普遍性があるんじゃないかと思って。
入山 たしかに、人間の物理的な構造にそう大きな違いはないはずですよね。
森岡 ですよね。10円のガムを買うときも、何百万円の車を買うときも、結婚相手を選ぶときも、テレビやYouTubeのチャンネルを選ぶときも、みんな同じ神経回路を使っているとわかれば、この回路の構造を読み解くと、逆に、商品・サービスが選ばれやすくなるために、どういう順番で人の頭の中に情報を入れていけばどんな音が鳴るのかを、狙って仕掛けられるようになる。マーケティングの成功の確率が上がりますよね。
感覚的にとらえるマーケティングが横行していて、センスがある人は素晴らしいし羨ましいですけど、自分はその土俵では勝負できないので、私が得意というより好きな、再現性のある方法で、マーケティングをアートよりも科学に近づけたいんです。
入山 本当の科学ですね。
森岡 私の手法だと再現性を担保したいので、数式や言語を体系化することが前提なんです。ということは、書籍にまとめたり、人が人に継承しやすい、というメリットがあります。
入山 つまり、森岡さんの考え方を惜しみなく開示して、その結果、日本全体が底上げされたらいい、とお考えなんですね。
森岡 そうです。私なりに蓄えてきて、ある程度まで確からしいとわかったものは開示して、誰かのお役に立てばうれしい。私の頭の中に蓄えて、私たちだけで利用していても、その先には何も見えない。マーケティングは、誰かの役に立つ学問であるべきだと思うんです。
入山 素晴らしいですね。
<4月28日に【森岡毅×入山章栄対談(2)】「結果が出る人」と「うまくいかない人」の”努力の中身”の決定的な違い を公開予定>