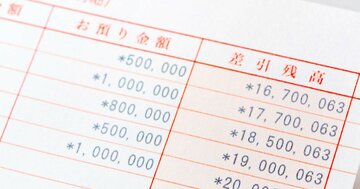【要注意】遺言書を国に預けるとき、絶対やるべき“たった1つのこと”
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
遺言書は、国に預けることもできます
お盆の時期、ご家族で相続について話し合われたご家庭も多いかと思います。本日は、遺言書についてお話しします。
2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度がスタートしました。早速、私自身の遺言書も預けてきたのですが、率直な感想は「思ったより大変だったな」です。
自分で遺言書を作成し、法務局の人が「氏名、日付、押印」があることを確認して、ぱっぱっぱと終わる手続かと思っていました。しかし実際には、遺言書保管制度独自のルールがあり、一から書き直すことになったため、法務局に2回も足を運ぶことになりました。ここでは、遺言書保管制度の注意点を中心にお伝えします。
5つの書類を用意します
まず、遺言書保管制度は事前予約制です。予約を取らずに法務局に行っても保管できません。法務局は、ご自身の①本籍地、②住所地、③所有する不動産の所在地を管轄する法務局の中から選ぶことができます。予約は電話だけでなく、インターネットからでも可能です。予約が取れたら、次に必要書類を準備します。
必要書類:
① 自筆証書遺言
② 申請書(法務省のホームページからダウンロード、または法務局の窓口でもらえる)
③ 住民票(本籍地の記載入り、発行から3か月以内のもの)※マイナンバーの記載は不要
④ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
⑤ 収入印紙(3900円)※収入印紙は法務局で売っているので、事前に買わなくてOK
自筆証書遺言と申請書の書き方には、注意点がたくさんあり、ここではすべてを解説できません。日付や氏名を書くことはもちろん、A4の紙を使用することや、余白を残さなければいけないことなど、遺言書保管制度独自のルールがあるので、必ず事前に保管制度の手引きを確認しましょう。
事前の電話確認がオススメです
わからないことがあれば、当日窓口で聞くより、事前に電話で確認しておきましょう。内容によっては、用意した遺言書をすべて書き直すことになるかもしれません。実際に私がそうでした。
私のケースでは、「私の財産のうち、所有する法人の株式を、相続発生時の会社役員に遺贈する」という内容の遺言書にしたかったのですが、保管制度を利用する場合、相続人以外の人に財産を渡す(遺贈)場合には、渡す人を特定したうえで、その人の住所を登録しなければいけないそうです。そのため、「相続発生時の会社役員に」というくくりだと保管制度は利用できないのです。ちなみに、公正証書遺言であれば、このような書き方でも問題ありません。
手続きにかかる時間は?
遺言書の保管申請が受理されるかどうかは、法務局の人が事細かにチェックするため時間もかかります。私の場合には、窓口に行ってから手続が完了するまで1時間以上かかりました。次の予約の人も控えていますので、書き直しになった場合や必要書類に不備があった場合には、また別の日に予約を取り直して再度足を運ぶことになります。何度も足を運びたくない人は、事前に内容確認をしっかりと行わないといけませんね。
絶対やるべきこと、それは「遺言書のコピー」
無事に保管の申請が受理されると、「保管証」という紙が発行されます。「この紙は失くさないように」と言われますが、万が一失くしてしまっても、保管されている遺言書の効力が無くなることはありません。ただ、遺言書の書き直しや撤回をしたいときに手続が煩雑になるので、失くさないようにしましょうね。
なお、遺言書の保管が受理された場合、預ける遺言書のコピーなどは発行してもらえません。そのため、どのような内容の遺言書だったかを忘れないようにするために、最終的に預ける前に遺言書の写真を撮っておくか、コピーを残しておくのをオススメします。
相続発生時の流れ
保管制度を利用した人に実際に相続が発生した場合には、相続人は法務局に行き、保管されている遺言書の写しの発行を受けることができます。この場合、相続人のうちの1人が申請すると、法務局から他の相続人や受遺者(遺言によって財産をもらう人)に対して、遺言書が保管されている旨の通知が郵送されます。
ゆくゆくは、役所に死亡届が出された時点で、役所から法務局にその情報を転送し、自動的にすべての相続人に通知される仕組みを導入するそうです。
付言事項について
ちなみに遺言書には「付言事項」という、法的な効力はないものの、家族への想いや願いを書くこともできます。これまでの感謝の気持ち等を遺言書に残すことによって、ちょっとしたサプライズの手紙にすることもできるかもしれませんね。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)