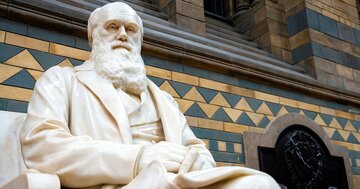ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、読者の「頭の中」に、実際に『種の起源』を読んだ後と同じような記憶が残る画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊される。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
第二次世界大戦中の兵士に起きたこと
たいていの場合、母乳は女性が分泌するものだ。しかし、男性が母乳を分泌することも、まったくないわけではない。たとえば、第二次世界大戦中の話だが、栄養不足に陥った男性の捕虜が、リハビリ中に乳汁を分泌したことが報告されている。
この捕虜は抑留されているあいだにいくつもの臓器が機能不全になっていたので、ホルモンのバランスが崩れていたことが原因とされている。
また、向精神薬などによって男性でも母乳の分泌が誘発されることはあるし、とくに原因がなくても乳汁を分泌する男性が少数いることも知られている。
コウモリのふしぎな機能
人間ではないが、マレーシアに生息するダヤクフルーツコウモリの場合、半分以上のオスが乳汁を分泌するらしい。ダヤクフルーツコウモリのオスには、発達した乳腺組織があるので、乳汁を分泌しても不思議ではない。
ただし、オスの乳汁の量はメスに比べて1.5パーセント程度に過ぎないし、オスが子に授乳している姿が観察されたことはないので、実際にオスが子を育てるために授乳している可能性は低いと思われる。
これらの事実からわかることは、オスが授乳して子育てをする種はいないけれど、オスが授乳するように進化すること自体は可能だ、ということだ。
それでは、なぜオスは授乳しないのだろう。とくに私たちヒトは、オスも子育てをする種なのだから、オスも授乳できたほうが何かと便利だと思われるのだが。
興味深い仮説
仮説の一つは、父親の不確実性だ。母親が産んだ子は確実に母親の子だが、父親にとっては、どの子も確実に自分の子である保証はない。
たとえ一夫一妻であっても、100パーセント自分の子だとはいえない。そのため父親は、乳汁を分泌してまで、子育てに協力しないというのである。しかし、おそらくこの仮説は間違いだ。
ハトの子育て
ハトは一夫一妻で、父親も子育てをする。そしてハトの場合は、母親だけでなく父親も授乳する。もっとも、ハトの乳汁はヒトの乳汁とは違って、喉から剥離した細胞でできており、ハト乳(にゅう)と呼ばれるが、とにかく父親も授乳するのだ。
そして、一夫一妻のハトの場合も、母親が産んだ子が100パーセント父親の子である保証はない。でも、100パーセントである必要はないのだ。90パーセントでも80パーセントでもよいのだ。
たいてい自分の子であれば、父親の授乳や子育ては進化するのである。
過去に目を向ける
したがって、100パーセントではないにしても比較的一夫一妻が多いヒトの場合、男性も授乳できるほうがよいと思われる。それでは、あらためて、なぜオスは授乳しないのだろうか。
その理由は、現在だけを見ていてはわからないけれど、過去を見ればヒントがある。ヒトは昔から一夫一妻で、オスも子育てをしていたわけではない。
ヒトは類人猿から進化したが、人類の祖先であるその類人猿は、おそらく一夫一妻でなく、子育てもしなかったのだろう。そのため、ヒトが進化したとき、すでに乳腺は退化していたのだ。
その結果、オスの子育てにおける役割は、餌を探してきたり肉食動物が来ないか見張ったりすることになり、授乳にはならなかったのだろう。
私たちヒトも含め、生物は過去から進化してきた歴史的存在である。そのため、現在だけを見ていてはわからないこともある。
そういうときは、過去に目を向けることも必要だろう。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』の著者による書き下ろしです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。