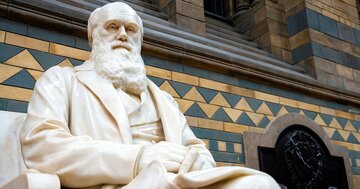ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、読者の「頭の中」に、実際に『種の起源』を読んだ後と同じような記憶が残る画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊される。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
種子は海水に浸かっても生きている
ダーウィンは、『種の起源』において、生物の移動能力は予想以上に高いと答えている。
バークリー氏の協力を得て、私がいくつかの実験をしてみるまでは、植物の種子が海水の中でどれくらい耐えられるか、ということさえ知られていなかった。しかし、実験の結果は驚くべきもので、海水に28日間浸した87種類の種子のうち、64種類が発芽したのだ。また、137日間浸した場合でも、数種類は生きていたのである。(358頁)
ダーウィンは、生物の移動能力が高いことを示すために、いくつかの実験を行っている。
植物の種子は海流に乗って…
これは、そのうちの一つで、長期間海水に浸されても、植物の種子の発芽能力が失われないことを示している。つまり、植物の種子は、海流に乗ってかなり遠くまで移動できるというわけだ。
さらにダーウィンは、以下のような思考実験によって、生物が北半球から南半球へ移動することさえありそうだと述べている。
ごく近い地質時代に中央ヨーロッパや北アメリカが極地のような気候であったことについては、生物学的なものから非生物学的なものまで、考え得るかぎりのあらゆる証拠が揃っている。スコットランドやウェールズの山々において、山肌が削られて谷になっていたり、岩の表面が磨かれていたり、高地に丸石があったりするのは、その地の谷間が最近まで氷河に覆われていたことを示しており、それらは家の焼け跡が火事の証拠である以上に明白な氷河の証拠である。(366頁)
もっとも寒冷だった時期には、温帯の生物が熱帯の低地にまで侵入して、そこを越えたことは確かだと思う。(中略)このようにして氷期のあいだに、多数の植物や少数の陸生動物やいくらかの海生動物が、北半球あるいは南半球の温帯域から熱帯域に侵入して、その一部は赤道を越えたと私は考えている。
その後、気候が暖かくなると(中略)、赤道を越えた種類は、反対側の半球の温帯域へ移住することによって、元の生息地からはますます遠ざかることとなった。(378~379頁)
北半球の温帯に棲んでいる生物が、氷期には熱帯に移動することもあっただろう。
そして、ふたたび温暖化したとき、その生物は、北半球の温帯に戻るのではなく、南半球の温帯に移動することもあったかもしれない。
そうすれば、ある生物が、北半球から南半球まで分布を広げても不思議はないというのである。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を編集、抜粋したものです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。