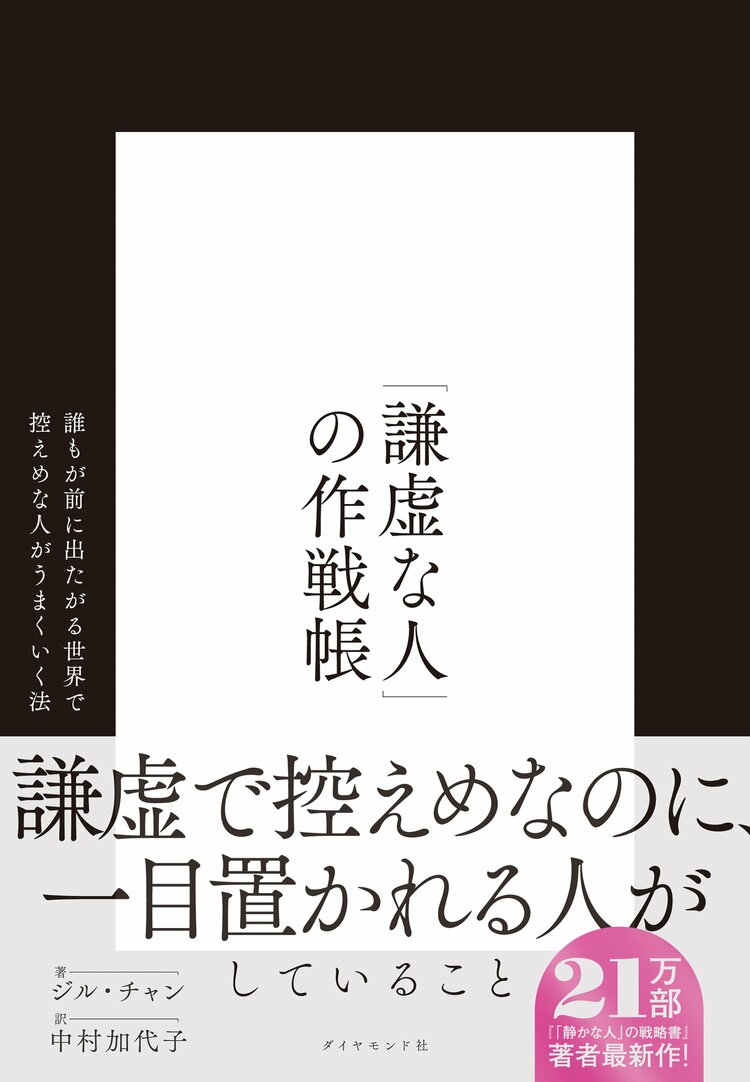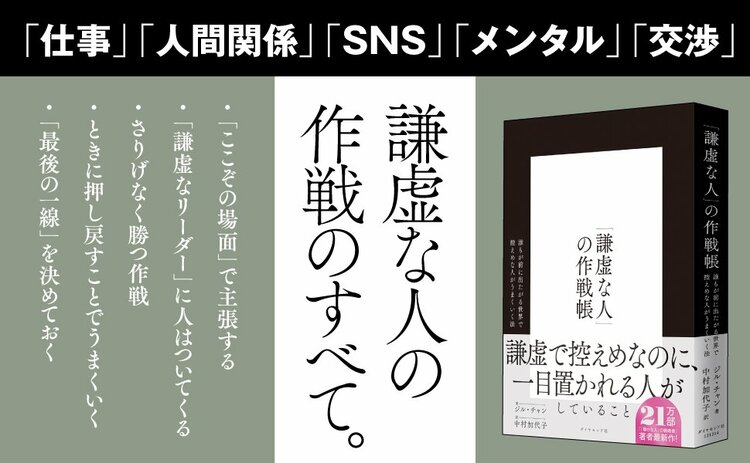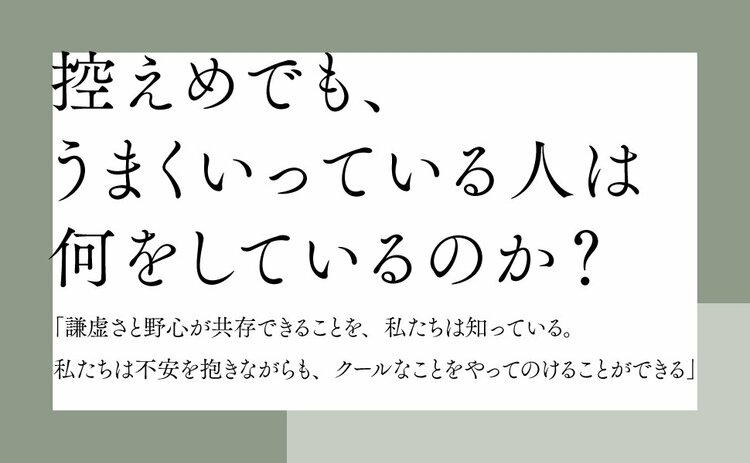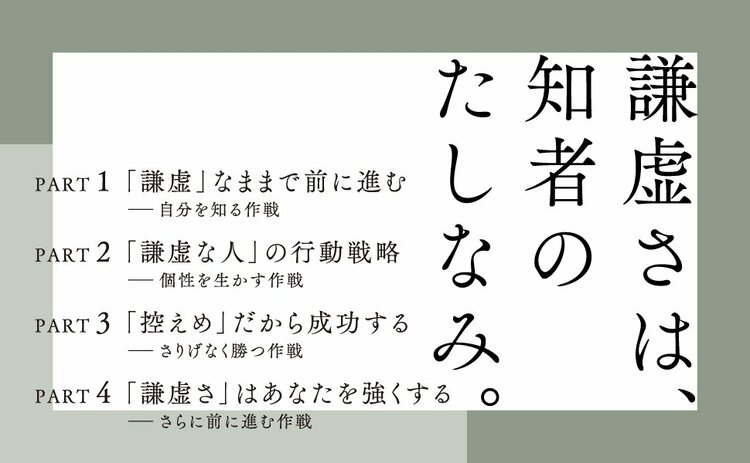『「静かな人」の戦略書』が世界で話題となり、日本でも20万部を超えるベストセラーとなったジル・チャンさんが、新作『「謙虚な人」の作戦帳――誰もが前に出たがる世界で控えめな人がうまくいく法』を携えて来日した。
アジアでは美徳とされる「謙虚さ」は、「自己不信」という弱みと表裏一体だ。謙虚さが行きすぎると、周りから評価されても「周囲は自分を誤解している」「自分はこのポストにふさわしくない」などと思い込んでプレッシャーを感じてしまう、いわゆる「インポスター(詐欺師)症候群」になってしまう人もいる。
多くのビジネスパーソンが抱えるこの課題に対して、今作でも自身の体験から引き出された具体的な「作戦」を余すところなく紹介しているジルさん。さっそく、そのエッセンスを語ってもらおう。(構成/藤田美菜子)
 ジル・チャン氏(Photo by Wang Kai-Yun)
ジル・チャン氏(Photo by Wang Kai-Yun)
「自分は評価に値しない」と思ってしまう
――「静かな人」に続く新作のテーマに「謙虚な人」を選んだ理由は?
ジル・チャン(以下ジル):私が考える「謙虚な人」とは、自分とは異なる考え方に対して寛容な人のことです。
謙虚な人たちは、他人の話に耳を傾けることができます。他人と協力することに対してオープンで、自分を物事の中心に置かず、常に周囲に注意を払います。そして、何か決断を下すときは、自分の考え方に偏ったところがないか、慎重に振り返ります。
その反作用として、そうした人たちは、時として謙虚すぎることがあります。その結果、十分に自信が持てず、「自分は周りからの評価に値しない」と落ち込んだり、大きな仕事を前にしても「この仕事は自分の身に余る」などと尻込みしたりしがちです。
前作の『「静かな人」の戦略書』もそうでしたが、私が本を書くときは、自分自身がキャリアや人生で遭遇した大きな困難をテーマにしています。謙虚であるがゆえに自信を喪失してしまうという問題は、私自身が必死に克服しようとしてきたことなのです。
ですから、世の中の謙虚な人たちが、私が味わったような悩みや苦労をいちいち経験しなくても済むように、この本では自分の体験を共有することにしました。
「もっとよくなろう」と考えて成長する
謙虚な人には、多くの強みがあります。
なかでも最大の強みは「成長志向」です。謙虚な人は、「自分はまだまだ十分じゃない」と考えがちなので、今よりもっといい仕事をしたい、もっと物事を改善できる方法はないだろうかと常に考えようとします。これは今日の職場環境において最も競争優位性のある特徴だと思います。
さらには、先ほど述べたような「傾聴力」はコミュニケーションの場面で大きな力を発揮しますし、自信のなさゆえに「準備を怠らない」点も、目標達成の可能性を高める上で大きく寄与するでしょう。
こうした強みを最大限に生かすために、謙虚さゆえの弱みを克服する方法を知ってほしいと思いました。心の備えがあれば、より多くの謙虚な人が、もっと若いうちに、もっと多くのことを成し遂げることができるはずです。
できるだけ「ハードル」を下げようとしてしまう
――改めて、謙虚な人ならではの「弱み」とは?
ジル:最大の弱みは、なんと言っても「自己不信」です。謙虚な人は、自分自身について丁寧に何度も振り返りを行うことが習慣になっていますが、振り返りとは常に自己不信を伴うものです。なので、結果的に自信を喪失しやすいのです。
2つ目の弱みは、自分で目標を設定できるとき、謙虚な人は「守りに入る」傾向があることです。リスクを好まず、期待されすぎるのも苦手なので、ほぼ確実に目標を達成できるように、ハードルを下げようとする傾向があります。これは、ビジネスシーンにおいては必ずしも有効な戦略とは言えません。
3つ目の弱みは、謙虚な人は「働きすぎる」傾向があるということです。何も間違いが起きないようにするために、常に120%、150%の努力を注ぐので、最終的に燃え尽きてしまいがちなのです。
毎日、うまくいったことを記録する
――「自己不信」はどうすれば克服できるでしょうか?
ジル:私自身が行っている作戦を、小さなものから大きなものまで3つご紹介しましょう。
最も手軽な作戦は、毎日うまくいったことをメモして記録することです。どんなに些細なことでも構いません。例えば、本当にばかばかしいことですが、私にとっては毎朝起きて玄関から出ることは成功体験です。人と関わるのが苦手なので、外に出て誰かと話すことができれば、それだけで万々歳なのです。
どんなに小さな出来事にも記録する価値はあります。将来、何かに挑戦することになって、それができるかどうか自信がないときは、いつでも記録を振り返ればいいのです。そこに書かれていることはすべて、実際に起きたことであり、自分に「できること」の証拠です。
そうやって自分に対して胸を張れるようにしておくのが、私が使うトリックの一つです。
「もう1人の自分」という味方をつくる
2つ目の作戦は「もう1人の自分」を持つことです。本人より客観的で、冷静で、中立的なバージョンの自分を相談相手にするのです。悩んでいるときや壁にぶつかったときは、この中立的な自分と頭の中で対話します。
例えば、自信がどんどんなくなっているときや、失敗するのが怖くて足がすくむような思いをしているとき、もう一人の自分はこんなふうに私に話しかけます。
「ねえ、あなたは前にもこれをやったことがある。ちょっとやり方は違うかもしれないけれど、本質は同じ。だから、準備して臨めばきっとできる」
このささやかな対話は、私が本来の自分――自己不信に襲われていない、ニュートラルな自分――に戻ることを助けてくれます。
3つ目の作戦は、これが最も強力なのですが、自分が弱っているときにサポートしてくれる仲間やパートナーを持つことです。私の身近にも、謙虚な人だけで構成された「アベンジャーズ(最強チーム)」がいます。といっても2、3人の小さなグループですが(笑)。みんな同じような考え方の持ち主なので、私が何に悩んだり迷ったりしているのか正確にわかるのです。
自己不信がひどくなってニュートラルな自分を保てないとき、私は彼らに連絡します。彼らは私が心から信頼している人たちなので、時にはたった一言の励ましや5分間の会話だけでも、すごい効果を発揮するのです。
「声の大きな人」にどう対処する?
――謙虚な人は、自分とは正反対な「声の大きな人」の前ではどう振る舞えばいいと思いますか?
ジル:謙虚な人の中にも外向的なタイプと内向的なタイプがいます。とりわけ内向的な人にとって、「声の大きな人」は苦手な相手です。というのも、内向的な人は自分を売り込むのが苦手なので、自分の功績を十分にアピールできず、主張の強い人においしいところを持っていかれがちだからです。
そこでまず私がすることは、自分の功績を伝える別の方法を探すことです。声の大きな人のように、会議室で大っぴらに主張することはできなくても、上司との1on1の場でならうまく伝えることができるかもしれません。「実際に何々をしたのは私で、これがその記録です」といった具合に、根拠も示せればいいですね。
2つ目の作戦は、友人の1人から教わったことですが、会議室で常に最初に発言することです。大したことのない内容でも、ぜんぜん準備ができていなくても、とにかく最初に手を挙げる人になるのです。
これは私自身の経験からも言えるのですが、周りの人はあなたがどれだけ考え抜いて発言しているかとか、どれだけアイデアが優れているかといったことではなく、単に「会議で最初に発言した」ということであなたを評価します。
話を聞かずにまくしたてる人を止められる一言
最後に、3つ目の作戦として、声の大きい威圧的な人や感情的な人に対処するための「決めゼリフ」も紹介しておきましょう。
彼らはとにかく喋りつづけますが、そのすべてが理にかなっているわけではありません。そこで私がいつも使うセリフは「一歩引いてみましょう。この会話の目的は何でしょうか?」です。
多くの場合、そうした人は考えながら話し、話しながら考えます。だから、会話が間違った方向に進んでしまいがちなのです。そこで、静かで謙虚な人が一歩引いて全体を見渡せば、本当に解決したいことや、直面している問題の本質へと議論を引き戻すことができます。
これは、ぜひ謙虚な人にお勧めしたい作戦の1つです。何かあったら「少し引いてみましょう」と言ってみる。そうすることで、あなたは会議室の中でも「冷静で賢い人」であることを示せます。
(本記事は、『「謙虚な人」の作戦帳』の著者、ジル・チャン氏へのインタビューをもとに構成しました)