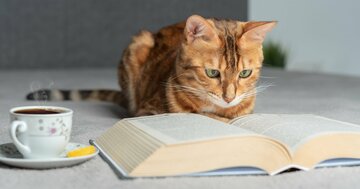ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
そもそも「生存闘争」とは?
「生存闘争(STRUGGLE FOR EXISTENCE)」。『種の起源』の中で、この言葉ほど誤解されているものはないだろう。
「生存闘争」という言葉を聞けば、肉食獣同士が闘って一方が殺されたり、ライオンがシマウマを殺して食べたりする残酷な場面をイメージする人が多いのではないだろうか。
もしかしたら、優しい性格のあなたは、こんなことを思っているかもしれない。
「私は、これからかぎりなく優しい気持ちを持って、みんなと仲良く助け合って生きていくことにしよう。ダーウィンが言うところの生存闘争みたいなことは、絶対にしないぞ」
しかし、残念ながら、そういうことはできないのだ。いや、「かぎりなく優しい気持ちを持つ」ことはできるだろうし、「みんなと仲良く助け合う」こともできるだろう。
この世界の過酷な現実
だが、それでも「ダーウィンが言うところの生存闘争」をしないわけにはいかないのだ。なぜなら、あなたは「生きて」いるからだ。
あなたがどんな生き方をしようと、とにかく生きているかぎり、あなたは生存闘争から逃れることはできない。それでは、ダーウィンの言葉に耳を傾けてみよう。
私は生存闘争という言葉を、広い意味で比喩的に使っている。ある生物が他の生物に依存することや、生き延びるだけでなく子孫を残すことも生存闘争に含まれるのだ。
たしかに、二頭の飢えた肉食獣が、食物を手に入れて生き延びるために闘うことも生存闘争だが、砂漠の縁に生えている植物の生存が水分に依存している状態も、生きるために乾燥に対して闘争していると言ってよい。
また、毎年一〇〇〇粒の種子を作るにもかかわらず、実をつけるまで育つのは、平均してその中の一粒だけという植物は、地上を覆っている同種あるいは別種の植物と生存闘争をしている、とたしかに言えるだろう。(中略)一方、ヤドリギの種子は鳥によって運ばれるため、ヤドリギが子孫を残していくためには、鳥に依存しなければならない。より多くの鳥を引き付けて果実を食べさせて、より多くの種子を運んでもらうために、ヤドリギは他の植物と生存闘争をしている、と比喩的に言うこともできる。(『種の起源』62-63頁)
私は大学を卒業したあと、すぐに大学院に進学したわけではなく、しばらく会社に勤めていた。
その会社では、社内報というものが配られていた。その社内報のコラム欄に、こんな意見が載っていたことがある。
優しい会社員の勘違い
「欧米の進化論は闘争を基本とする残酷な思想であり、日本の進化論は共生を基本とする平和な思想である。そこで、私たちは……」
このコラムを書いた会社員は、残酷ではなく平和な思想のもとに仕事をしていこうという考えだったようだ。じつにもっともな意見であり、私もこの会社員の結論には全面的に賛成する。ただし、この会社員は、少しだけ勘違いをしていたように私は思う。
闘争を基本とした残酷な欧米の進化論というのは、おそらくダーウィンの進化論を念頭に置いての発言だろう。そして、「残酷な」という部分は、「生存闘争」を指していると思われる。
たしかに、誰だって「闘争」なんてしたくない。仲良く平和に生きるのが一番だ。だから、生存闘争を基礎にしたダーウィンの進化論を嫌いになる気持ちもわかる。
しかし、進化にはどうして生存闘争が必要なのだろうか。生存闘争をしない進化というものはないのだろうか。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を抜粋、編集したものです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。