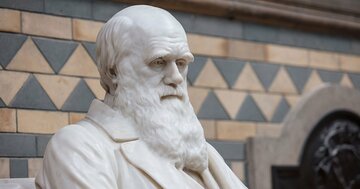ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
「子孫を残す」ということ
先日、ある新聞社から、生物における子孫の残し方について、電話でインタビューを受けた。20分ほどのかんたんなインタビューだったのだが、後日、実際に掲載された記事を読むと、残念ながら私にインタビューした内容は採用されていなかった。
もちろん、いくつもの情報から取捨選択して記事をまとめるのだから、私にインタビューした内容が載らなかったことはかまわない。ただ、そういう経緯があったので、「子孫を残すことの大変さ」を解説した、その記事を私は読んだのだが、そこにはなかなか興味深い研究が紹介されていた。
オオゴミムシダマシの闘い
それは、岡山大学の松浦輝尚氏と宮竹貴久教授による、ツヤケシオオゴミムシダマシという昆虫に関する研究だ。異性との交尾をめぐって闘う動物は、メスをめぐってオス同士が闘うゾウアザラシや、オスをめぐってメス同士が闘うレンカクという鳥など、たくさんの例がある。
ツヤケシオオゴミムシダマシもその一つで、メスをめぐってオス同士が闘う昆虫なのだが、その闘い方がすこし変わっている。お互いに相手の肢を噛み合うのである。
なぜ、こんな闘い方をするのか、その理由を明らかにしたのが、この研究だ。肢を噛まれて闘いに負けたオスは、その後メスと交尾したとしても、肢を地面につけて踏ん張ることができない。
そのため、残せる子の数が減ってしまうのである。実験的に交尾させて、最終的に孵化した卵の数で比べると、闘いに勝ったオスの平均値は28個で、負けたオスの平均値は1個だった。
興味深い実験結果
肢を噛むことによって、相手の生殖能力を弱めることが、はっきりと示された結果である。ところで、さらに興味深いことがある。それは、闘いをしなかったオスの場合、平均で61個もの卵が孵化したことだ。
たしかに、闘いになった場合は、勝ったほうがよいだろう。もし負けたら、孵化する卵の数が劇的に減ってしまうからだ。しかし、そもそも闘いをしなければ、闘いの勝者よりもさらに多くの卵を孵化させることができるのだ。
どうやら闘いに勝ったとしても、激闘によって体が疲弊しているので、元気なときよりは残せる子の数が減ってしまうらしい。先ほど述べた新聞の記事では、この結果から、動物が生殖に費やすコストは膨大である、という結論を導きだしていた。
進化は何のために起こるのか
それはそのとおりなのだが、この結果は別の面から捉えることもできる。それは、進化は個体のために起こるのであって、種のためには起こらないということだ。
しばしば「進化は種のために起きる」という発言を聞くことがあるけれど、それはまちがいなのだ。
もし種のために進化が起きるのなら、ツヤケシオオゴミムシダマシもオス同士で闘わないように進化したはずだ。もし闘えば、勝っても負けても、残せる子の数は減ってしまうからだ。
それなのに、闘うように進化したのは、自分のために、つまり個体のために進化が起きるからだろう。
進化と生存戦略
最後に一つ、たとえ話をしよう。
もしアフリカのサバナ(草原)を歩いているときに、ライオンに出合ったらどうすればよいだろうか。
走って逃げれば、確実にライオンに掴まってしまう。ライオンは人間よりも走るのが速いからだ。では、どうすればよいかというと、2人でサバナに出かければよいのである。
2人で楽しくサバナを歩いていると、ライオンに出くわした。驚いたあなたたち2人は、思わず回れ右をして、走って逃げ始めた。ライオンが後ろから追いかけてくる。
しかし、あなたは絶望することはない。
たしかに、あなたはライオンよりも速く走ることはできない。しかし、ライオンより速く走る必要なんてないのだ。あなたは、ただ、隣の人より速く走ればよいのである。
きっと、ツヤケシオオゴミムシダマシも、似たような戦略のもとに進化してきたのであろう。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』の著者による書き下ろしです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。