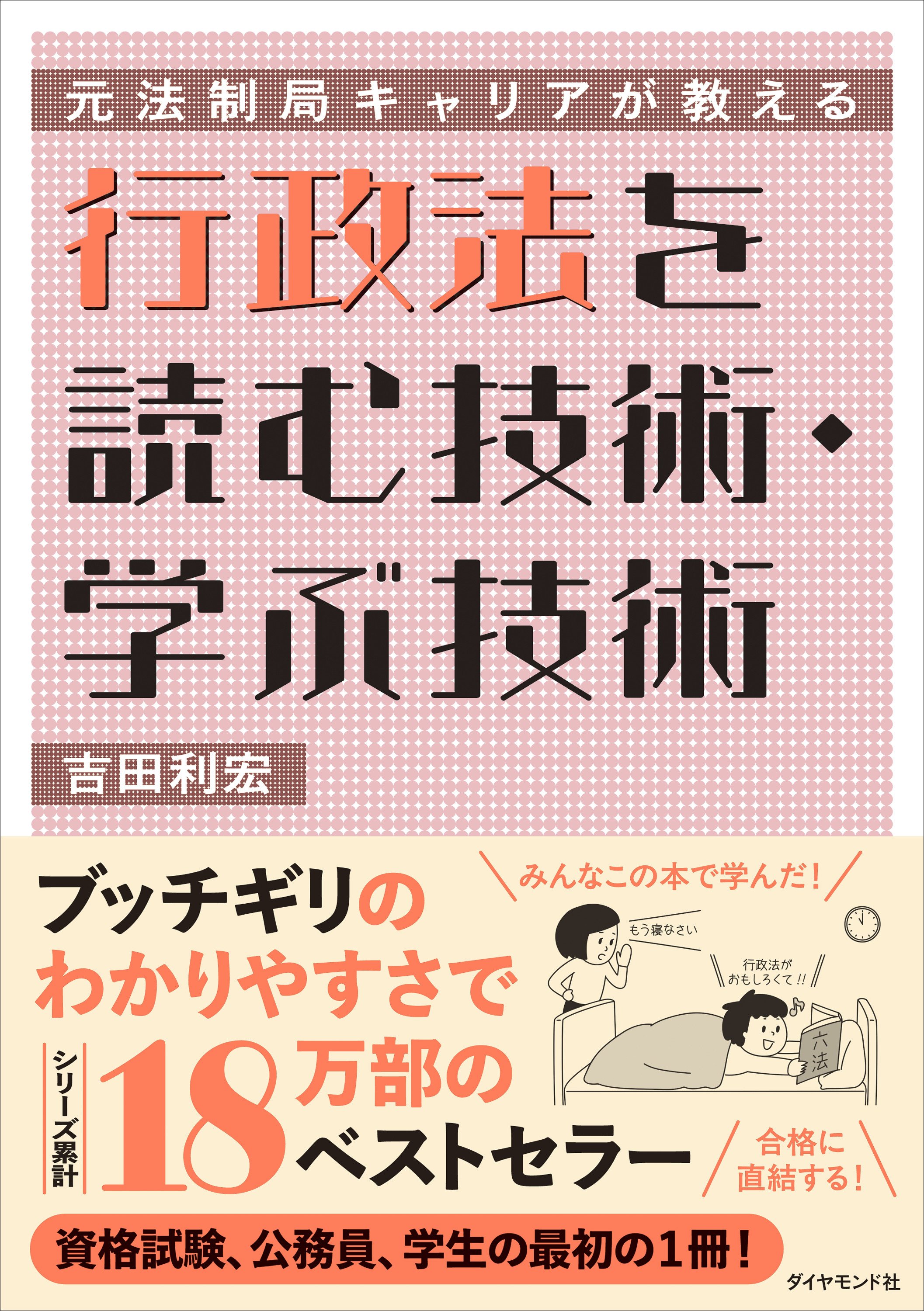累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。
 イラスト:草田みかん
イラスト:草田みかん
行政調査とは?
行政機関が行政目的のためにする調査を行政調査といいます。
あらかじめ「調査します」などと調査内容を予告して調査するのでは目的を達成できないことも多いので、以前は、行政調査は即時強制の一部としてとらえられていました。
行政調査には国勢調査のように行政の基礎情報を集める調査もあります。しかし、行政調査として問題になるのは、個別の行政活動との関係での調査です。
たとえば、「どうも法で定める手続が守られていない感じがする」といった場合、是正のため、何らかの働きかけをしなければならないわけですが、その前提となる調査が行政調査といえるでしょう。
任意調査とは?
相手の承諾を前提にする行政調査もあり、任意調査といいます。相手の承諾を前提とする以上、法律の根拠は必要ありません。
ただ、法律に根拠がある任意調査はあります。たとえば、警察官が不審者に行う「職務質問」もそのひとつです。警察官職務執行法2条1項が根拠となります。
任意調査の場合に問題となるのが、「どの程度まで認められるか」という問題です。警察官職務執行法との関係でいえば、ポケットに入っている物が怪しいと感じた場合「ポケットに入れている物は何?」と聞くことはできるわけですが、ポケットに手を突っ込んで調べることができるかということが問題になります。
覚せい剤の所持を疑った警察官が職務質問中に「被告人の承諾がないのに、その上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した」事例について、次の判例があります。
警職法2条1項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである
ただ、この判例でも承諾なくポケットに手を入れるのは「一般にプライバシイ侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において捜索に類するものであるから、上記のような本件の具体的な状況のもとにおいては、相当な行為とは認めがたいところであって、職務質問に附随する所持品検査の許容限度を逸脱したものと解するのが相当である」と述べています。
※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。