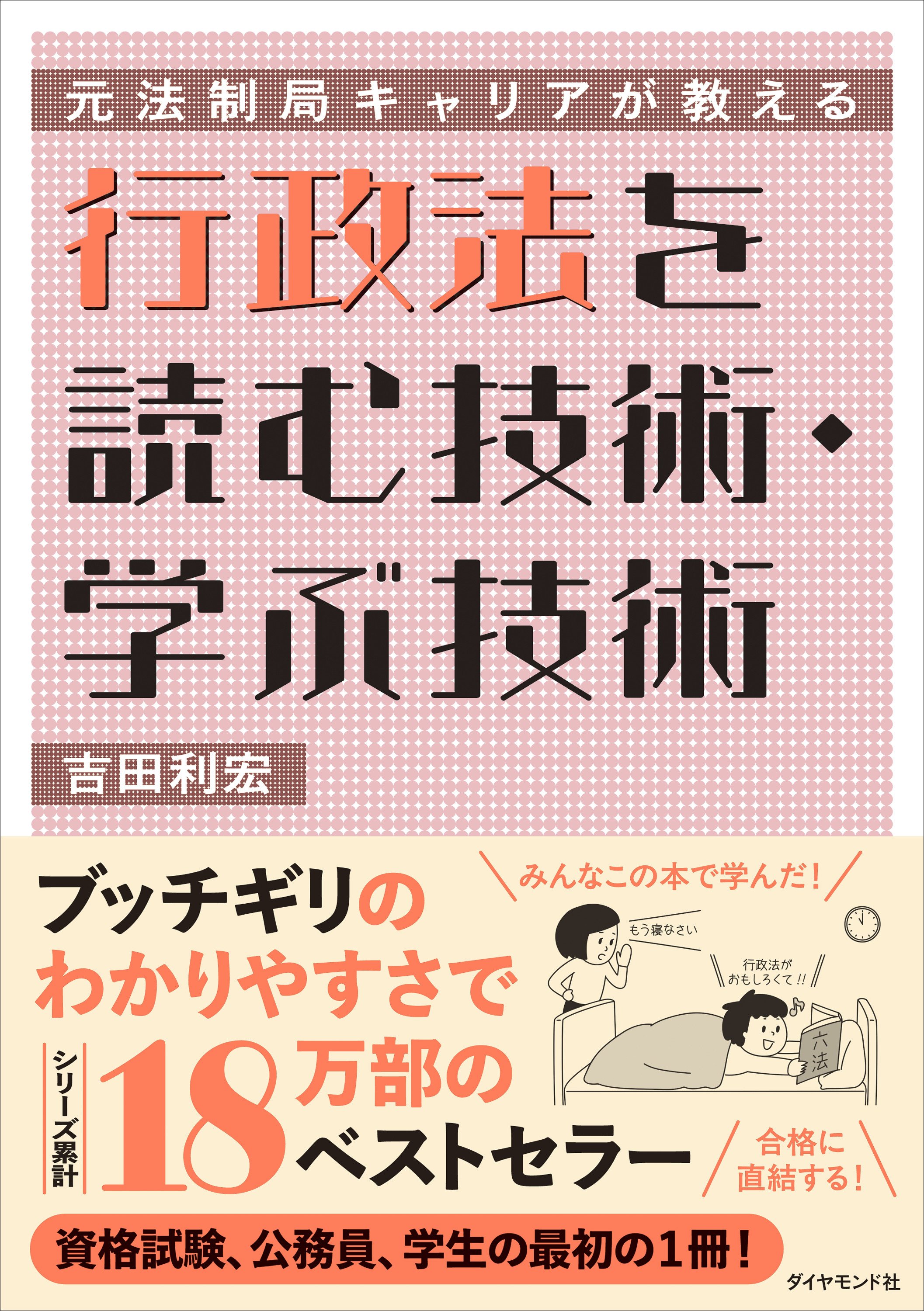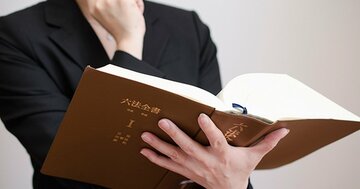累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。
 イラスト:草田みかん
イラスト:草田みかん
主体と客体という言葉
行政法の教科書では、いくつか紛らわしい言葉が出てきます。最初にハッキリさせておきましょう。
まず、行政主体という言葉です。
法律の世界は主体と客体という言葉が大好きです。
民法でも「権利の主体」という言葉が出てきます。「権利を手にしたり、義務を負うことができる者」という意味です。人(自然人)や法人がこれに当たります。
その一方で権利の対象となるものが「権利の客体」です。「物」はイメージしやすい権利の客体でしょう。
「ペットショップで、かわいい子猫を買ってきた」。この場合、子猫を買って所有者となる人が「権利の主体」で、子猫が「権利の客体」となります。
行政主体とは?
では、行政主体とは何のことなのでしょう?
これは「行政活動を行う権利を有し、義務を負う団体」のことです。国や地方公共団体が代表例ですが、ほかにも健康保険組合、独立行政法人、特殊法人などが含まれます。
一般的には国や地方公共団体を行政主体としていますが、時には行政法で国や地方公共団体以外の団体を行政主体として取り扱う必要があります。行政主体に独立行政法人などが含まれるのはそのためです。
たとえば、いわゆる情報公開法のほかに、独立行政法人等情報公開法(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律)があります。これは、独立行政法人等の役割に照らして、行政機関と同じような情報公開制度が必要だと考えて定めた法律といえます。
いろいろと言いましたが、最後にシンプルにまとめておきます。
「行政主体といえば、国や地方公共団体などのことだ」と理解しておけばいいでしょう。
ちなみに、行政客体とは、行政の相手方のことです。普通、自然人(人間のこと)や法人などの私人がそれに当たります。
「行政機関」と「行政庁」との関係
次は行政機関です。
行政機関とは行政主体(国や地方公共団体など)のために手足となって働く機関のことです。国や地方公共団体そのものではなく(それは行政主体です)、それらの一部の機関だといえます。
市で考えるなら、窓口で住民に対応している職員も行政機関(補助機関)なら、市長の諮問に答申する審議会も行政機関(諮問機関)ですし、市を代表してその名で許可を出す市長も行政機関(行政庁)ということになります。
どんな行政機関があるのか、行政法ではその役割ごとにグルーピングしています。その種類については後ほど詳しくお話ししますが、こうした行政機関のうち、行政主体のために意思を決定し、それを外部に表示する機関を行政庁といいます。
具体的には、市町村長・知事や大臣などが行政庁となります。運転免許を見ると○○県(都道府)公安委員会の名がありますが、これも行政庁です。
行政庁とは国や地方公共団体が利用している建物だと思っていた私にとって、このことは新鮮でした。
行政行為の特徴
行政行為は行政の行為のうちで、次のような要素を持った行為です。
・特定の者を狙い撃ち
・具体的に権利を制限したり、権利を与えたりなどする
・法的に裏付けされたもの
・一方的な行為
行政行為は「○○さんへの許可」のように特定の者を狙い撃ちにする行為ですから、法律や条例を定めるような行為とは異なります。
たしかに、法律や条例によって権利制限されるような場合はあるでしょうが、その場合には、すべての国民や住民が対象となります。
また、行政行為は一方的に行われます。交渉の余地はありません。
許可に当たって「こんな形で許可してくださいよ」とか「次回はちゃんとしますので今回だけは許可してください」などと国民(住民)の側から交渉することはできません。契約ではないのですから……。
こうしたことを踏まえて、行政行為は法に基づいて行われるものとされているのです。
行政裁量とは?
行政行為が法に基づくものだとしても、たとえば、「こんなときには許可する」とか「こんなときには許可を取り消す」というケースを洗いざらい条文に書き込むことがいいのかという問題があります。
論理的には、そうした方が国民(住民)のためにはいいはずです。しかし、実際には起こり得るすべてを書き込むことはできません。
許可に関する条文を見ると「次の各号のいずれかに該当する場合には許可を取り消すことができる」と書かれていることも多いものです。そして、各号に挙げられた文言は少し抽象的な部分を残しています。
つまり、許可取消権者からすれば、「各号に当たるかどうか」を判断しなければならないのです。
行政のこの選択の余地のことを裁量とか行政裁量といいます。
ある程度、条文が抽象的な書き方だからこそ、様々な要素を入れて許可を取り消すべきか目的に照らした判断ができますし、当初予想していなかった事態にも対応できるのです。
その反面、行政裁量が大きくなれば国民の権利保護は不十分なものになります。時には、裁量を認めるべきではない行政行為も存在します。
この行政裁量というものを組織としてどうコントロールし、踏み外しがあったときなどにどう国民を救済するかというのが行政法でのひとつのテーマとなっています。これもまた、おいおいお話しすることにしましょう。
 イラスト:草田みかん
イラスト:草田みかん
※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。