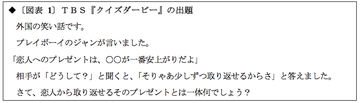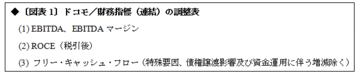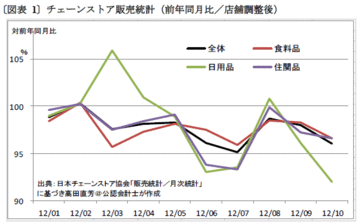先日、ある大学教授からユニークな質問を投げかけられた。「会計学が、経済学から見下される最大の問題は何か」というものである。答えは、「会計学は『規模の経済』が無限に働くことを想定していることにある」と。
「規模の経済」は経済学の専門用語なので(『マンキュー経済学第2版Ⅰミクロ編』378頁)、以下では「量産効果」と読み替える。販売数量が増えれば増えるほど、製品1個あたりの平均コストが低下することをいう。
会計学は本当に、量産効果が無限に働くことを想定しているのだろうか。もし、それが事実ならば、経済学から見下されても仕方がない。
今回のコラムは、家庭用・産業用の消耗品を扱うライオン、アース製薬、小林製薬のデータを用いて、「会計学、見下され問題」を検証してみる。
読者の中には、家庭用品は「多品種・大量生産」であって、どこも同じコスト構造を抱えており、三社ものデータ解析は不要ではないか、と思うことであろう。それは、実証を怠った者が、観念的に空想する評論である。
量産効果の問題を解決してその先に視線を移していくと、ライオン〔図表 9〕からは、アース製薬〔図表 7〕や小林製薬〔図表 10〕の「芝生が青く見える」ことがある。アース製薬や小林製薬からも、他社の芝生が青く見えることもあるのだ。
ひと口に家庭用品といっても、コスト構造が明らかに異なることが原因だ。量産効果の問題は、その相違点の一端を炙り出してくれる。
量産効果には「底」がある
早速、量産効果(規模の経済)の概略を説明する。
次の〔図表 1〕は、経済学の教科書であれば必ず見かける「量産効果の説明図」である。その右にある〔図表 2〕は、会計学の教科書であればどこでも見かける「量産効果の説明図」である。