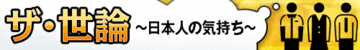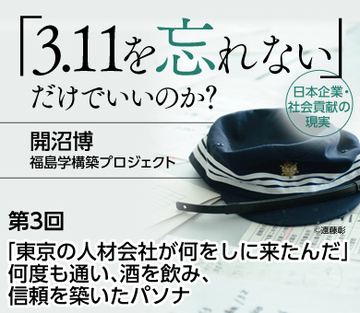AAAS年次大会初日に開催される開会セレモニーでは、例年、その地域の自治体首長もスピーチを行う。大学・科学界・産業界と連携しつつ、地域の貧困問題を主に教育によって解決しようとする取り組みについて語るシカゴ市長 Rahm Emanuel 氏。ステージ下にいる男性は手話通訳
AAAS年次大会初日に開催される開会セレモニーでは、例年、その地域の自治体首長もスピーチを行う。大学・科学界・産業界と連携しつつ、地域の貧困問題を主に教育によって解決しようとする取り組みについて語るシカゴ市長 Rahm Emanuel 氏。ステージ下にいる男性は手話通訳Photo by Yoshiko Miwa
毎年2月、米国またはカナダのどこかの都市で、科学の祭典が開催されている。科学雑誌「Science」の発行元でもあるAAAS(米国科学振興協会)の年次大会だ。今年も2月に第180回年次大会がシカゴで開催された。
約2世紀にわたって毎年開催されてきたAAASの年次大会には、教育・研究・科学政策・科学コミュニケーションなど多様な立場で科学に関わる人々、さらに科学を愛好する市民たちが、世界中から参加する。参加者は、多い年には約1万人に達する。今年は寒波と天候不順のため、当初予想よりも参加者は少なかったようだが、それでも7600人ほどだったそうだ(「Science」誌2014年2月21日号による)。
震災から3年を迎えた今、科学に関わる世界の人々は、東日本大震災や福島第一原発を、どのように記憶し、話題にしているのだろうか?
日本人も忘れつつある
東日本大震災
2014年3月11日は、東日本大震災から3年にあたった。読者の皆様は、ふだん、東日本大震災をどれだけ意識しているだろうか? 「あの大震災のときにどこにいたか」「どのような被害を受けたか」「現在どこに住んでいるか」で、意識のしかたは全く異なるであろう。
同じ東北でも、「激甚被災地であるかどうか」「福島第一原発からの距離はどの程度か」などの要因が、被害の状況や意識のされかたを大きく変えてしまっている。東北以外の地域では、よほど意識していなければ、東日本大震災を忘れずにいることは困難であろう。
恥ずかしながら筆者自身も、ふだんは「もう、あまり意識していない」というのが実情だ。東日本大震災の時、東京23区西端にある筆者の住まい、築60年に達する木造家屋は、倒壊の可能性を思い浮かべるほど揺れた。幸い、家屋は大きな被害を受けなかったものの、脆い大谷石の門柱が一本折れた。ご近所への被害に結びつかなかったのは幸運であった。上半分が折れて失われたままの門柱は、今もそのまま日常の風景に馴染んでしまっている。
その後、1週間程度を想定した飲料水の備蓄・2週間程度を想定した食糧等の備蓄は行った。また筆者の車椅子には、1晩程度の帰宅不能状態には備えられるように、食品・水・サバイバルグッズを常時積んでおくようにしている。しかし、そのあたりが個人でできることの限界だろう。2011年3月11日から「非常時の水の確保のため、庭に井戸を掘っておきたい」とは思い続けているものの、実行に移せないまま3年が経過してしまっている。
さて、世界の科学界は、どのように東日本大震災を記憶しているだろうか? あるいは、忘れてしまっているだろうか?