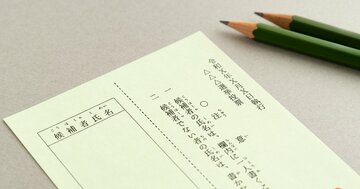みわよしこ
生活保護の制度がある日本では、誰でも「健康で文化的といえる生活」を営めるはずだ。しかし、「日本には生活保護があるから安心だね」という喜びの声は聞こえない。政府の財政上の都合や「生活保護は恥」という偏見が、権利であることを妨げ続けてきた。この状況を打開するためにできることを考えてみたい。

2021年12月17日朝、大阪・北新地の心療内科クリニックで火災が発生した。合計27人が死亡した衝撃的な事件の直接の原因は、そのクリニックの患者でもあった容疑者・T氏(当時61歳)による放火だ。T氏自身が意識不明のまま約2週間後に死亡したため、放火に至った動機や経緯、そして事件直前のT氏の暮らしぶりのほとんどは、不明のままになっている。何があれば、事件は起こらなかったのだろうか。T氏の職歴・刑務所入所歴・生活保護・生活環境・心療内科クリニックの五つの「謎」に注目して、この問いを解きほぐしてみよう。

2021年現在、生活保護を受けながら大学等の昼間部に在学することは、ごく一部の例外を除いて禁止されている。現状をレポートしよう。

21年10月25日、東京都中野区役所は、現在建設中の新庁舎に福祉事務所を移転させるという方針を決定した。しかし、その道のりは、平坦ではなかった。「生活保護が必要な区民は、美麗な新庁舎の外のどこかへ」という形態での検討も進んでいたからだ。

7月初旬、住居を喪失して東京都が契約したビジネスホテルに滞在していた人々は、間近に迫る五輪の影響で寝泊まりの場を失いかけた。この事件で日本の「住」の脆弱さが露呈したのだ。そもそも、「ビジネスホテルの空室」という不確かな資源を前提とした政策そのものが、危うさを内包しているのではないだろうか。

そもそも小室さんに、母・K代さんを扶養する必要はない。日本には、人生に起こりうるあらゆるリスクをカバーする生活保護という、優れたシステムが存在する。年老いた親の生活を生活保護に委ね、子世代が親と円満な関係を維持して交流を続けることは、非難されるべき選択肢ではないはずだ。

5月18日、衆議院法務委員会で審議されていた入管法改正案の採決が見送られ、現在開催中の第204回国会(6月18日まで)では成立しない見通しとなった。「難民認定される人々は多い年でも申請者の1%程度」という日本の難民認定の異様な厳しさ、さらに収容施設での非人道的な処遇は、長年にわたって国際社会の非難を受けている。中東出身で仮放免中のBさん(40歳代)に、状況と暮らしぶりを聞かせていただいた。

先天性の筋委縮症を持つシンガー・ソングライターの朝霧裕さんは、「車椅子の歌姫」として知られている。彼女の生活を支えているのは、生活保護だ。朝霧さんは自分の収入によって生活保護から脱却することを夢見ているが、その前には「貧困の罠」が立ちはだかる。

3月末、厚労省は生活保護の扶養照会に関する事務連絡と課長通知を発行した。「本人がイヤなら、扶養照会を止めることができる」という内容を含む、かなり画期的な内容だ。生活保護申請者と親族の仲を壊しかねない扶養照会の「不要ぶり」に彼らが気付いたのはなぜか。

コラムニストの伊是名夏子さんが「JRで車いすは乗車拒否されました」と題する記事を公開し、賛否と共に大きな反響を呼んでいる。伊是名さんの一件をめぐる「ネット炎上」は、時折発生する「生活保護叩き」を重ね合わせてしまう。なぜこんなことが起きたのか。

2019年、京都府向日市と滋賀県米原市において、福祉事務所で生活保護に関わる現職ケースワーカーが刑事事件で逮捕された。理由は、死体遺棄と殺人未遂だ。なぜ、こんなことが起きたのか。彼らを犯行に走らせた現場の深刻な課題、そして再生への取り組みとは。

3月下旬、札幌地裁において、生活保護基準引き下げの取り消しなどを求める訴訟の判決が言い渡された。結果は「棄却」だった。裁判長は同性婚訴訟で「同性婚を認めないのは違憲」という画期的な判決を下した人物だ。同じ裁判長が下した判決とは思えないのは、なぜか。

コロナ禍で生活保護への期待が高まる中、福祉事務所から申請者の民法上の扶養義務者へ「仕送りできませんか?」などと問い合わせる、扶養照会の存在理由が問われている。この扶養照会、場合によっては申請者と親族の絆を粉々に砕いてしまいかねないのだ。

東日本大震災から10年が経つ中、忘れ去られようとしている人々がいる。福島第一原発事故のあと、国や自治体の方針を待たずに避難した「自主避難者」たちだ。災害救助法の適用期間が終わり、故郷にも戻れない中で、生活苦に陥る人もいる。誰が手を差し伸べるのか。

生活保護の実施は本来、公務員が行わなければいけないが、ケースワーク業務を外部委託化しようとする自治体の動きが広まっている。しかも非職員が、生活保護受給者に対して不当ともいえる保護費の返還を求めるケースもある。中野区の事例を基に、問題点をあぶり出す。

2月22日、大阪地裁において、2013年に行われた生活保護基準引き下げの撤回を求める訴訟の判決が言い渡された。それは、原告であり生活保護のもとで暮らす人々の主張を、ほぼ全面的に認めたものだった。その意義は大きい。生活保護の意義を、もう一度振り返ろう。

2020年2月、大阪府八尾市で、生活保護を利用していた母親と長男が遺体で発見された。この事件では、母子の安否がきちんと確認されないまま生活保護が打ち切られたことが問題となった。先日行われた調査団による申し入れでの市の弁明は、信じられないものだった。

コロナ禍の中で生活保護への関心が高まっているが、生活に困窮する人たちに生活保護の申請をためらわせるのが、福祉事務所による家族への「扶養照会」という措置だ。それによって家族との絆が壊れてしまい、申請者の生活が余計に窮地に追い込まれることもある。

日に日に生活保護への関心が高まる中、筆者のもとに文化放送からラジオ出演の打診があり、先日10分ほどの出演の機会を得た。生活保護の概要から申請法、不正受給の現状までを駆け足で説明したが、語り尽くせなかったことがある。この場で改めて論じてみたい。

地方選挙シーズンが到来した。地方議員選挙の「1票の価値」は、極めて重い。そこで、1月31日に選挙が予定されている地域について、生活保護と生活困窮者支援に注目し、自治体の施策と議会会議録を眺めてみた。コロナ禍だからこそ注目し、徹底比較してみよう。