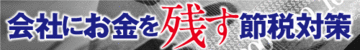高橋敏則
相続税が払えず死を選んだ夫婦も……来たるべき時に備え、対策は万全ですか?
平成25年度の税制改正で大きく変わった相続・贈与税。特に影響が大きいのが相続税の基礎控除の縮小。現状では100人亡くなると4人に相続税がかかるといわれるが、これが6~7人に増加すると試算されている。大増税時代をいかに乗り切るか、相続税対策の基本を解説する。
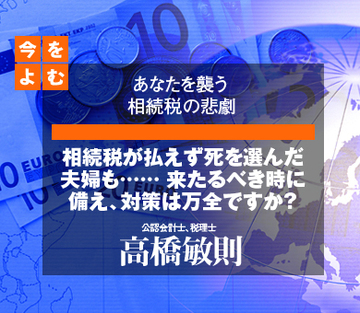
最終回
税務調査も終盤を迎えてくると、調査官のチェックはかなり具体的になってくる。その際も、簡単に収拾してはならない。時に調査官との駆け引きの局面になったとしてもだ。
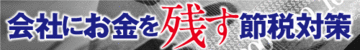
最終回
企業が成長している時こそ、資金が不足しやすい。資金不足を避けるためには財務体質の強化が優先だ。そのためには直接金融主体の資金調達を心がけるべきだ。
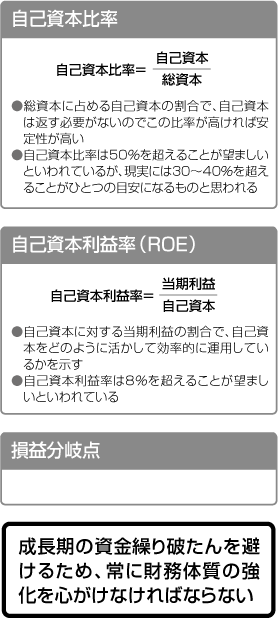
第14回
限られた時間で行う税務調査では、調査官が見るポイントが絞られる。いかに課税対象額を上げることができるかという部分だ。事前の段階で注意深く準備することが大切だ。
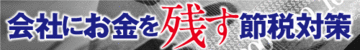
第13回
資金繰りが厳しい時こそ、「手形」の扱いには特に慎重になるべきだ。「融通手形」は資金の調達手段と安易に考えやすいが、リスクも高く手を出すことは厳禁だ!
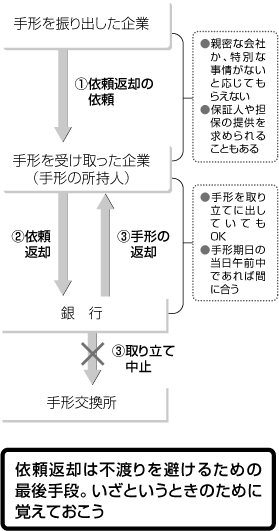
第13回
実際に税務調査に入ったら、調査官とは対等な立場だということを常に自覚し、必要以上に萎縮する必要はない。逆に、調査官に対して横柄な態度を取るのもよくない。
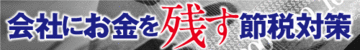
第12回
会社が収益を上げ、成長するために設備投資は不可欠です。しかし、多額の資金を必要とする設備投資は資金繰りを悪化させる原因になることもあり、計画性が必要だ。
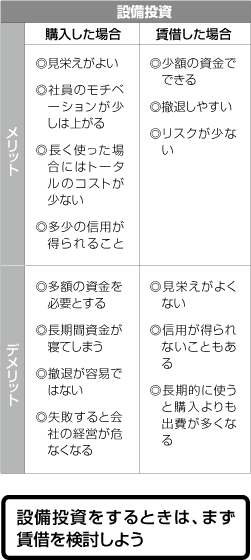
第12回
抜き打ち調査はいざ知らず、税務調査が決まったら、税務署に調査前に必要なものの確認をし、念入りな準備で望もう。事前にしっかり準備することで余裕ができるはずだ。
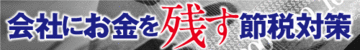
第11回
設備投資の施策のいくつかは、そのまま資金繰りの有効な方法に変わる。遊休資産・低収益資産の売却損を計上すれば節税に、不採算部門の撤退は資金繰りの改善に直結する。
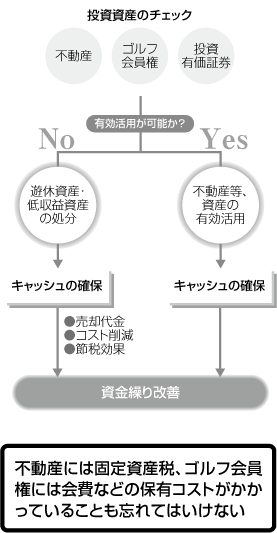
第11回
会社にお金を残すための節税術を考える上で、避けて通れないのが「税務調査」だ。税務調査の上で、注意しておくこととは何か? 税務署と渡り合う基本を伝授する。
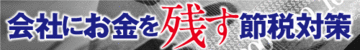
第10回
損益取引から資金繰りを改善するためにはキャッシュフロー計算書の活用が不可欠だ。その上で利益を出すためのコストの見直し、アウトソーシングの活用が効果的だ。
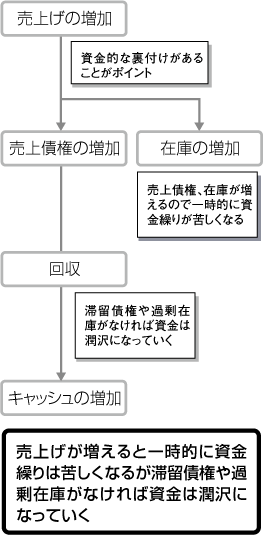
第10回
節税対策に有効な手を打てるリミットは決算日の3ヵ月前。この日程より前であれば、不動産の購入・売却などより高い節税効果をあげる対策の選択肢が増える。
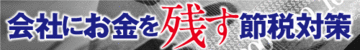
第9回
銀行の貸し渋りの兆候は手形割引に始まるいくつかのパターンがある。粘り強く交渉しつつ、他の金融機関を探すなど準備をし、決して銀行の一方的な要求には安易に対応しない。
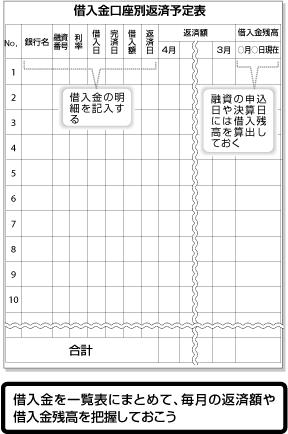
第9回
税務署は可能な限り税金をたくさん納めてもらいたいと思っています。素人が考えつく目くらましやごまかしは、「待ってました」といわんばかりに真っ先に見抜かれるのがオチ。
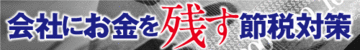
第8回
複数の短期借入金がある場合は長期借入金に一本化することが資金繰り改善の上で不可欠だ。その上で、普段から銀行とは上手く付き合うことが重要だ。
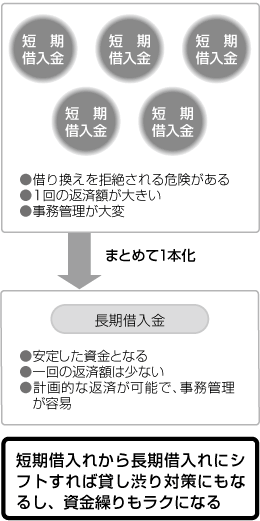
第8回
節税効果の上げるためには、いくつか交際費を損金参入することが効果的だ。その方法には「子会社」の設立、会議費とみなされない飲食費の処理など有効だ。
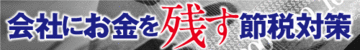
第7回
資金調達を従来先を銀行だけで考えるのではなく、民間・政府系など多くの選択肢から選ぶべきだ。借入の際には自社に有利な条件のものを判断する事が重要だ。
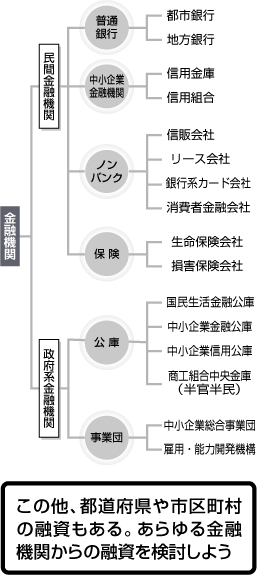
第7回
法人税節税では、減価償却の活用が不可欠だ。資産の状況を正確につかみ、その上で増加・特別償却などの制度を熟知する事で、さらに節税が期待できる。
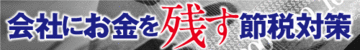
第6回
資金繰りの基本は回収日と支払日を調整して、資金の収入と支出のバランスを図ること。そして、デメリットの多い手形払いに頼らない資金計画が鉄則だ。
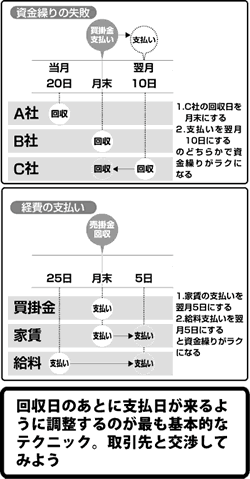
第6回
会社の節税は役員賞与と交際費がキモだ。役員賞与は損金不算入という税制上の扱いを受けるなかで、税制上のルールを知ることは必須だ。