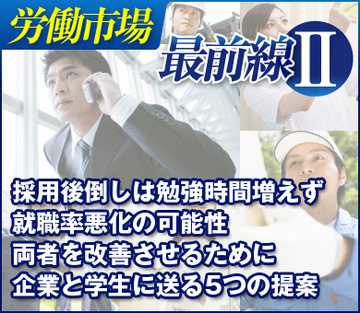大久保幸夫
「みんなの前で褒める」は当たり前!キャリアのプロが教える褒め方のコツ5選
従来の人材育成では「叱ってこそ人は育つ」という考えが一般的であったが、現代では、メンバーのやる気を出すためにも「ほめる」マネジメントが欠かせない。ほめることは部下にこびることでも甘やかすことでもない。ほめることを通じて部下の成長を促し、成果を上げるために必須のテクニックなのだ。リクルートワークス研究所所長・大久保幸夫氏がそのコツを解説する。※本稿は、大久保幸夫『マネジメントのリスキリング――ジョブ・アサインメント技法を習得し、他者を通じて業績を上げる』(経団連出版)の一部を抜粋・編集したものです。

「優秀な部下を異動で手放したくない」→上司の「あるある悩み」をキャリアのプロがバッサリ!
マネジャーとしての大きな悩みの一つは、メンバーとの関わり方だろう。マネジャーの中にはメンバーの欠点ばかりが目に入ってしまい、人間関係にヒビを入れてしまう人もいる。しかし、相手の弱みよりも強みを見つけることができればメンバーの成長をグッと促すことができるのだ。『強み』を生かして成果を上げるマネジメントの5つのコツをご紹介する。※本稿は、大久保幸夫『マネジメントのリスキリング――ジョブ・アサインメント技法を習得し、他者を通じて業績を上げる』(経団連出版)の一部を抜粋・編集したものです。

なぜ誰も管理職になりたがらないのか?「そりゃそうだ」と思える納得の理由
「人手不足なのに管理職のなり手がいない……」ビジネスの最前線では今、管理職人材の不足が深刻な問題になっている。管理職に抜擢されればキャリアアップと収入アップを望めるにも関わらず、マネジメント人材が不足しているのはなぜなのか?リクルートワークス研究所所長・大久保幸夫氏がその背景に迫る。※本稿は、大久保幸夫『マネジメントのリスキリング――ジョブ・アサインメント技法を習得し、他者を通じて業績を上げる』(経団連出版)の一部を抜粋・編集したものです。

第13回
4月19日、政府は採用活動開始時期の繰り下げを要請した。学業を阻害しないように採用活動を後倒しすることは、長らく大学側の希望でもあったわけだが、果たしてこのようなルール変更は、期待通りの成果を上げることができるのだろうか?