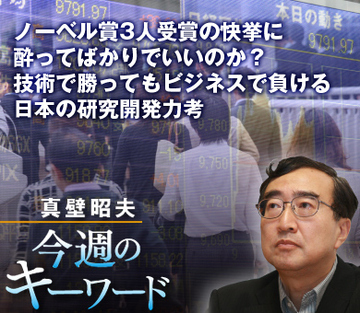喜ばしい大隅氏のノーベル賞受賞
誰も予測できない基礎研究の成果

ノーベル医学・生理学賞を大隅良典氏が受賞した。日本人としてはとても喜ばしいが、大隅氏は記者会見で「科学が『役に立つ』という言葉が社会を駄目にしている。本当に役立つのは100年後かもしれない。将来を見据え、科学を一つの文化として認めてくれる社会にならないかと強く願っている」と話した。
また、大隅氏はノーベル賞受賞以前にも科研費や研究環境について訴えている。「現在の科研費、とりわけ基盤研究の絶対額が不足しており、採択率がまだ圧倒的に低い。今の2、3倍になれば大学などの雰囲気も変わる」と言っている(https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/29_essay/no78.html)。
実は筆者も、「基礎研究は社会に役立つべきもの」という言葉は、大隅氏のようにかなり抵抗がある。
筆者は理系であり、もちろんノーベル賞級の研究とは無縁であったが、数学という基礎科学の典型を専攻していた。特に、代数曲線上の数論にハマり込んでいた(この用語はおまじないと見てほしい!)。
後日、勉強していたことが、フェルマー最終定理(300年以上解けなかった数学上の大難問)に関係したり、さらに、ある人からそれを暗号理論に使って金融取引などで社会に役立っているということを聞いて、びっくりした。それを選んだのは、単純に面白かったからであり、その社会応用なんて考えた人もいなかった。
この感覚は、筆者が説明するよりも、プリンストン大のノーベル賞学者ナッシュを描いた映画「ビューティフル・マインド」を見てもらったほうがいいかもしれない。ナッシュが大学院生の時に書いた論文はゲーム理論となって、ナッシュが予想できなかったほど社会に役立っている。
こうした基礎研究が、その後社会に役に立つかどうかは、誰も予測することはできない。はっきりいえば、基礎研究で将来役に立つものはかなり少ない。しかし、大量に基礎研究しなければ、そもそも当たらないし、社会への貢献もない。この意味で、基礎研究は未来への投資の典型である。下手な鉄砲でもいいから、数多くやれば、確実に一定の成果はあるものだ。