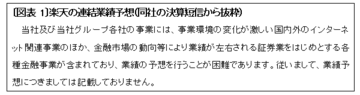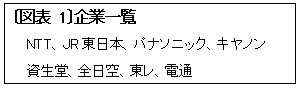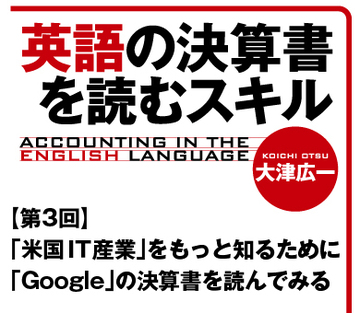本連載の第58回コラム(楽天vs.ヤフー編)のとき、米グーグルが2004年4月に株式公開を行なったときの資金調達額が「2,718,281,828ドル」であったことを紹介した。その27億ドルが、「自然対数の底e=2.718281828……」を10億倍したユーモアであることも併せて紹介した。
2012年5月に株式公開した米フェイスブックの資金調達額は、8年前の米グーグルをはるかに凌ぐ。円周率πを10億倍した程度では収まらないようだ。
米フェイスブックの資金調達額が160億ドルなら、それに1ドル=80円をかければ1兆2800億円になる。よくもそれだけのキャッシュが吸い寄せられるものだと感心してしまう。
自らの預金通帳を眺めると、感心が溜息に転じる。総務省統計局「平成21年全国消費実態調査」によれば、2人以上の世帯の家計の平均貯蓄残高は、1521万円だという。
「おいおい、そんなにはないぞ!」という声には、大丈夫。あなたの隣にいる人は、3000万円をこっそり貯め込んでいるのだから。3000万円を2人で割れば、1500万円の貯蓄があることになる。「平均」とは、そういうカラクリを含んでいる。
溜息をグッと飲み込んで、ここでは何故、米グーグルや米フェイスブックといった少数の企業(または経営者)に、これほど巨額のキャッシュが集まるのだろうか、という問題を考えてみたい。もちろんそれは、いまの時代で実現できる最強のビジネスモデルを確立しているからに他ならない。
その方法の一つが、第79回コラム(パナソニック&キヤノン編)で紹介した特許戦略であろう。今回はそれ以外の点について、検証してみたい。
アダム・スミスはかく語りき
一攫千金で億単位のキャッシュを狙う手っ取り早い方法としては、宝くじがある。アメリカでは12年3月に、530億円という史上最高額の当たりくじが出た。翻って日本の場合、当選金として払い戻される割合は、宝くじの収益金の半分に満たない。「宝くじ公式サイト」によれば、46.2%だという。
仮に、1人で宝くじのすべてを買い占めたとする。その資金が100億円であった場合、当選金として払い戻されるのは46億2000万円だ。個人ではなく、企業が宝くじを購入した場合、まず間違いなく減損会計が適用されることになるだろう。
宝くじは、ハイリスク・ローリターンどころか、リターンが確実にマイナスになる「損なビジネスモデル」である。しかし、人は、そんなに割り切って行動するわけでもない。万が一当選したときの「夢」を描くことができるのであれば、高い買い物だとはいえないであろう。