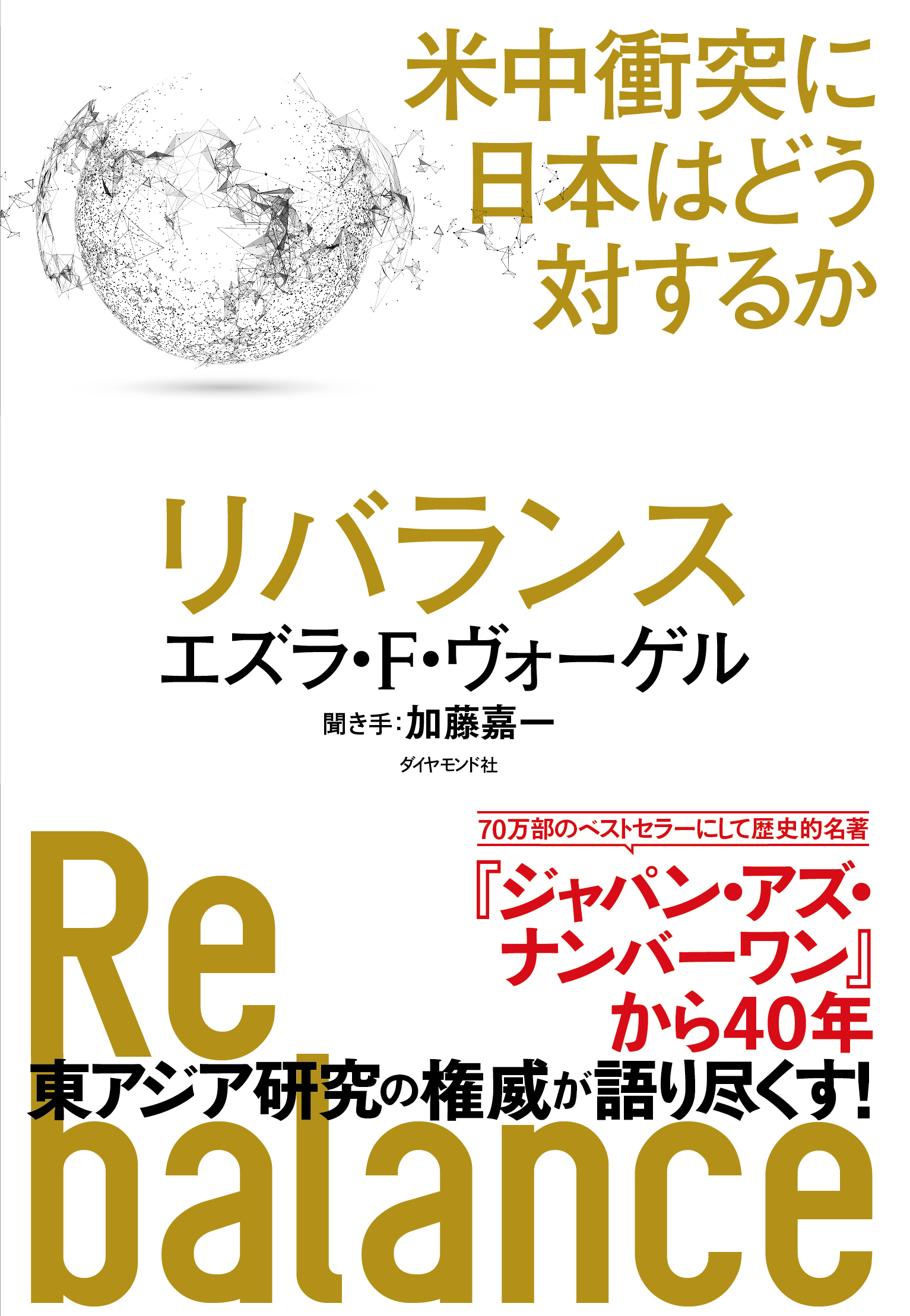日米中の「愛国」主義はどのように違うのか? 世界のリバランスに日本がどう立ち振る舞うべきか、東アジア研究の権威であるハーバード大学のエズラ・F・ヴォーゲル名誉教授がいま日本人に伝えたいことを語り尽くしていただいた新刊『リバランス 米中衝突に日本はどう対するか』。発売を記念して中身を一部ご紹介いたします。聞き手は、香港大学兼任准教授の加藤嘉一さんです。
Question
『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を執筆された目的を伺うと、先生なりの祖国への愛情が感じられます。日本を重視し、そこから何らかの教訓を得るという意識と作業が、米国が持続的に発展していくうえで重要になる、という先生なりの愛国主義がにじみ出ています。先生はこの「愛国」というものにどのような姿勢や見方を持っておられますか。特に、これまで日本、中国と付き合ってこられた米国人学者として、三国の愛国主義をどう比較しますか。
ヴォーゲル教授 私が尊敬する旧友に、朝日新聞の論説主幹を務めた松山幸雄がいる。私と彼は同い年だ。日本で出版された拙書『ジャパン・アズ・ナンバーワン──それからどうなった』(たちばな出版、2000年)に序文を寄せてくれた松山は、そのなかで私のことを「コスモポリタン愛国者」と描写した。少し照れくさかったが、まあそう言われればそうなのかなあと思ったものだ。
「愛国」とは何なのだろうか。
私の経験と観察から、日米中の愛国主義を簡単に比較してみたいと思う。
まず日本人だが、その愛国主義は意外と強いと思っている。しかも、日本人の愛国心は自然と湧き出る類のものであり、それが時に島国根性という精神につながり日本人の我慢強さや忍耐力に結実しているように思う。
中国人の愛国主義は、なんと言っても「自分たちの文化こそが世界一だ」という認識で成り立っている。それは歴史に対するプライドとも言える。みずからの悠久の文化に自信は持っているが、それだけで国民を団結させることができるか、為政者はいつも心配している。だから宣伝工作を通じて国民の意識を統一させようとする。政治的観点から愛国主義を盛り上げようというのが中国の特徴である。
米国の場合は、やはり建国以来、世界各国の人々を魅了してきた「自由の国」という要素が大きいだろう。ただ、10年ぐらい前から自信がなくなってきたようである。国や社会も分裂してきた。自信を持って未来へ向かっていくというよりは現状に対して文句ばかりを言うような国民性が根付いてしまっているような気がしてならない。自信満々ではなく自分勝手な国民が増えた。利己主義と愛国主義は当然異なる。みなが利己的になってしまえば愛国主義は育たない。
愛国と言ったときに私が思い出すのは、マデレーン・オルブライト(1937~)、マイケル・マンスフィールド(1903~2001)、ウォルター・モンデール(1928~)といった偉大な政治家である。彼ら、彼女らは愛国者だった。国家の未来のために物事を考え、実践していた。米国一国ではなく全世界のことを幅広く考え、自分にできることに真剣に向き合いながら行動していた。エリートたちは自分の権益だけではなく、国民が豊かになるように、社会全体が繁栄するように行動していた。
戦後を生きた米国人たちが愛国主義を抱擁し、実践するに至った背景・要因として、ここでは三つだけ取り上げたい。
初めに、エリートが愛国主義を持ち、実践していた一つの歴史的背景が、第二次世界大戦にあると考えている。当時、ナチスはひどかった。私の両親がヨーロッパから米国に移住してきたユダヤ人だから、その思いはことさら強い。あの戦争の残酷さを乗り越え、世界平和の実現のために良い秩序を作る。そのために米国が貢献する。それが、当時を生きた米国人の愛国主義だった。前述した人物は、その典型であった。実際に、戦後構築された秩序とシステムは、その後の世界の平和と繁栄を保障し、促進するための原動力となったことは論をまたないだろう。
次に私が想起する要因は、宗教である。戦後の一定期間、米国では宗教が強かった。一例がメソジスト派だろう。多くの人が教会などに赴いて宗教に参加した。それが社会やコミュニティーに道徳をもたらした。少し極端に聞こえるかもしれないが、神様のために、社会や国家、そして世界全体にとって良いことをしよう、という潜在意識と行動規範が、米国人たちに自律を促していたのである。ただその後、宗教という要素が、米国人の生活様式、行動規範、価値体系に及ぼす影響が弱体化していった。結果的に、道徳心や自律心を持って社会、国家、世界に向き合う米国人が少なくなっていった。それはすなわち、愛国主義の劣化を意味していた。
最後に、理想主義という要素が挙げられるだろう。「世界平和」という四文字は理想的に聞こえるかもしれないが、戦後の世界は本当にそういう理想を必要としていたし、それを実現するために米国人、特にエリート層を駆り立て、国民もそれを支持し、続いていった。大いなる理想を掲げ行動する人々には、世界全体のことを第一に考え、ゆえにみずからを律し、自分にできることを真剣に考え、実践する素養が備わっていった。私が生まれ育った中西部オハイオの小さな街の人々や母校の関係者でさえ大いなる理想を持って、米国の発展と世界の平和に何らかの形で貢献しようとしていたのである。
以上、戦後世界平和への希求、宗教と道徳心・自律心、理想主義の探求という相互に絡み合う三つが、当時の米国人を愛国的にした背景・要因である。言い換えれば、これらが失われた、あるいは弱くなったがゆえに、昨今を生きる少なくない米国人、特にエリート層が全世界のことを考えなくなった、愛国的でなくなった理由だと思われる。
今日の政治家も狭隘な利益のために物事を考え、実践しているように見える。私が身をおいてきたアカデミックの世界でも、同様の現象が起きていると感じている。今日、健全な愛国主義精神を持っている若者は、私たちの世代が若かった時代に及ばないようだ。自分の研究成果、たとえば学位の取得や論文の発表、終身教授の地位にばかり固執し、それを得るためには一生懸命に働くが、米国全体の繁栄、世界全体の平和を念頭に学者として何ができるか、何をすべきか、という観点から日々の仕事に向き合っている学者は少なくとも私が見る限り、私が若かった頃よりも少なくなっている。
今日の米国は、戦後の繁栄と平和をみずからの行動で促した頃の米国に及ばない。その一つの要因は、米国の愛国主義が後退した現状と構造に見出せる。一人の祖国を愛する学者として、この現状を認めないわけにはいかない。