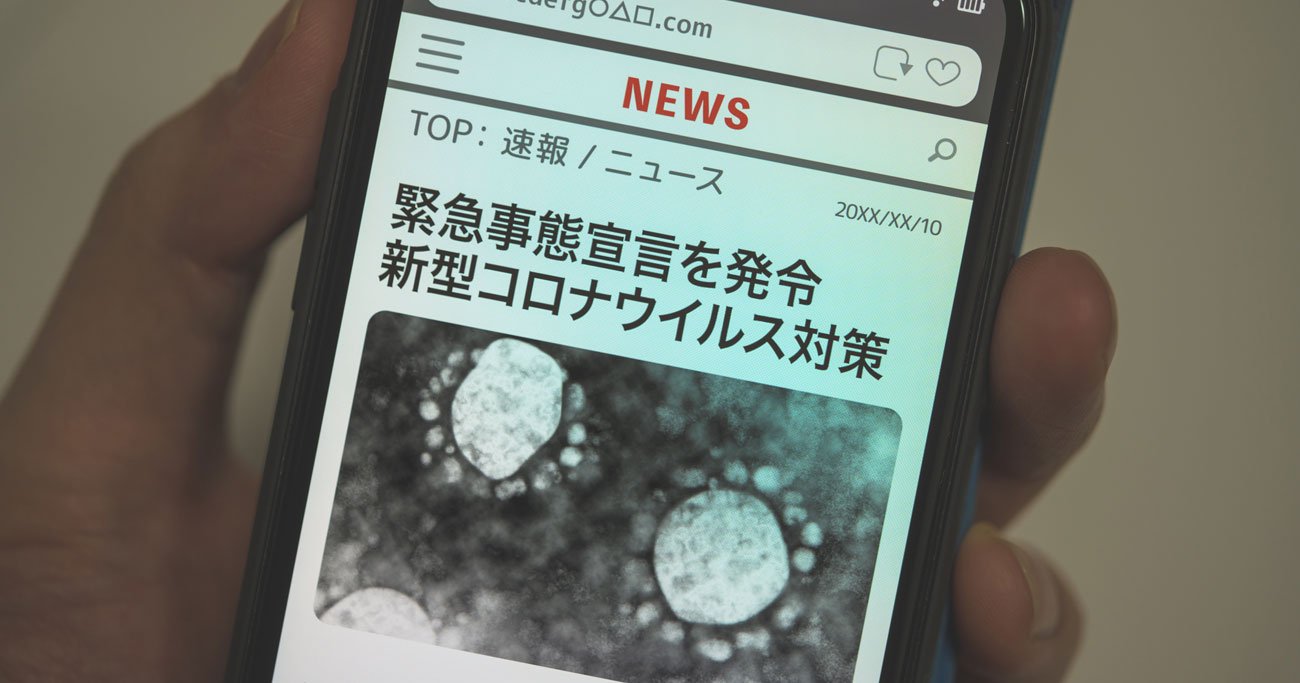 「緊急事態宣言」はされたが…(写真はイメージです) Photo:PIXTA
「緊急事態宣言」はされたが…(写真はイメージです) Photo:PIXTA
安倍晋三首相は4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、緊急事態宣言を発出した。海外での都市封鎖とは異なり、法的な強制力のない自粛要請だが、これできちんと「ウイルスとの戦い」に勝利できるのか。医師(日本内科学会総合内科専門医)であり、かつビジネススクールで医療経営を教えているという立場の筆者が、中央集権的な管理でウイルスの封じ込めに成功しつつある中国の事例などと比較して、考察してみた。(中央大学大学院戦略経営研究科教授、医師 真野俊樹)
ナイトクラブや集団での会食で
コロナに感染してしまった医師
ナイトクラブを訪れた岐阜大学の精神科医師のほか、集団での会食が原因と思われる横浜市立市民病院や慶応大学病院の研修医から新型コロナウイルスの感染者が出てしまった。
これ以外でも、飲食店やカラオケ店などで感染してしまったという記事が出て、コメント欄などは批判の書き込みで炎上状態になっているようだ。
私も臨床経験はそれほど豊富ではないが、一応、医師の端くれでもあるので自分が感染しないように最善を尽くしているつもりだ。もちろん、周りにも感染させないように気を遣っている。
ただ、ここで中心に考えたいのは医師のモラルについてではない。







