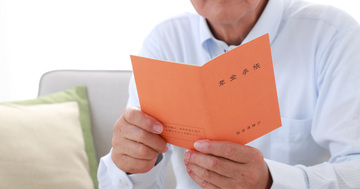Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
コロナで生活が困窮した学生は
忘れずに「学生納付特例」の手続きを
今年も新年度がスタート。学校も入学シーズンを迎えた。
昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、多くの大学が入学式を中止した。今年は、感染対策を行いながら開催するところも増えているが、昨年同様に中止するところもあり、いまだ収束しないコロナ禍が学校生活にも影響を与えている。
コロナ禍であぶりだされたものの一つが、アルバイトで生計を立てている学生のたちの窮状だ。国からの外出自粛要請で、飲食店などが休業や時短営業となり、学生のアルバイトも勤務日が激減。学費が払えなくなり、休学や退学に追い込まれるケースも報告された。
減収で学費や生活費もままならなくなれば、当然、国民年金保険料の支払いも厳しくなっているはずだ。
日本では、この国で暮らす20~59歳のすべての人に、公的な年金保険への加入を義務づけている。たとえ学生でも20歳になれば国民年金に加入し、保険料を納めなければならない。滞納すると、年金の給付を受けられなくなる可能性も出てくるので心配だ。
学生の間は、保険料の納付が猶予される「学生納付特例」があるが、利用できるかどうかは前年の所得によって線引きされる。アルバイトなどの収入が一定以上あると、制度を利用できないこともあるのだ。
だが、コロナ禍で、学生納付特例も臨時の特例措置が設けられ、令和3年分も引き続き特例が継続されることになっているので、忘れずに手続きをしたい。