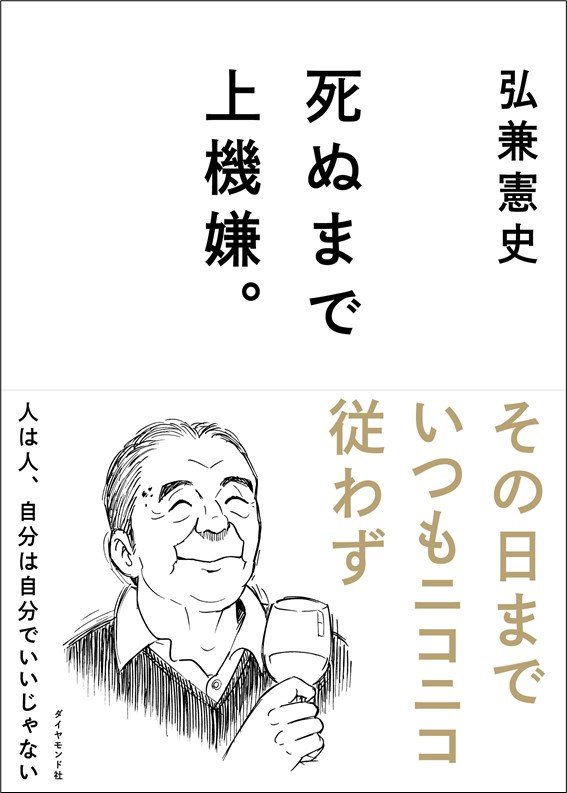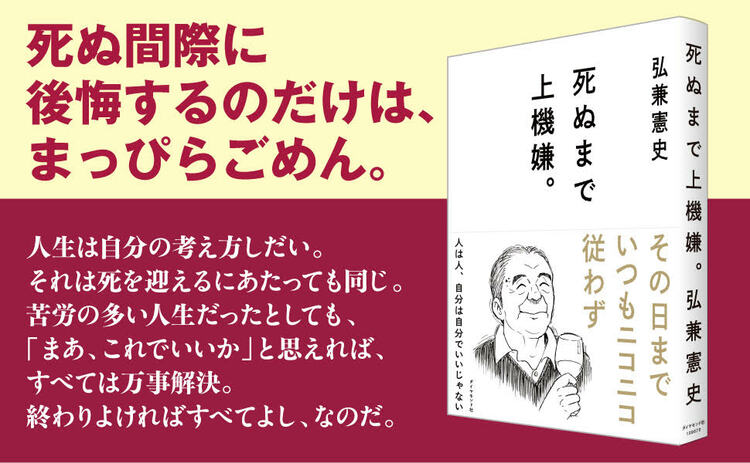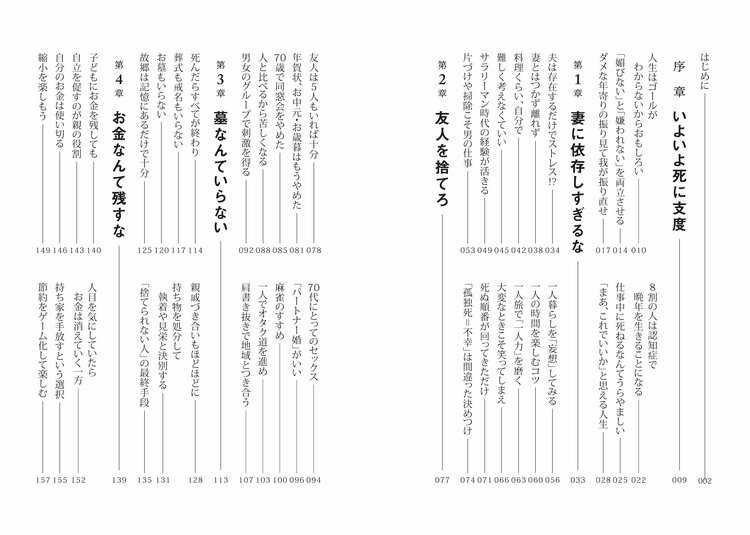壁を超えたら人生で一番幸せな20年が待っていると説く『80歳の壁』が話題になっている今、ぜひ参考にしたいのが、元会社員で『島耕作』シリーズや『黄昏流星群』など数々のヒット作で悲喜こもごもの人生模様を描いてきた漫画家・弘兼憲史氏の著書『死ぬまで上機嫌。』(ダイヤモンド社)だ。弘兼氏のさまざまな経験・知見をもとに、死ぬまで上機嫌に人生を謳歌するコツを説いている。現役世代も、いずれ訪れる70代、80代を見据えて生きることは有益だ。コロナ禍で「いつ死んでもおかしくない」という状況を目の当たりにして、どのように「今を生きる」かは、世代を問わず、誰にとっても大事な課題なのだ。人生には悩みもあれば、不満もあるが、それでも人生を楽しむには“考え方のコツ”が要る。『死ぬまで上機嫌。』には、そのヒントが満載だ。
※本稿は、『死ぬまで上機嫌。』より一部を抜粋・編集したものです。
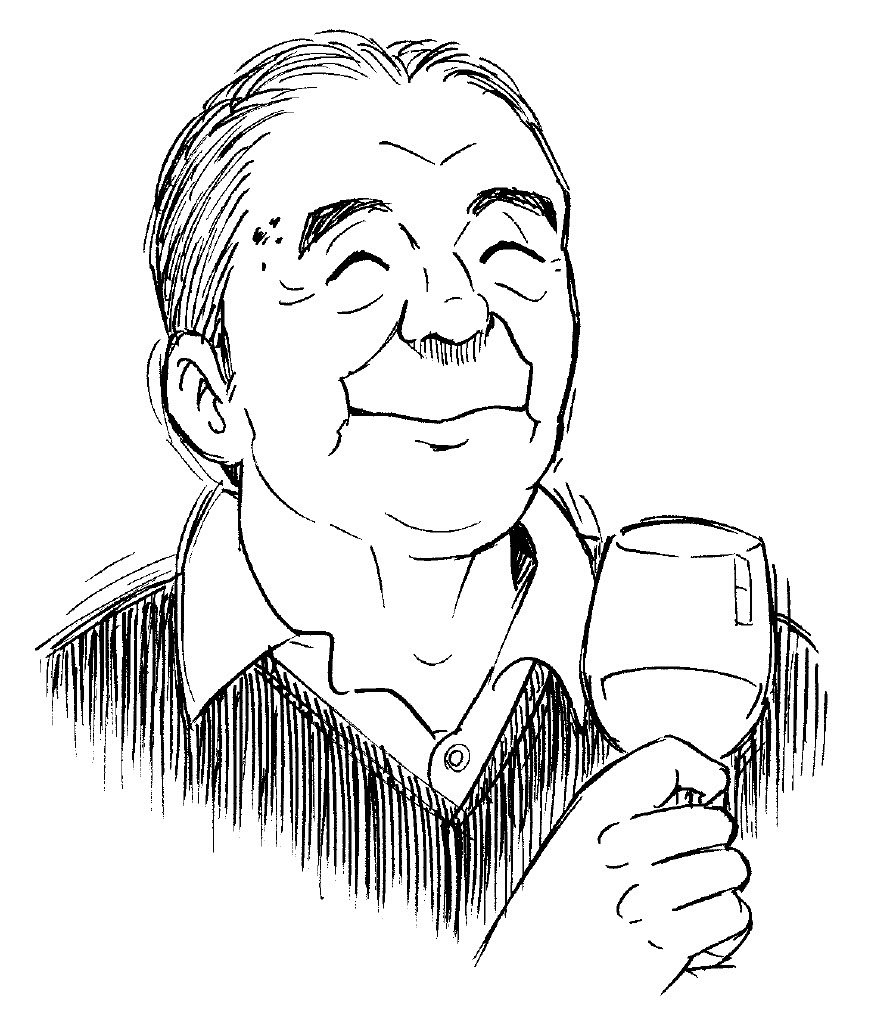 作:弘兼憲史 「その日まで、いつもニコニコ、従わず」
作:弘兼憲史 「その日まで、いつもニコニコ、従わず」
料理は「段取り」
僕が男性に料理をすすめるのは、男性に料理の素質があると考えるからというのもあります。現に飲食業界では、たくさんの男性料理人が働いています。特に中華料理などは、大きな中華鍋で調理する腕力が要求されますから、男性料理人の活躍が目立ちます。
味覚に関しても、サラリーマン時代に接待やランチで外食をたくさん経験している人は、味覚のセンスが磨かれている可能性があります(主婦の方々のほうが優雅なランチをたくさん経験しているかもしれませんが)。料理は「段取り」そのものです。完成にいたるまで、たくさんの工程があります。
まずは食材を買い出しに行くところから始まります。新型コロナウイルスの感染が拡大してからは、あらかじめ献立を決めたうえで、必要な材料をまとめて手に入れる行動様式が定着しつつあります。ただ、店内に入ってから、特売品のほうれん草やナスを見つけ、「このほうれん草はおひたしにしようか、それともバター炒めも悪くないな……」などと考えることもあります。
サラリーマン時代の経験が活きる
さらに自分の食欲や体調、時間的な余裕、そのとき冷蔵庫に入っている食材といったさまざまな要素も踏まえて、最適なメニューを導き出します。こうしたことは、サラリーマン時代に培った予算管理やコスト追求の視点も活きてきます。
さらに料理に不可欠なのは、食材からメニューを構想する企画力です。このスキルは、サラリーマン時代に企画立案の仕事を経験した人には、十分備わっているはずですし、やっていて充実感も得られると思います。買ってきた食材を調理するときには、要領よく作業する必要があります。「鍋に水を入れて沸かしている間に野菜を切り、肉の下ごしらえをして……」といったように、同時進行で複数の作業をこなします。
この手の段取りも、サラリーマン時代の業務と重なる部分が大きいです。慣れてくると、調理をしながら使い終わった食器を手早く洗うなど、後片づけを並行して済ませてしまえるようになります。スキマ時間に何かの作業を組み込み、無意識のうちに効率を上げて全体最適につなげていくのです。これも仕事で培ったスキルを活かせるはずです。
スーパーでの買い物を楽しむちょっとしたコツ
僕はよくスーパーで買い物をしますが、レジに人が並んでいたら、なんとなくスーツ姿の男性とか、仕事帰りっぽい女性がいるほうに並びます。そのほうが経験的に回転が早いと感じるからです。
レジに並んで支払いをする人たちを見ていると、仕事帰り風の人は、レジの台に買い物かごを置いたあと、待っている間に財布からお金やクレジットカードを取り出したり、電子決済用のスマホ画面を用意したりして支払いに備えているケースが多いです。
かくいう僕も、早々に小銭を手の平に出しておき、値段がわかるやいなや、瞬時に支払うようにしています。2374円みたいな金額をムダのない動きでピッタリ出せたときなど、ちょっとした快感を覚えるほどです。昨今はキャッシュレス決済も浸透してきたので、現金を使わない人も増えました。それでも高齢者は現金派が多く、おばあちゃんなどが手にお財布すら用意せず、値段がわかってからようやく手提げからお財布を取り出す……なんていうシーンをよく目にします。
サラリーマンこそ料理をしてみるべき理由
別におばあちゃんを責めるつもりはないのですが、こういうおばあちゃんの後ろに並んでしまったときには、「あー、レジの選択を間違ったな」と苦笑いしてしまうのです。一般的に、男女は脳の構造が違っていて、男性は論理的にものを考え、女性は共感力が高いといわれることがあります。それを裏づけるデータもあれば、逆に根拠がないとするデータも出ていて、素人の僕にはよくわかりません。
ただ、僕たちの世代は男性が外で働き、女性は専業主婦として家庭を守るというスタイルが多数派でした。男性の多くは長年の仕事で段取りを叩き込まれています。それが料理の段取りに応用できると思いますから、ぜひ料理をやってみてほしいのです。
※本稿は、『死ぬまで上機嫌。』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。