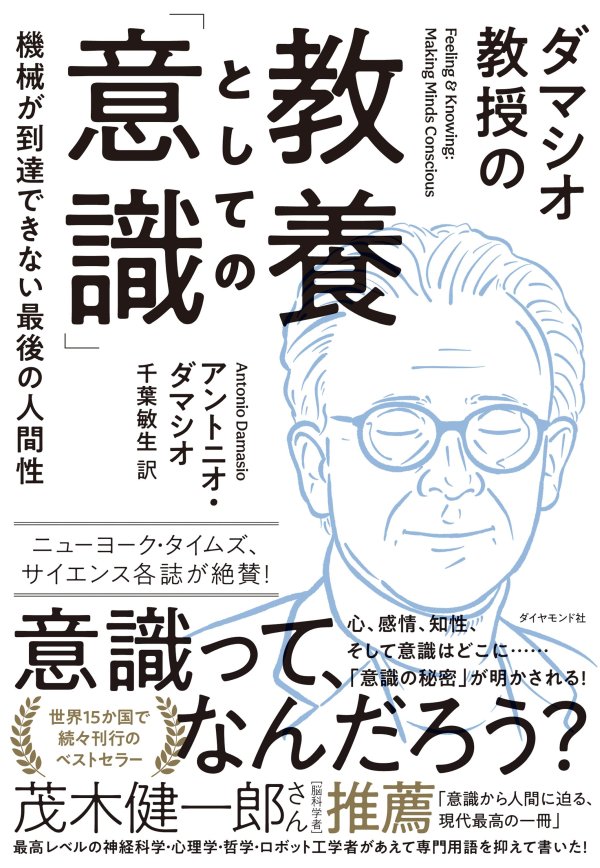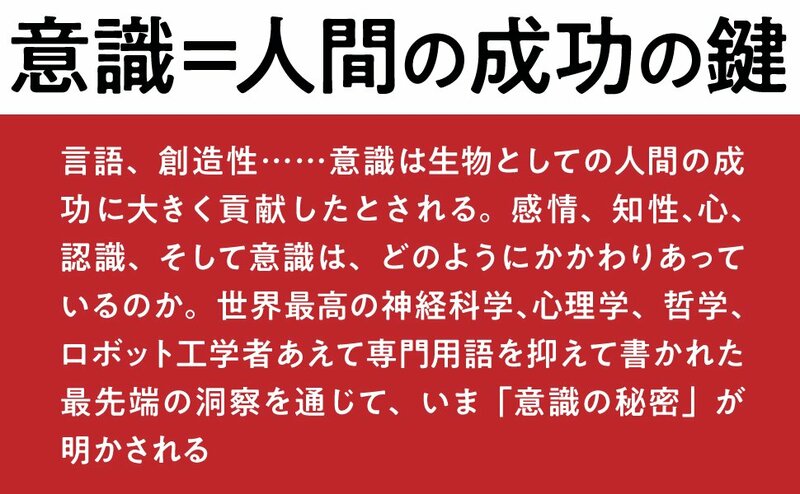言語や創造性をはじめとして、意識は生物としての人間らしさの根源にあり、種としての成功に大きく貢献したと言われてきた。なぜ意識=人間の成功の鍵なのか、それはどのように成り立っているのか? これまで数十年にわたって、多くの哲学者や認知科学者は「人間の意識の問題は解決不可能」と結論を棚上げしてきた。その謎に、世界で最も論文を引用されている科学者の一人である南カリフォルニア大学教授のアントニオ・ダマシオが、あえて専門用語を抑えて明快な解説を試みたのが『ダマシオ教授の教養としての「意識」――機械が到達できない最後の人間性』(ダイヤモンド社刊)だ。ダマシオ教授は、神経科学、心理学、哲学、ロボット工学分野に影響力が強く、感情、意思決定および意識の理解について、重要な貢献をしてきた。さまざまな角度の最先端の洞察を通じて、いま「意識の秘密」が明かされる。あなたの感情、知性、心、認識、そして意識は、どのようにかかわりあっているのだろうか。(訳:千葉敏生)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
エンジニアたちがロボットから省略したもの
AIやロボット工学のパイオニアたちは、人間のように、効率性や機敏性を持ちつつも、そうした物事すべてに対する感情まで兼ね備えた生物、つまり自分のしたこと(あるいはされたこと)に対して喜びや、ときには恍惚さえも覚える一方で、状況によっては不満や悲しみ、さらには苦痛をも覚える生物を、まるまる参考にしたと思うかもしれない。
しかし、聡明なパイオニアたちは近道をし、いきなり核心に迫った。彼らが最も不可欠で有用だとみなした要素(仮に「素朴な知性」とでも呼んでおこう)を再現しようとし、おそらく余分で、さらには不都合だとみなした要素を省略したのだ。そう、感情を。
たぶん、彼らは情緒(アフェクト)を異質などころか、時代遅れな要素とみなしたのだろう。情緒は、明晰な思考、厳密な問題解決、正確な行動へと向かう勝利の行進の中で、後れを取っている要素とみなされたわけだ。
歴史に照らせば、彼らの選択は理解できなくもない。間違いなく、彼らは多くのすばらしい成果と、それに見合う富を生み出してきた。しかし、その過程で、人間の進化に関する重大な誤解を浮き彫りにし、その結果として、AIやロボットの創造性や最終的な知能レベルを、むしろ狭めてしまったのではないかと私には思えてならない。
その進化に関する誤解というのは、本書のこれまでの議論と照らし合わせれば、明白なはずだ。情緒(動因、動機、ホメオスタシス調節、情動に由来する感情体験のこと)の世界は、きわめて適応能力が高く効率的な知性の歴史的な前兆であり、創造性の出現と発達にとって大きな役割を果たした。
この種の知性は、細菌などが隠し持つ暗黙の能力よりは数段上だが、人間の持つ本格的な知性には及ばない。実際、情緒の世界は、意識ある心が少しずつ発展させ、拡張していった高次の知性にとっての足がかりとなった。人間が獲得していった段階的な自律性の発展の根源であり、道具であったのだ。
今こそ、こうした事実を認識し、AIやロボット工学の新たな章を切り開くときだ。「ホメオスタシス由来の感情」に従って機能する機械を開発できることは今や明白で、そのために必要なのは、機能維持のために調節や調整を必要とする“身体”をロボットに与えることだろう。つまり、逆説的とも言えるが、ロボット工学の世界であまりにも高く評価されている堅牢性に、一定の脆弱性を付け加えることこそが必要なのだ。
今日では、これは容易に実現できる。ロボットの構造全体にセンサーを配置し、身体の状態の効率性の良し悪しを検知および記録させ、それに応じた情報を組み込めばよい。「ソフトロボット工学」の斬新な技術の数々は、強固な構造を柔軟で調整可能な構造へと置き換えることで、こうした進歩を実現する。また、この「感知し、感知される」身体の影響を、周囲の状況を処理して反応する有機的な構成要素へと伝達すれば、最も効果的(つまり知的)な反応を選び出せるようになる。
言い換えるなら、機械が身体の内部で“感じた”ことが、周囲の状況への反応に関して一定の発言権を持つようになるわけだ。この“発言権”は、その反応の質や効率性を高め、内部の状況から届けられる助言がない場合と比べて、そのロボットの行動をいっそう知的なものにする。感じる機械は、冷徹で型にはまったロボットなどではけっしてない。ある程度、自分自身に気を配り、自分の置かれた状況を克服できるロボットなのだ。
そのような“感じる”機械は、“意識する”機械になりうるだろうか? まあ、近い将来は無理だろう。感情は意識に至る道の一部であるから、意識に関連する機能的要素を発達させることはできるだろうが、機械の“感情”は生物の感情とは等しくない。こうした機械の最終的な意識の“度合い”は、「その機械の内部」と「周囲」の両方の内的表象の複雑さによって決まるだろう。