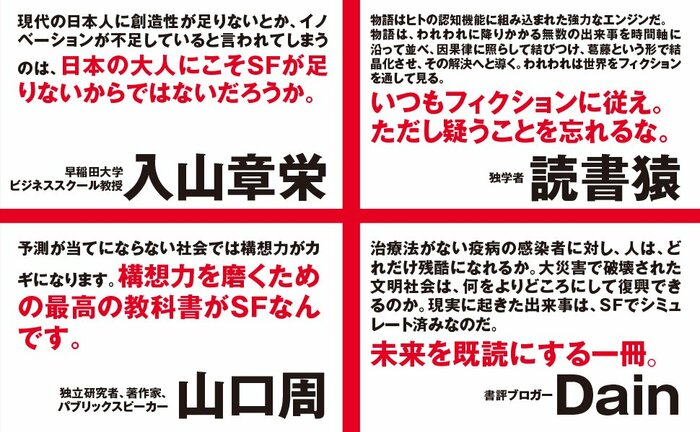『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』著者の冬木糸一さんは、SF、つまり物語を現実が追い越した状況を「現実はSF化した」と表現し、すべての人にSFが必要だと述べている。
なぜ今、私たちはSFを読むべきなのか。そして、どの作品から読んだらいいのか。この連載では、本書を特別に抜粋しながら紹介していく(※一部、ネタバレを含みます)。
『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』の著者の冬木糸一です。エンジニアとして働きながら、ブログ「基本読書」などにSFやらノンフィクションについての記事を、15年くらい書き続けています。
僕はSFを「現代を生きるサバイバル本」と位置付けています。理由は、イーロン・マスクを代表とする起業家たちのインスピレーションの源が、SFだからです。彼らは文字通り、今ビジネス、そして世界を動かしています。頭のいい人ほど、フィクションから発想を得ていると考えることもできます。
今回は本書のなかから「生物工学」関連の本を紹介します。
どんな作品か:親のいない少年少女に課せられた、過酷な「使命」
『わたしを離さないで』
─科学の発展と、無慈悲で、残酷な世界
 カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳、早川書房、2006年(原著刊行2005年)
カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳、早川書房、2006年(原著刊行2005年)
カズオ・イシグロは、ブッカー賞を受賞した『日の名残り』(1989)をはじめ、ベビーシッター役のアンドロイドと少女の関係性を通して未来のAIと人間の関係性の在り方を問う『クララとお日さま』(2021)など、ジャンルを問わず評価の高い作品をコンスタントに発表してきた作家だ。その功績から、2017年にノーベル文学賞を受賞した。『わたしを離さないで』は、そんなイシグロの代表作のひとつである。
本作は、主人公である女性の〈キャシー・H〉が、自身が幼少期に暮らしたヘールシャムと呼ばれる施設での生活を振り返りながら、作中の現在に到達するという構成になっている。
ヘールシャムは、数人の保護官と親のいない少年少女たちで構成される児童養護施設のような場所。物語は当初、思春期特有の問題やいざこざを交えながらも、穏やかで平和な思い出とともに進行する。それだけならどこにもSF要素はなさそうに思えるが、文中には時折、〈提供者〉や〈介護人〉といった不穏な単語が紛れ込む。そして、ヘールシャムで暮らす少年少女たちの行く手には残酷な未来が待ち構えていることが、次第に明らかになっていくのだ。
少年少女たちはなぜ、〈提供者〉と呼ばれるのか。彼らは何のために存在しているのか。なぜ、親がいないのか─本作が「生物工学」の章に含まれる理由を説明するには、これらの核心に触れる必要があるため、以下では物語の結末にも言及する。
物語の主な舞台であるヘールシャムには、語り手であるキャシーをはじめ、ルースやローラ、トミーといった子どもたちが暮らしている。表向きは一般的な全寮制の学校のように見えるが、実態としては外部から隔絶した世界だ。
外の人間との交流は存在しないし、毎週のように健康診断が行われ、彼らにとって健康は最も重要なことだと教えられる。また、ここで暮らす少年少女たちは、性交によって子どもをつくることができない事情もさらりと明かされる。
キャシーの回想の合間には、〈介護人〉となった現在の彼女の語りも挿入されるが、そこでは〈提供〉という耳慣れない単語が幾度も用いられる。やがて、〈介護人〉は〈提供者〉の世話をするのが仕事であり、提供者にとって〈提供〉は避けることのできない使命であることがわかってくる。
〈提供〉とは、臓器提供のことだ。キャシーをはじめヘールシャムで暮らす少年少女たちはみな、クローン人間として親を持たずに生まれてきた子どもたちであり、いずれは〈オリジナル〉に臓器を提供して使命を全うすることになる。それゆえ、彼らに老年は訪れない。直接的な描写こそないものの、おそらく〈提供〉は生死に関わらない部位から始まり、最終的には重要な器官を提供することで死に至る。
とはいえ、ヘールシャムではキャシーらも普通の子どもたちと変わらずに過ごす。当たり前のように喧嘩をし、恋愛をし、絵を描いたり彫刻をつくったりといった創造的な活動も行う。クローンではあっても、人間と何も変わることはない。彼らが臓器提供者であり、将来的に死は避けられないことは表向きには伏せられていて、施設の保護官らも誰もそのことに触れないが、子どもたちは自らがそういう宿命にあることを、断片的な情報をかき集めることで知っている。
あるとき、彼らにその宿命をすべてぶちまけてしまう保護官が現れるのだが、子どもたちの反応は「そんなことはもう知ってるよ」なのだ。運命を知っても、取り乱すわけでもなく、反抗するわけでもなく、あくまでも当然のこととして受け入れている。なぜ、彼らは逃げ出したり、反抗したりしないのか? 生まれたときから「そういうものだ」として育てられてきたら、それ以外の生き方など思いつかないものなのかもしれない。
多くの学校に都市伝説があるように、キャシーらの周りでもある噂が広まる。それさえも、彼らの宿命を変えるようなものではなく、「愛し合う二人がその愛を証明することができれば、提供者になったとしてもすぐに臓器を取られることはなく、三年程度の猶予が与えられるらしい」という、ささやかなものだ。ヘールシャムを出たのち、介護人と提供者という立場で再会したキャシーとトミーは、この噂の真相を二人で確かめにいくが、やはり状況は何ひとつ変わらない。
キャシーはヘールシャム時代、誰もいない寮の中で、「わたしを離さないで」という曲に合わせて、子どもを腕に抱くような仕草でスロウなダンスを踊ってみせる。
「ベイビー、ベイビー、わたしを離さないで」というフレーズの繰り返しに乗せた、子どもを産めない、死すべき運命を生まれながらに決定づけられた少女の踊りは、美しくも残酷なものだ。それを偶然目撃した、ヘールシャムの保護官であるマダムはその場で涙を流し、後にその涙の理由を問われてこう語る。
「あの日、あなたが踊っているのを見たとき、わたしには別のものが見えたのですよ。新しい世界が足早にやってくる。科学が発達して、効率もいい。古い病気に新しい治療法が見つかる。すばらしい。でも、無慈悲で、残酷な世界でもある。そこにこの少女がいた。目を固く閉じて、胸に古い世界をしっかり抱きかかえている。心の中では消えつつある世界だとわかっているのに、それを抱き締めて、離さないで、離さないでと懇願している。わたしはそれを見たのです」(p415-416)
どこがスゴいのか 科学の発展の裏側にある「日陰の世界」を描く
『わたしを離さないで』が試みていることはいくつもあるが、そのうちのひとつはまさにマダムが言うような、科学の発達の裏側で起こりえる無慈悲で残酷な世界を描き出すことだ。
キャシーらはヘールシャムで平和な生活を送り、その後提供者としてその使命を終える─それ以外の可能性を与えられることもなく、職業選択の自由もなく、ただ臓器を失って死んでいく。
現実では、先述のようにブタなどで人間用の臓器をつくる実験が先行しており、本作で描かれるような、臓器提供用のクローン人間が登場することはなさそうだ。だが、「この世界は、無慈悲で、残酷な世界でもある」という観点それ自体は、捨ててはいけないものだ。
『わたしを離さないで』の世界では、クローン人間の存在はできるかぎり世間から隠されている。〈提供者〉の世話をする〈介護人〉もまた、将来的に〈提供者〉になることが確定しているクローン人間であり、提供のプロセスは見えなくされている。そこからは、臓器提供による寿命延長という大いなる恩恵だけを受けて、そのために用意されている残酷なシステムからは目をそむけていたいという人の願望が透けて見える。頭の隅に追いやり、普段はできるだけ考えないようにする。どうしても考えなければいけないときは、クローン人間は自分たちとは違う存在なのだとなんとかして思い込もうとする。彼らは完全な人間ではないのだから、問題にする必要などないのだと。
科学の発展の裏側で、こうした日陰の世界が生み出されている可能性は常にある。われわれは、そんな世界を存在しないと切り捨て、見なかったことにするのではなく、それがあることを見据えていく必要がある。切り捨てた先には、本作で描かれているキャシーの人生があるのかもしれない。そのことを実感させてくれるのは、物語の力のひとつである。
カズオ・イシグロ
1954年、日本生まれ。イギリスを代表する作家として活躍。1989年に『日の名残り』でブッカー賞を受賞、2017年にノーベル文学賞を受賞。
※この記事は『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』からの抜粋です。