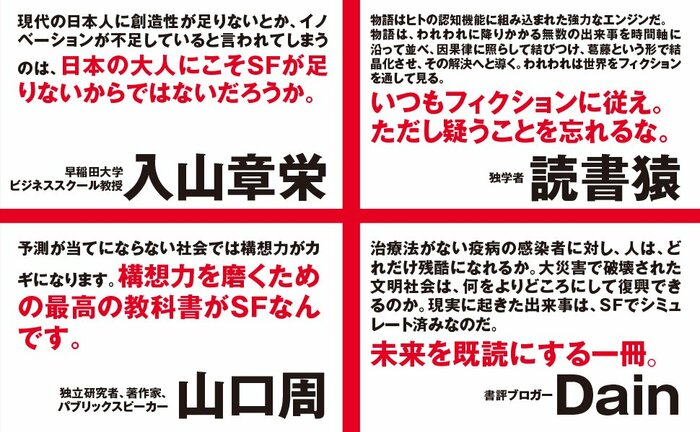『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』著者の冬木糸一さんは、SF、つまり物語を現実が追い越した状況を「現実はSF化した」と表現し、すべての人にSFが必要だと述べている。
なぜ今、私たちはSFを読むべきなのか。そして、どの作品から読んだらいいのか。この連載では、本書を特別に抜粋しながら紹介していく(※一部、ネタバレを含みます)。
『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』の著者の冬木糸一です。エンジニアとして働きながら、ブログ「基本読書」などにSFやらノンフィクションについての記事を、15年くらい書き続けています。
僕はSFを「現代を生きるサバイバル本」と位置付けています。理由は、イーロン・マスクを代表とする起業家たちのインスピレーションの源が、SFだからです。彼らは文字通り、今ビジネス、そして世界を動かしています。頭のいい人ほど、フィクションから発想を得ていると考えることもできます。
今回は本書のなかから「ジェンダー」関連の本を紹介します。
どんな作品か:成人男性に「女性」になる義務を課す社会
『徴産制』
─男が「出産する性」になったとき
日本にも、ジェンダーを扱った小説は数多くある。そのひとつとして取り上げたいのが、田中兆子による連作短編集『徴産制』だ。
女性と男性を分ける根拠のひとつとされるのが「子どもを産む」ことができるかどうかである。しかし、本作では「男も(性転換を行うことで)妊娠できるようになった世界」が描かれる。はたして男性は、自分たちが「出産する性」になったとき、何を思うのか。また、この世界では女性が完全な形で男性になることも可能であり、それが社会にどのような変化をもたらすのかという考察もなされていく。
物語の舞台は、女性にのみ発症し、若年層ほど死亡率の高いインフルエンザが蔓延した世界。その結果、子どもを産むことのできる年代の女性が極端に少なくなっている。しかし同時期に、可逆的に性別を変えることができ、しかも大規模な手術が不要という画期的な技術が登場。この性転換技術をもとに、日本では通称〈徴産制〉が提案、承認され、2093年から施行されることになったという設定だ。
徴産制とは、言うまでもなく徴兵制のもじりだ。日本国籍を有する満18歳以上31歳未満の男性に、最大で24ヵ月間「女」になる義務を課す制度である。
子どもをつくって人口を増やすことを目的とした制度ではあるものの、義務化されるのは女性になるところまで。その後の出産・育児までは強制されていない。女性に変わった時点で給付金が発生し、子どもを産めば新築の家が一軒買えるほどの報奨金をもらえる。
産役についた者は、赴任先で男性と個人的なパートナー契約を結んで性交し、子どもを産む。制度上、人工授精を選んで誰とも性交せずに子どもを産むこともできるが、パートナー契約を結んでいない者は社会で下に見られる風潮もある。通常、子どもは国が引き取って国立の養育施設で育てられるが、養子に出すこともできるし、産役を終えた後にそのまま女性としてとどまり、自ら子育てをすることも可能だ。フィクションながら、いかにもありそうな社会の在り方が、様々な立場の〈産役男〉たちの視点を通して描かれていく。
どこがスゴいのか:「違う性別」から世界を見るということ
女性でも男性でも「一時的に別の性の持ち主として生きてみたい」と思ったことがある人はいるだろう。ある意味、徴産制はそうした願望を叶えてくれるものではあるのだが、そうハッピーな制度というわけでもない。
第一章「ショウマの場合」では、徴産制が施行された直後、田舎で初めての産役についたショウマの身に起きる、少々残酷な体験が描かれていく。
性転換が行われると精神もまた女性的になるというが、体が一からつくり変えられるわけではないので、基本的に大柄な男性はそのまま大柄な女性になってしまう。ショウマは身長180センチ、体重72キロという体格の持ち主で、もとの容貌も決して美しかったわけではない。そんな彼は、オオサカの街を歩いているだけで、「どけや、デカドブス」などと男性から心無い言葉をあびせられ、かなりのショックを受けてしまう。男性であるときには受けなかった仕打ちを、女性の姿になると当たり前のように受けるのだ。
見た目のいい産役男が次々と契約相手を見つけていくなかで、ショウマにはなかなか相手が現れない。田舎に戻れば祖父から、いつになったら子どもができるんだ、女になった証拠を見せろ、セックスはどうなんだ─などと自覚なきセクハラにさらされる。
こうした仕打ちを受けて初めて、以前は彼らと同じ男であったショウマは、自分も知らないうちに女性たちを傷つけていたかもしれない可能性に思い至る。
そんなショウマにも、意識を変えて身だしなみに時間を使うようになったことで変化が訪れる。化粧をして、ロングヘアのウィッグをつけた自分の姿を褒められる喜びを知り、女としての自分を肯定できるようになっていくのだ。やがて、うどん屋の店主アオタさんと結ばれたショウマは、女性であることの証として子どもを欲するようになっていく。
子どもを産むこと=女性の証であると考える女性ばかりではない。産役男となった男性たちも同様で、彼らを通して各人各様のスタンスが語られるのも、本作の読みどころだ。
第二章「ハルトの場合」では、将来的に政治家、それも総理大臣になることを目指しているエリート官僚、ハルトの産役が描かれる。
ハルトは強固な徴産制反対者だが、ピカピカの経歴に傷をつけたくない一心で産役に従っている。すぐれた容姿を持つハルトは女性としても引く手あまた。エリート官僚というポジションも手伝って、優秀な契約相手をとっかえひっかえしているが、なかなか妊娠に至ることができない。子どもを人工授精で産むことは、ハルトにとっては敗北を意味するので選択肢にはなく、次第に精神的に追い詰められていく。
そんなハルトを救うのは、行きつけのバーに集まる産役男たちだ。得意とするメイクを彼らに教えることで、これまでの人生では出会ったことのない属性の人々との交流が生まれ、ハルトはその楽しさを知っていく。妊娠は体の問題なので、エリート官僚のように努力でのし上がってきた人間であってもどうにもならないこともある。だが、見た目なら技術で向上させられる。
ずっと「国のため」に生きてきたハルトだったが、バーに集まる産役男たちは自由だ。なかにはピルを飲んで避妊している産役男もいる。「国のため」を思えば子どもを産むべきなのだが、徴産制では「女性になる」ところまでが義務なので、必ずしも出産はしなくていい。男だった頃は、子どもを産まない女性には価値がないと考えてきたハルトだが、バーの面々の様々な生き方に触れて、国のために我慢をすることをやめ、自分のため、目の前の人のために活動しようと決意する。
本作では、自分の夫が女性になり、男性とセックスすることに対して、その妻が複雑な感情を覚えるエピソードや、生来の女性が男性になることを決意するエピソードなど、女性から見た徴産制もきっちり描かれている。何度も「自分だったらどうするだろう」と考えずにはいられないはずだ。
田中兆子(たなか・ちょうこ)
1964年、富山県生まれ。本作『徴産制』で、2019年度センス・オブ・ジェンダー賞大賞を受賞。
※この記事は『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』からの抜粋です。