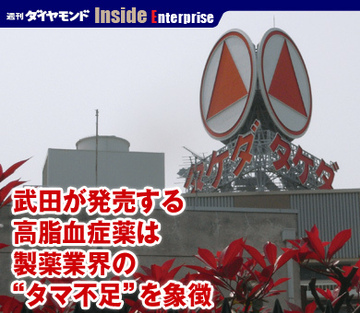国内製薬最大手の武田薬品工業は2度の大型買収を経て、世界企業へ様変わりした。主力製品の特許切れに苦しむ中での急速なグローバル化は、財務や社員の意識に歪みも生み、一筋縄ではいかない。 (「週刊ダイヤモンド」編集部 山本猛嗣)
「武田薬品前」と書かれた乗降場。そこに停車したバスからあふれ出てきたさまざまな人種が白く巨大な建物に吸い込まれていく。武田薬品工業の研究拠点である湘南研究所(神奈川県)の出勤風景はまるで外資の日本オフィスのそれを見ているようだ。
役員の顔触れを見ても同じ錯覚に陥る。取締役7人のうち、2人が外国人。英国の大手製薬会社、グラクソ・スミスクラインで研究開発本部長として活躍した「タチ・ヤマダ」こと山田忠孝取締役を含めれば、3人がビジネスで英語を“公用語”とするメンバーだ。
経営に関わる上級幹部のコーポレートオフィサーは9人中6人が外国人と外資系出身者。海外従業員比率を見れば、2007年度は43.3%であったものが11年度には68.6%まで跳ね上がっている。
昨年6月、都内で長谷川閑史社長の講演を聴いたある内科医は「内向的な会社というこれまでのイメージがすっかり消えた」と驚く。「社長の目は完全に海外に向いていた」。