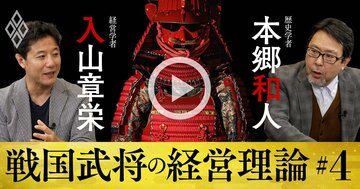「仕事が遅い部下がいてイライラする」「不本意な異動を命じられた」「かつての部下が上司になってしまった」――経営者、管理職、チームリーダー、アルバイトのバイトリーダーまで、組織を動かす立場の人間は、悩みが尽きない……。そんなときこそ頭がいい人は、「歴史」に解決策を求める。【人】【モノ】【お金】【情報】【目標】【健康】とテーマ別で、歴史上の人物の言葉をベースに、わかりやすく現代ビジネスの諸問題を解決する話題の書『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、島津斉彬など、歴史上の人物26人の「成功と失敗の本質」を説く。「基本ストイックだが、酒だけはやめられなかった……」(上杉謙信)といったリアルな人間性にも迫りつつ、マネジメントに絶対活きる「歴史の教訓」を学ぶ。
※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
抵抗する者
最後に切腹
貧しい農民の子として生まれた豊臣秀吉と、豪族の生まれである前田利家との間には、もともと大きな身分格差がありました。
本来であれば、利家は秀吉の出世にわだかまりを抱いても、なんら不思議ではありません。
実際、利家と同じく勝家の配下にいた佐々成政(?~1588年)という武将は、秀吉の家臣となることをよしとせず、長いこと抵抗しました。
結局のところ、敗れて秀吉の家臣になりますが、肥後(熊本)の支配を任されながらも失敗し、最後は切腹してしまいます。
「律儀さ」こそ
最強の武器である
それに対して利家は、秀吉の出世に大きなわだかまりを抱くこともなく、友情を保ちつつ、比較的スムーズに主君と家臣の関係に移行しました。
そして、家臣として利家は秀吉の天下統一を支え続けたため、秀吉は利家に対して大きな領土と五大老という重臣の立場を与えたのです。
晩年に至るまで利家に対する秀吉の信頼は揺らがず、遺言のなかで利家を「律義者(正直者)」と評価し、自分の子である豊臣秀頼を託すまでになります。
わだかまりを抱かず
長い繁栄につながる
残念ながら秀吉の死(1598年)の直後に利家も亡くなりますが、豊臣政権下で大きな力をもっていた前田家を徳川家康も軽く扱うことはできませんでした。
前田家は加賀百万石の当主として、江戸時代を生き抜きます。出世競争には負けた前田利家でしたが、秀吉との友情を大事にして、与えられた立場で懸命にとり組みました。
その結果として、滅亡した豊臣家よりも長い繁栄を前田家にもたらしたのです。
※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。