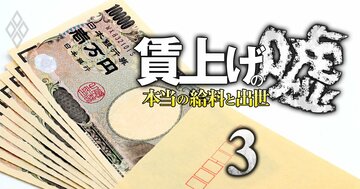写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
ある大規模調査によれば、労働者の労働時間が短くなっているにもかかわらず、生産性は落ちていない。その理由として、「1週間のうち1日だけ楽をすること」が、企業・労働者双方にとってメリットがあるためという――。(イトモス研究所所長 小倉健一)
テレワーク実質率は
高いまま
東京都の産業労働局が調査をしている「都内企業のテレワーク実施状況」(3月)には、こんな結果が出ている。
(1)都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は43.4%。2月の前回調査(43.4%)と同率。
(2)テレワークを実施した社員の割合は36.0%と、前回(35.2%)に比べて、0.8ポイント増加。
(3)テレワークの実施回数は、週3日以上の実施が45.6%と、前回(40.1%)に比べて、5.5ポイント増加。
さらに、従業員が増えれば増えるごとにテレワークの実施率は高まる。従業員が300人以上の大企業では、66.7%がテレワークを実施している。
全国規模ではどうだろう。イトーキは5月23日、全国の正社員・経営者約5,000人を対象に、働き方・オフィス環境に対する意識と満足度向上要因をまとめたリポート「働き方とオフィス2024」を発表した。それによれば、新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」へと移行した2023年5月以降、1日以上リモートワークしている人の割合は全体の26.7%だった。
製造業、サービス業、小売業など従業員が現場にいる必要のある業種・業界では、テレワークの実施はそもそも不可能であることを考えれば、テレワーク、在宅勤務はかなり定着してきたということだろう。
リモートワーク普及も
仕事と私生活の境目が曖昧に
しかし、リモートワークにしたからといって、労働者が楽になっているわけではないようだ。2021年に総務省統計局が実施した「社会生活基本調査」によると、通勤時間の全国平均は往復で約1時間19分であり、リモートワークが実現することでこの時間が浮くはずなのに、不思議な現象だ。
例えば、日経新聞ではこんな指摘がされている。
<在宅勤務は出社する負担を軽くした半面、仕事と私生活の境目を曖昧にしたとの指摘もある。自宅にパソコンや資料を持ち帰れば、いつでも仕事をできるためだ。
連合の調査では「出勤するよりも長時間労働になることがあった」と回答した人が5割を超えた。深夜に業務した人の割合も32.4%に上った。(中略)
在宅勤務は仕事と育児・介護などの両立を後押しするとされてきた。だが実際に子供の世話をしながら業務に集中することは容易ではない。
「オンライン会議中に子供が帰宅するとお帰りも言ってあげられない」。東京都内の不動産会社に勤める30代女性はこう語る。仕事の合間に家事をこなした後、子供たちが就寝したのを見計らって深夜0時ごろまで働くこともあるという>
(日経新聞デジタル『祝日は多いのに…週末も仕事 在宅勤務「見えない残業」』2023年12月28日)
この報道に接して、私も思い当たる節があった。自宅で作業できるとリラックスできて、長時間労働をしてしまいがちだ。また、ネットフリックスやアマゾンなど誘惑も多いので、注意力が散漫になるときも多い。この記事のように、家事をする必要がある人はなおさら大変だろう。時間というものは本当にあってないようなものだ。