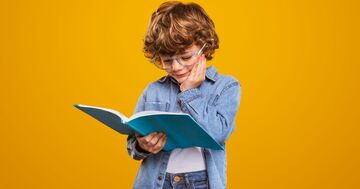お子さんの「国語力」が伸びないと悩んでいる親御さんが多いのではないでしょうか? そんななか、「本を読まない子でも“中学受験の国語”は全然大丈夫!」「国語はテクニック! 解き方さえ分かれば合格点は取れる!」など、心強いメッセージを届けてくれる注目の国語講師がいます。『中学受験 となりにカテキョ つきっきり国語』シリーズなどの著書があり、安浪京子先生も絶賛する教育メソッドで、子どもたちの国語力をグングン上昇させてきた金子香代子先生です。本連載では、そんな金子先生に、「中学受験の国語」について、知りたいことを聞いてみました。(構成:書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「読書習慣がある」=「国語が得意」ではない
国語力を身につけるには、「読書習慣が大切」とよく言われますが、ただ本を読んでいればいいということではありません。
読書というものは「主観的に読んでもいいもの」です。好き勝手に読み進めたっていい。
ところが、受験の読解問題は「客観的に読まなければならないもの」です。
受験の国語では、目の前の文章が言わんとしていることを客観的に読み解かなければいけません。ここが「読書」と「読解」の大きな違いです。
たとえば、「このときの花子の気持ちを答えなさい」と聞かれたときに、子どもは読んだときの自分の感想と一致する選択肢を選んでしまいます。
花子が喜んでいても、読んだ本人がかわいそうと感じていれば「かわいそう」の選択肢に飛びついてしまう。これでは点はとれません。
また説明文であれば、「人類は人工知能とうまく共存していくべき」と筆者が言っていれば、それを答えとすべきです。
「人類の脅威になりえるから研究開発を止めるべき」という選択肢を見て、そちらに本人が共感しても、その選択肢を選んではいけないのです。
「主観で読んでるようではだめ」「文脈をちゃんと理解して、登場人物や筆者の気持ちになって読みましょう」と繰り返し伝えていく。私たち国語講師の仕事のなかでも、すごく大事なところです。
ですから、読書量が豊富でも主観で読んでいるうちは、国語が得意科目にはなりません。
「本は読むのに、国語ができないんです」とおっしゃる親御さんがたくさんいますが、ここに原因があるわけです。
「読書習慣」自体はとても大切なもの
とはいえ、読書習慣自体が悪いものかと言えばそんなことは全然ありません。本好きという特性は国語を得意教科にしてくれる力があります。
もし、お子さんに読書習慣があるならば、さきほどお伝えしたように、まずは「客観的に読むこと」を教えてあげましょう。
そのうえで、可能であれば多様なジャンルを読むことをおすすめしてあげてください。
本好きな子が何を読んでいるかといえば、だいたい小説です。
エッセイや伝記などであれば、小学生でも楽しめるコンテンツがありますから、そういったジャンルの面白い本が世の中にはあるということを教えてあげるといいと思います。
いろんなジャンルを読んで、多様な語彙や様々な知識に触れる経験は、お子さんの国語力にとって間違いなくプラスです。
一方でいくら本好きな子でも、説明文を小学生のうちから前向きに読むのはなかなか難しいと思います。
説明文については、受験用のテクニックを身につけて得点をとっていくのが現実的な方法でしょう。
そもそも、中学受験の国語は、技術を身につければ充分合格点がとれるものです。
お子さんが本好きだからといって、親御さんが読解技術の習得を軽視すると、国語の得点が伸び悩むこともあるのでそこは注意してください。