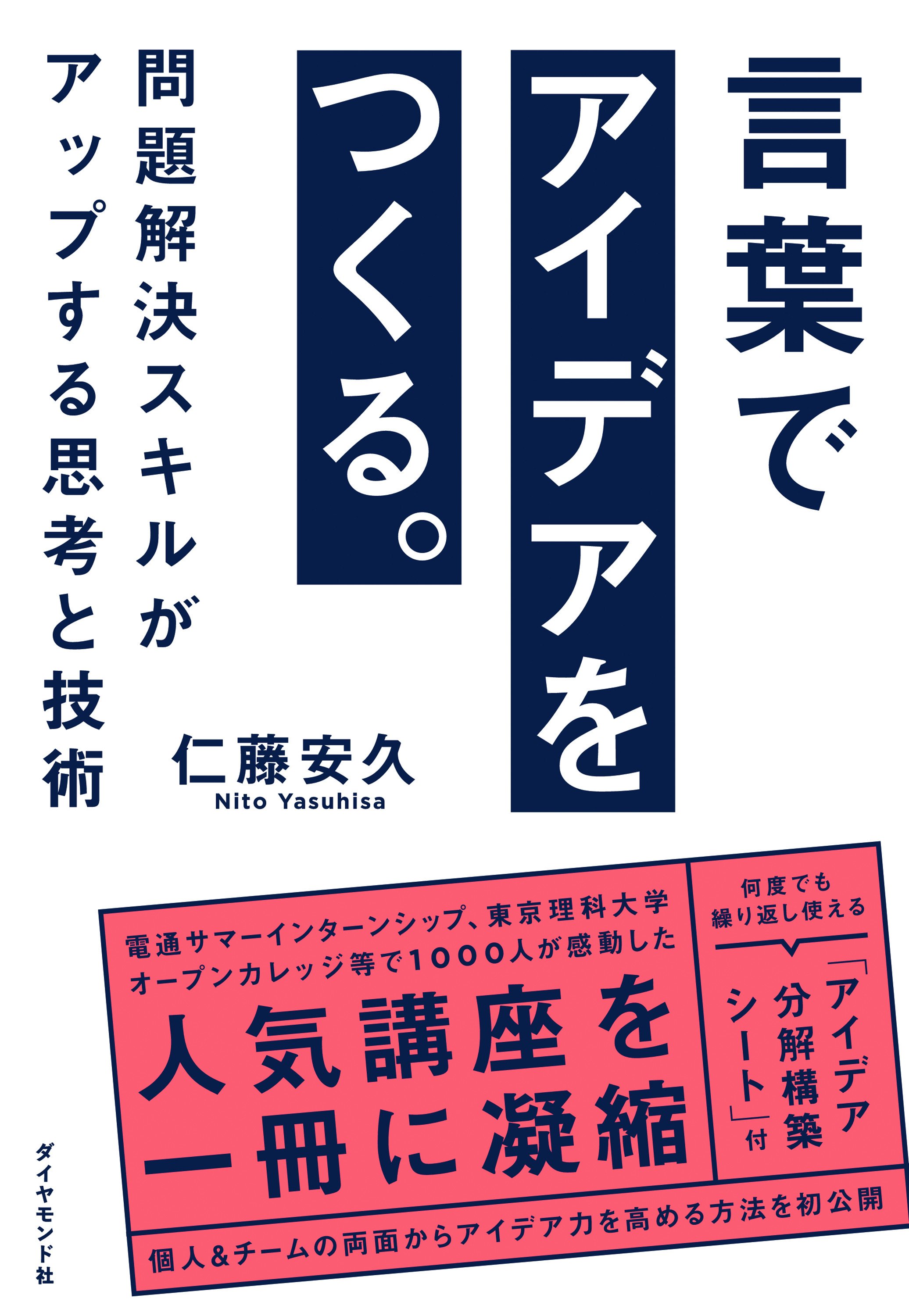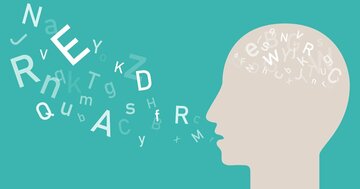価値観が多様化し、先行き不透明な「正解のない時代」には、試行錯誤しながら新しい事にチャレンジしていく姿勢や行動が求められる。そのために必要になのが、新しいものを生みだすためのアイデアだ。しかし、アイデアに対して苦手意識を持つビジネスパーソンは多い。ブランドコンサルティングファーム株式会社Que取締役で、コピーライター/クリエイティブディレクターとして受賞歴多数の仁藤安久氏の最新刊『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』は、個人&チームの両面からアイデア力を高める方法を紹介している点が、類書にはない魅力となっている。本連載では、同書から一部を抜粋して、ビジネスの現場で役立つアイデアの技術について、基本のキからわかりやすく解説していく。ぜひ、最後までお付き合いください。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
アイデアを出してみましょうとか、ブレインストーミングをしようと思っても、停滞してしまうことは多々あります。そのときに、どのように対処するのがいいのでしょうか? 私の経験から、効果的な方法についてお伝えします。
①チームをさらに小分けにする
会議の人数をさらに分割しましょう。8人だったり6人だったりするときも、いったん半分に割ってみて時間を区切って少人数のグループで話し合ってもらいます。それぞれのチームで話したことをシェアしてもらうのも、とてもよい方法です。
②議論の過程を可視化する
ふせんを使う、もしくは、オンラインボード(Miroなど)を使ってみることで、発想が活性化することがあります。議論の過程を可視化することによって、課題設定まではよかった、もしくは、この発想軸は可能性がありそうだ、など「どこに立ち戻って、みんなでアイデアを考えるべきか」といったフォーカスするポイントが見つけやすくなります。
③アナロジーの問いかけを行う
狭い領域で考えすぎていてアイデア発想が停滞することがあります。そのときには、先述したアナロジーでの問いかけをしてみるのもひとつの手です。
アナロジーとは、「論理学で、物事の間の特定の点での類似性から、他の点での類似性を推論すること」と言われますが、平たく言えば「別の領域の事象やアイデアから、要素を借りてくること」です。
先述した際には、「全社イベントがあるのだけど参加者のモチベーションづくりに困っている」という状況があったときに「地域のお祭り」への参加の構造をヒントにしました。
リーダーは、停滞した状況で、「こんなことをヒントに考えてみるとどうだろう」とアナロジーの問いかけを投げ込めるように用意しておきたいところです。
どういうところからアナロジーを持ってくるべきか、ということですが、身の回りにある事象についても、その背景や成り立ちを調べておく癖をつけておくと、アナロジーのストックとして持っておけるように思います。
たとえば、日本三大○○、といったものがあります。
こちらを調べてみると、面白い気づきがあります。
日本三景というと「松島・天橋立・宮島」と言われます。これは、儒学者、林春斎が『日本国事跡考』の中で記述しているものなので、この3つに異論はありません。
しかし、誰が定めたのかはっきりとしない、日本三大◯◯、というものも多くあります。これらを見てみると、3つがきちんと定まっていないことが多くあります。
たとえば、日本三大和牛。こちらは、「松阪牛・神戸牛・米沢牛」と言っているものだけではなく、「松阪牛・神戸牛・近江牛」と言われていたりします。
他にも、日本三大うどん。こちらは「讃岐うどん・稲庭うどん」というところまでは、ほぼ相違ないのですが、3つ目は「水沢うどん」「五島うどん」「氷見うどん」「きしめん」など、様々な説が散見されます。
この「三大○○」を声高に言っているのは、3番目に食い込みたいと企んでいる人たちなのです。こちらをアナロジー的に応用すると、業界の4番手、5番手の奥の手として、もしくは、カテゴリーとして、「令和の三種の神器」などと言い切ってしまう作戦が考えられます。
④最低のアイデアを出して結論づけようとする
これは、「想定し得る中での最低の提案」をすることにより、「その最低の提案が可決されるのを阻止」しようとする、ことです。
あるいは、誰かが最初に最低のアイデアを口にした結果、2人目以降の発言のハードルが下がり「もしかしたら、こんなことを言ったらばかばかしいと思われるかも」といった心配が薄れ、皆の間で議論が活発化する、ということがあります。
かつては「マクドナルド理論」と呼ばれていたこともあるようです。
お昼時に食事に出る場合を想像してみてください。
「ランチ、どこにする?」とみんなに問いかけますが、誰もなかなか意見を言わないみたいなことがありませんか。そうこうしているうちに、短いランチタイムを無駄に消費してしまいます。
マクドナルド理論とは、そういうときに「マクドナルドに行こう!」と提案してみるとどうでしょう、といったものでした(あくまで、数十年前のアメリカでの話ということで、いまでは消極的ではなく積極的に選ぶ選択肢としてマクドナルドはあると思います)。
すると、「いや、マクドナルドはないでしょ」というようにみんなは否定しますが、不思議なことにそれ以後は議論が活発化していき、次々と提案がされるようになっていきます。
「イタリアンの○○は、どうだろう?」
「昨日はお肉だったから、魚とかがいいかもね」
「それだったら、このお店はどう?」
といったように、ブレストのときに必要なのは「いいアイデア」ばかりではありません。そうではなく、「これはないよね」といったアイデアにも、アイデア発想を活性化させる役割があるのだということを覚えておいてください。
くだらないアイデアを出すのは勇気がいりますが、リーダーが率先して出して、こういうアイデアでいいじゃない、というようにあえて結論づけようとしてみてください。すると、黙っていたメンバーの意見が出てくるようになる可能性が高いです。
(※本稿は『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』の一部を抜粋・編集したものです)
株式会社Que 取締役
クリエイティブディレクター/コピーライター
1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。
2004年電通入社。コピーライターおよびコミュニケーション・デザイナーとして、日本サッカー協会、日本オリンピック委員会、三越伊勢丹、森ビルなどを担当。
2012~13年電通サマーインターン講師、2014~16年電通サマーインターン座長。新卒採用戦略にも携わりクリエイティブ教育やアイデア教育など教育メソッド開発を行う。
2017年に電通を退社し、ブランドコンサルティングファームである株式会社Que設立に参画。広告やブランドコンサルティングに加えて、スタートアップ企業のサポート、施設・新商品開発、まちづくり、人事・教育への広告クリエイティブの応用を実践している。
2018年から東京理科大学オープンカレッジ「アイデアを生み出すための技術」講師を担当。主な仕事として、マザーハウス、日本コカ・コーラの檸檬堂、ノーリツ、鶴屋百貨店、QUESTROなど。
受賞歴はカンヌライオンズ 金賞、ロンドン国際広告賞 金賞、アドフェスト 金賞、キッズデザイン賞、文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など。2024年3月に初の著書『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』を刊行する。