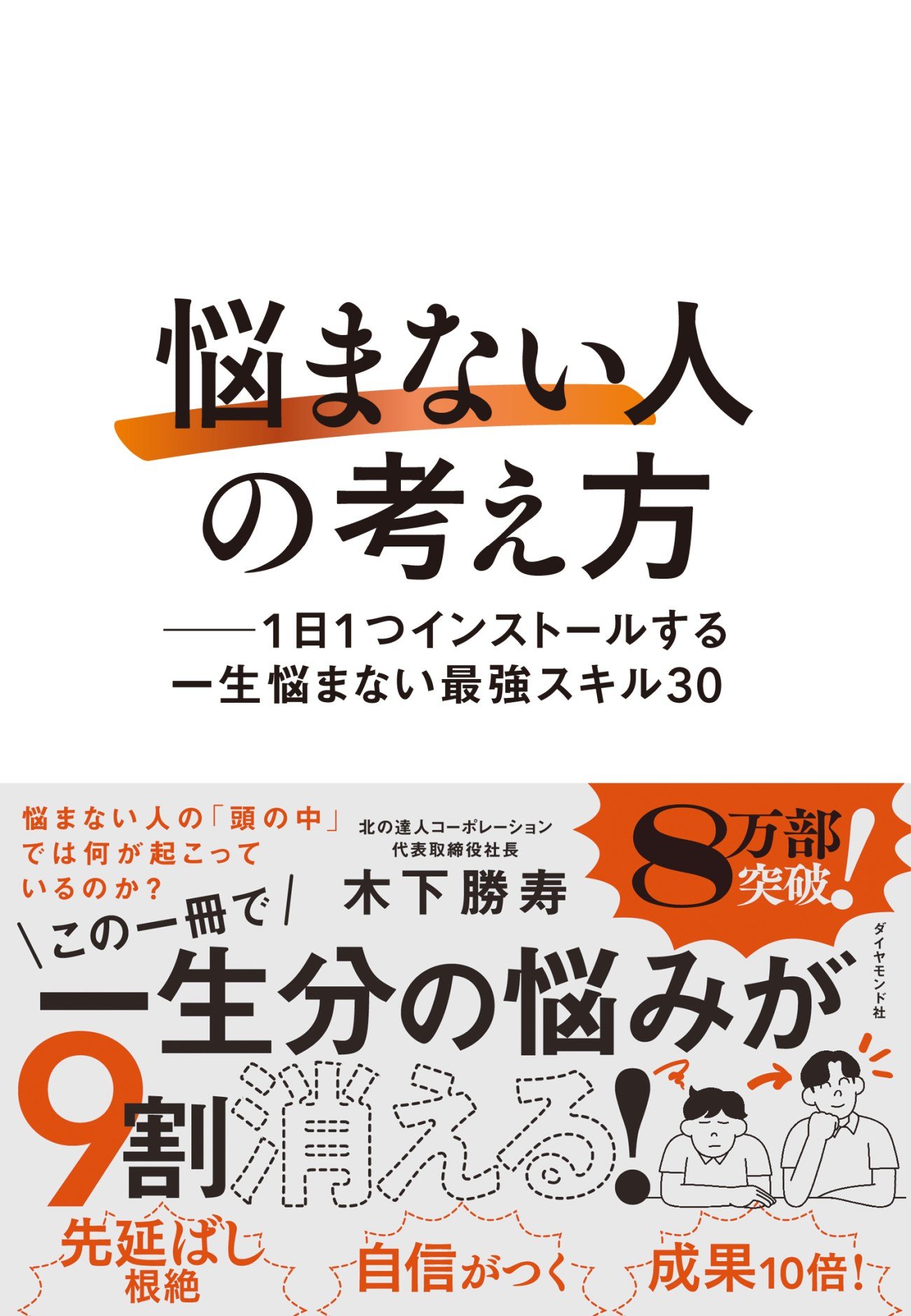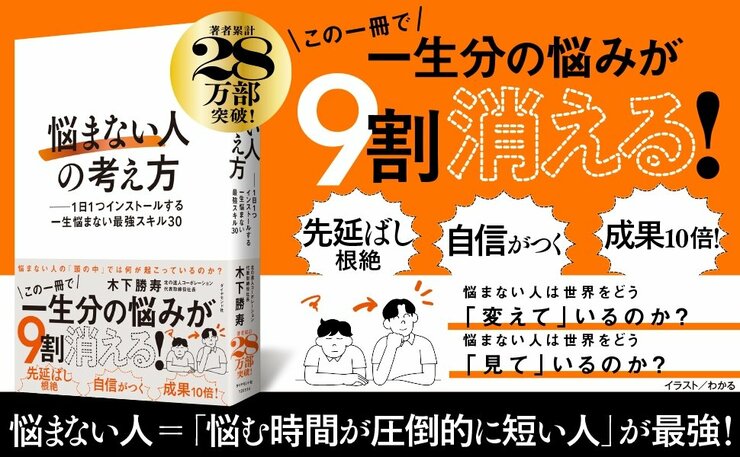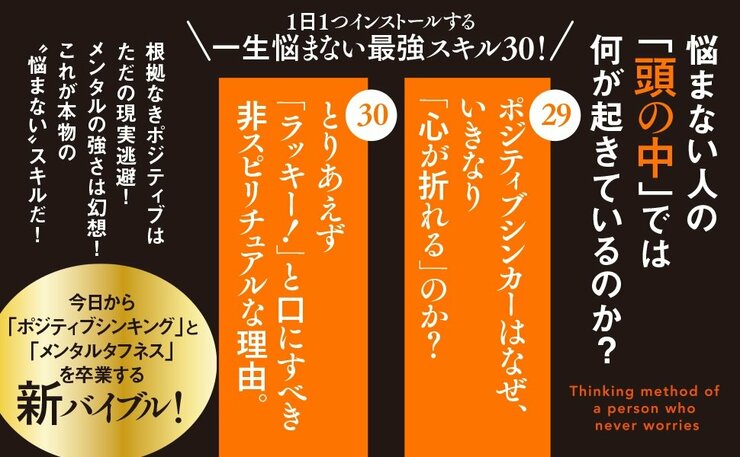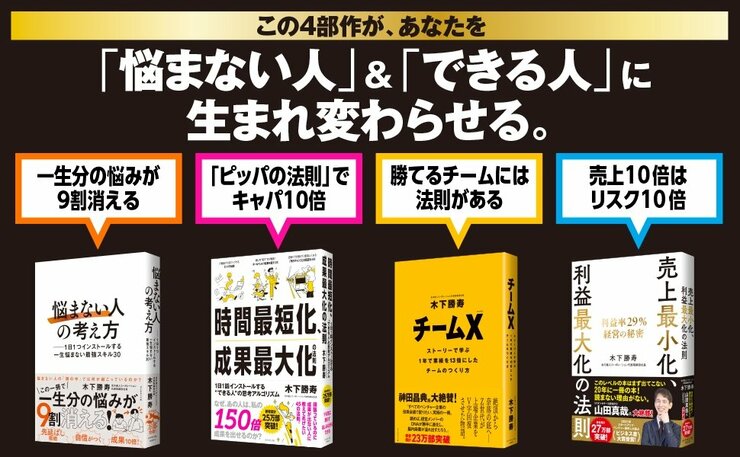職場には、いつも責任転嫁する「他責の人」と自分で責任を取る「自責の人」がいる。
この差は、一体、何だろう? どうしたら前者は後者に変わるのか?
今、ビジネスパーソンから経営者まで数多くの相談を受けている“悩み「解消」のスペシャリスト”、北の達人コーポレーション社長・木下勝寿氏の自己啓発書『「悩まない人」の考え方 ── 1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30』が話題となっている。
「ここ20年以上悩んでいない」という著者を直撃。本稿では新年のスタートダッシュに役立つ「悩まない人の思考法」をお届けする(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「他責の人」と「自責の人」の評価
想定外のトラブルやミスが起きたとき、評価する上司側からすれば、
「今回は想定外の事態が起きたので、自分の責任ではありません」
と言う人より、
「今回は自分の想定が甘かったので、自分の責任です」
と言う人のほうを評価します。
なぜなら、前者(他責の人)は今後の改善の努力が期待できませんが、後者(自責の人)は想定の範囲を広げる努力をするので今後の成果が期待できるからです。
次回、同じことが起きても、前者は想定外なので同じようにミスをしますが、後者は想定外をなくす習慣をつけているため、ミスをしない可能性が高いのです。
上司はミスを自分の責任(自責)とする人を評価すべきです。
稀にそれを知っていて何でもかんでも「自分の責任です」と言うだけで改善努力をしない人もいますが、上司は普段の行動を観察して、自責の文化をつくっていくことが大切です。
「他責の人」が支配する職場の未来
本書では、「他責の人」の事例を挙げました。
□「この顧客はいつも文句ばかり言うクレーマーだ。要求が無理難題すぎるから、まともに対応できなくても仕方がない……」
□「プロジェクトが失敗したのは、同僚がスケジュールを守らなかったからだ。彼女がもっときちんと仕事をしていれば、結果が出せていたはず……」
□「友人がいきなり大きな声を出したので、びっくりして大事なお皿を落としてしまった。彼がそんな発言をしなければ、お皿を割らずにすんだのに……」
□「電車の人身事故で足止めをくらったせいで、打合せに遅刻してしまった。事故がなければ余裕で間に合ったのに……」
□「天候が悪かったからイベントが中止になった。雨が降らなければ、いま頃楽しめていたのに……」
「他責の人」ばかりの職場の未来は悲惨です。
当事者意識がない集団では、みんなが人のせいにし、いつまで経っても責任の押しつけ合いが終わりません。
「他自責混在思考の人」と「全部自責思考の人」の決定的な違い
多くの人は一部の出来事を「自責」、一部の出来事を「他責」として解釈します。
私はこの思考アルゴリズムを「他自責混在思考」と呼んでいます。
世の中にはまったく責任を取ろうとしないように見える人がいます。
しかし、すべてを他責で捉えている人は現実的には存在しません。
そういう人は他責幅が異常に広い「他自責混在思考」と言えます。
一方で、「悩まない人」は「全部自責思考」です。
「全部自責思考」の人は、全責任は自分にあると考えます。
「他自責混在思考」の人と「全部自責思考」の人では「原因」と「責任」の捉え方が違います。
「他自責混在思考」の人は、出来事の「原因」と「責任」を同一視しています。
一方、「全部自責思考」の思考アルゴリズムでは、「原因」と「責任」を分けています。
「全部自責思考」の人は、すべての出来事の「原因」が自分にあると考えているわけではありません。
ただ、自分が「原因」であろうとなかろうと、その「責任」はとにかくすべて「自分」にあると考えているのです。
また、「責任を取る」ということの捉え方も違います。
「他自責混在思考」の人は「責任を取る=罰則を受ける」と考えます。
だから、他人が原因の責任を取らされるのは損以外のなにものでもないのです。
一方、「全部自責思考」の人は「責任を取る=問題を解決する」と考えます。
だから責任を取る行為とは、自分はもちろん、他人やほかの原因で失敗したことに対して問題を解決したり再発防止策を打ったりすることなのです。
まずは少しずつでも、
「それは自分の責任です」
と言える人を増やしていく。
リーダーや管理職が「悩まない人」になるために、一歩ずつ改善していきましょう。
(本稿は『「悩まない人」の考え方──1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30』の著者による書き下ろし記事です。)