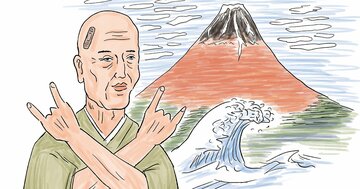そして、本屋は、そうして作った本を小売りするほか、町中に多数あった「貸本屋」に卸(おろ)していました。そのため、「問屋」と呼ばれていたのです。
そうした地本問屋の活動が、最も活発かつ精彩を放っていたのは、18世紀後半から19世紀半ばにかけての約1世紀間です。その時代の前半、蔦重が経営する耕書堂は、業界トップクラスの座にあったのです。
江戸の読者層は新しい趣味「読書」をどうやって楽しんだか?
江戸時代の日本は、同時代としては、世界的に見ても、出版が盛んな国でした。とりわけ、江戸後期には、おびただしい数の書物が出版されました。
本が大量に作られた背景には、江戸時代の識字率の高さがあります。江戸後期には、男女合わせて、5割程度の人が読み書きができたと推定されています。当時、ヨーロッパ人の識字率が10~20%だったとみられますから、世界水準からみて、それはひじょうに高い数字でした。幕末、日本を訪れた欧米人は、庶民にも字が読める者が多いことに驚いています。
その高い識字率を生み出し、ささえたのは、全国各地にあった「寺子屋」でした。
寺子屋は中世の寺院ではじまったので、その名があるのですが、江戸時代には寺院と離れて、町中や農村に多数の寺子屋が生まれます。親は、子供が8~9歳ぐらいになると、3~4年ほど寺子屋に通わせ、読み書きそろばんを学ばせたのです。そうして識字率が高まり、江戸後期には、読書が庶民にとっても身近な娯楽となったのです。
ただ、身近とはいえ、当時は紙の値段が高かった分、本も高価なものでした。今の金額にして1冊数千円はし、たとえば『好色一代男』は8巻揃いで、今の金額にして5万円はしました。そうそう買えるものではなかったので、侍も庶民も貸本屋を利用しました。多少富裕な人も、本を読むときには、貸本屋を利用するのが一般的だったのです。
江戸時代の貸本屋は、店舗でお客を待つスタイルではなく、本を背負って持ち歩く行商で行われていました。貸本屋は、お客の好みに合わせて、人情物、実録物、戦記物など、さまざまなジャンルの本をかついで、お客のもとに届けていたのです。