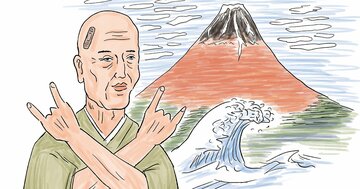そうして、木版印刷本を商う「本屋」が登場するのですが、本屋が最初に登場したのは、江戸ではなく、京都でした。江戸初期の文化の中心地は、あくまで上方(かみがた)にあったのです。
江戸初期、京都の本屋がおもに扱ったのは、「書籍」と総称された硬い本でした。歴史書、仏書・漢籍、医学書などを中心に商っていたのです。そうした硬い本をおもに扱う本屋は「書物問屋(しょもつどいや)」と呼ばれました。次いで、出版業は大坂に広まり、かるい読み物である「浮世草子」が人気を博します。その代表作が、井原西鶴の『好色一代男』(1682年)です。
江戸でつくられた本を扱う「地本問屋」の急増
1700年代に入ると、江戸にも本屋が多数現れ、1721年には、江戸市中に47軒の本屋があったと記録されています。ただし、その半数以上は、上方からの出店(でみせ)でした。そのころ、京都には200軒にのぼる本屋があったのです。
蔦重の生まれた1750年ごろから、江戸では、書物問屋のほか、やわらかい本を扱う「地本問屋」が急増します。「地本」とは「地元(江戸)で作られた本」という意味。上方で作られて運ばれてきたものではなく、江戸で作られた地産地消の本というわけです。一方、上方で作られ、上方の出店で売られる本は「下(くだ)り本」と呼ばれました。
地本問屋が扱ったのは、草双紙、人情本、洒落本(しゃれぼん)、黄表紙、浮世絵といった娯楽本のジャンルでした。蔦重が経営した耕書堂は、むろん地本問屋のひとつです。
書物問屋も地本問屋も、現在の本屋とは違って、出版社を兼ねていました。現代の出版業は、出版社、取次(問屋)、書店によって分業化されていますが、江戸の地本問屋はそれらの業務を一手に引き受けていたのです。
地本問屋は、自ら本を企画し、著者らに原稿・絵を発注し、編集、印刷、製本を行い、そして、版木を有することから、「版元」とも呼ばれました。なお、当時、版木は売り買いされ、版木を買ったものは、印刷・販売することができました。この版元という言葉、今の出版界にも残っていて、「その本、版元はどこ?」などと使われています。