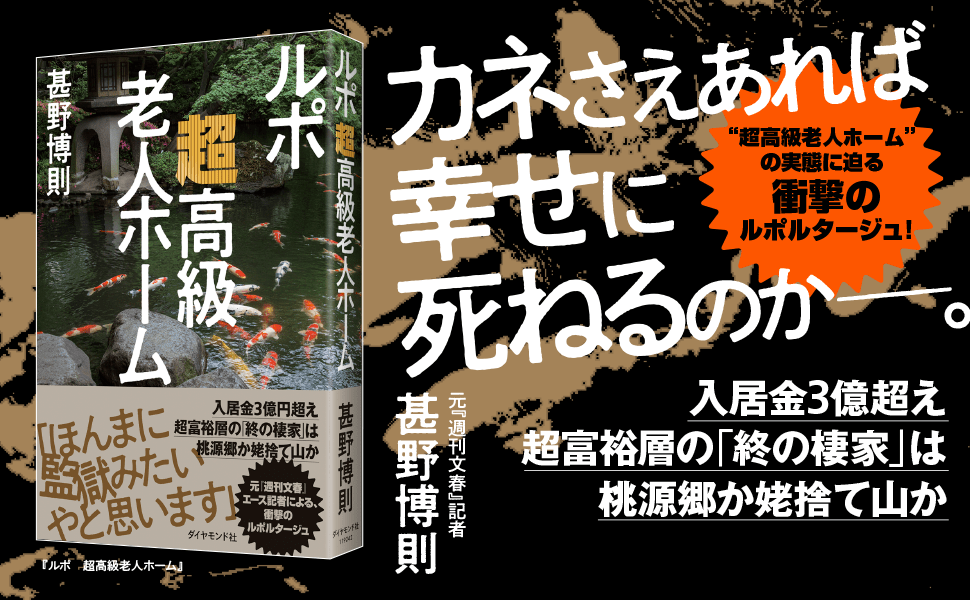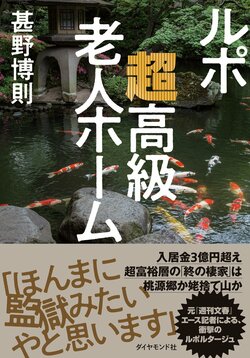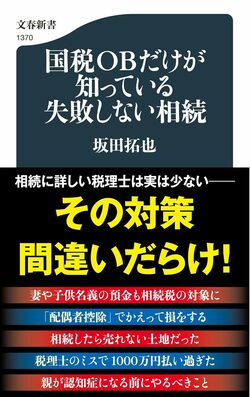誰にしてる?
生命保険の「受取人」
事前準備が必要で効果の高い相続税対策の2つ目は「生命保険への加入」だ。被相続人が生命保険に加入して相続人を受取人にした時は、受け取った保険金のうち1人500万円まで相続税が非課税になる特例だ。
被相続人(亡くなる人)となる父親が、母親と長男・長女の3人を受取人にして各500万円の生命保険に入れば、課税対象額を1500万円減らせるため効果がかなり大きい。
「ただし父親が母親を受取人にしていた場合、母親が受け取った保険金は当然母親の財産となります。このため、母親が亡くなり、相続が発生した時には長男・長女の課税額が増える可能性があるのです。
父親は母親を受取人にして、母親は父親を受取人にして、生命保険への加入を続けている人がいますが、75歳を過ぎた親は受取人を子どもに変更すべきです。
遺産は分割に合意しなければ分配されませんが、保険金は死亡後すぐに支払われるため、亡くなった被相続人の葬儀費用に当てられるなどのメリットもあります。」(杉江税理士)
どう切り出す?
「親子の相続」
相続は“争続”と呼ばれるほど争いが起きるものだ。
相続争いを回避するためには、家族が事前に話し合い、財産の分配等を決めておくことが大切となる。
杉江税理士は順序として、相続税の概算額を算出した後に話し合うべきだと言う。
「親の気持ちだけで財産の分配を決めてはいけません。親が亡くなった途端に争いが起きる原因となるからです。遺言書を作成しておくことは有効ですが、親は自分の思いを子どもたちに伝え、子どもたち全員が合意した上で遺言書を作成すべきです。
分割の難しい不動産が財産の大部分となっている場合は分配に悩みますが、後のトラブルの元になる『共有』は避けるべきです。
家族の形は様々であり、相続の形も千差万別。AI(人工知能)では答えを出せませんし、よく話し合うことです」(杉江税理士)
問題は、相続の話を誰が切り出すかということだ。杉江税理士はこう続ける。
「親が率先して話すことが理想です。人の死を前提とするだけに、子どもから切り出せば親が感情を害し、揉めてしまうことは少なくありません」
「財産はどう分ける?」と切り出すより、「相続税はいくらぐらいになるかな?」と切り出す方が、抵抗は少ないのかもしれない。
大分市出身。大学在学中に1992年「サンパウロ新聞」(サンパウロ)、卒業後1997年から2004年「財界展望」編集記者、2008年から2018年まで「週刊文春」記者、現在はフリーランスのライターとしてマネー、経済分野を中心に幅広く執筆を行う。著書に『国税OBだけが知っている失敗しない相続』(文春新書)、取材・構成『日本人の給料』(宝島社新書)などがある。