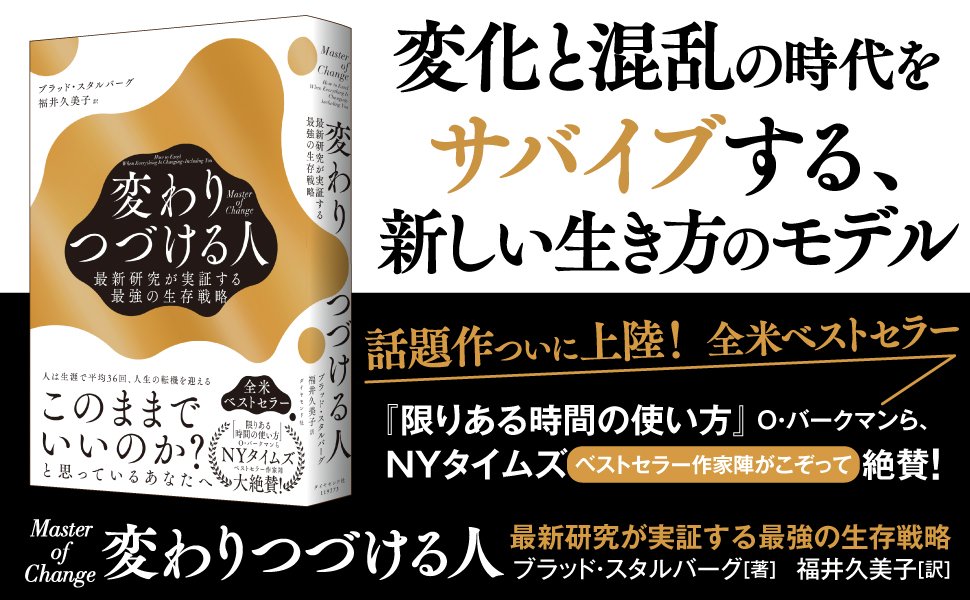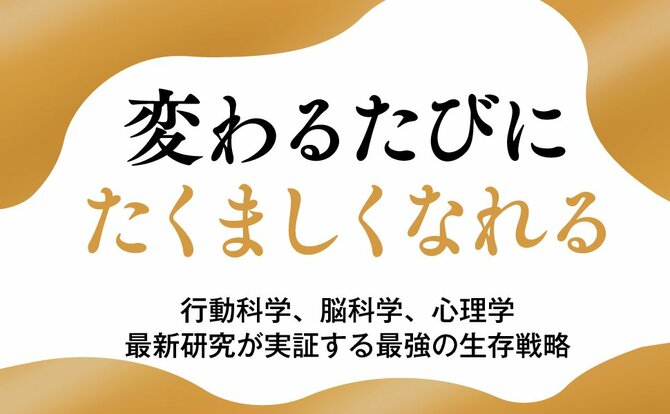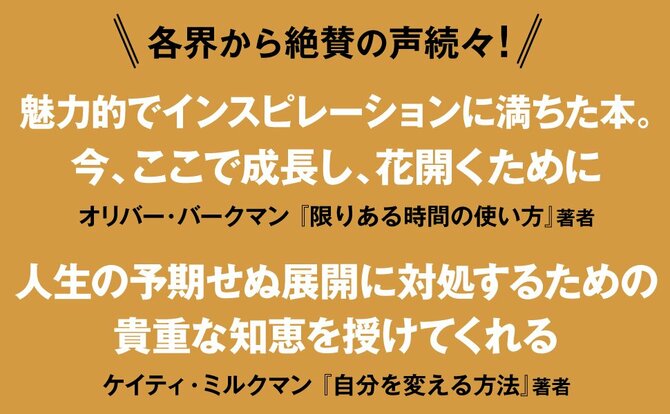アメリカでベストセラーとなり、多くの絶賛を集めた『Master of Change 変わりつづける人:最新研究が実証する最強の生存戦略』がついに日本に上陸した。著者のブラッド・スタルバーグはマッキンゼー出身で、ウェルビーイング研究の第一人者。この本が指摘するのは、人生を消耗させる「思考の癖」だ。この記事では、本書の内容をベースに「感情に振り回されず、意識的な行動を取るコツ」を紹介する。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
人の行動は2種類――「反応」と「対応」
私たちは日々、さまざまな感情に振り回されている。
仕事のプレッシャー、人間関係のストレス、予期せぬ出来事によって、怒りや焦り、不安といった感情が湧き上がることは避けられない。
日々それらの感情に対してどのように向き合うかで、その人の生き方は大きく変わってくる。
ブラッド・スタルバーグは『Master of Change 変わりつづける人:最新研究が実証する最強の生存戦略』の中で、「反応」と「自発的な対応」という2つの概念を対比している。
反応とは、よく考えもせずについ早まって出てしまう行動だ。反応すると、型どおりの行動に出やすい。他方で、自発的な対応は計算したうえで意図的に行動することだ。
(P.331)
たとえば、コンビニのレジで前の人の会計が長引いているのを見て苛立ち、ため息をついたり、無意識に足を踏み鳴らしたりしてしまう。職場で同僚に仕事の進め方を指摘され、すぐに感情的になり反論してしまう。これらは「反応」にあたる。
一方で、こうした状況に直面しても感情のままに行動せず、冷静に受け止めて適切な行動を取ることが「自発的な対応」だ。
つい反応したくなる衝動を抑え込むには?
スタルバーグは、神経科学者のパンクセップらの研究を引用しながら、人間は脳の構造上、「主体的な対応」と「感情的な反応」を同時に行えないことを説明している。
脳には、主体的な計画や行動を司る「ワクワク回路(SEEKING)」と、怒りの感情を司る「怒り回路(RAGE)」と呼ばれる領域があり、片方が活性化しているともう片方は抑制される関係にある。
パンクセップとその同僚たちが最先端の神経科学を使って明らかにしたことは、ほとんどの人が身に覚えのあることだろう。計画を立てたり、難題に注意深く取り組んだりしながら、かんかんに腹を立てて激怒することはほぼ不可能だ。脳は主体的な対応と反応を同時におこなうことができないため、脳の機能が前者に取り組む間は、後者のような怒りのスパイラルに陥らないのだ。
(P.238)
つまり、自発的な対応を取る人は、ワクワク回路が活性化しているため、次の行動も主体的に対応しやすくなり、好循環が生まれるのだ。
反応し続けることの健康リスク
反対に、反応が習慣化すると、自発的な対応が取りにくくなる。反応し続けることで、人は精神的に疲弊していく。
怒り、憤怒、パニックといった反応的な感情を解決しないまま長期間放置すると、人は燃え尽き症候群、慢性疲労、臨床的抑うつ状態に陥りやすくなる。
(P.238)
瞑想のすごい効果
できるだけ「主体的な対応」の時間を増やし、「反応」の時間を減らしたい。では、どのようにすれば反応ではなく「自発的な対応」がとれるようになるのか。
スタルバーグが提示する答えのひとつが、瞑想だ。
反応するのではなく、主体的に対応できるようになるには瞑想も役に立つ。欧米人が抱く一般的なイメージとは異なり、瞑想は心をリラックスさせて陶酔感を味わうためのものではない。むしろ、さまざまな思考や感情や感覚に反応することなく、傍観することを学ぶためのものだ。
(P.256)
たとえば、瞑想中にイライラや焦りを感じた時、「この感情を消したい」と思うのではなく、「今、自分はイライラしているな」と観察するだけにする。
このような訓練を続けることで、瞑想中でなくとも、日常生活の中で感情の波に飲み込まれることなく、それを冷静に見つめる力が養われるとされている。激しい感情が湧き上がった時に、すぐに反応せず、一歩引いて考える余裕を持てるようになる。
※本稿は『Master of Change 変わりつづける人:最新研究が実証する最強の生存戦略』の内容を一部抜粋・編集したものです。