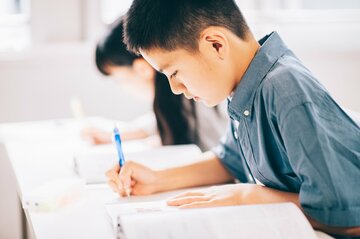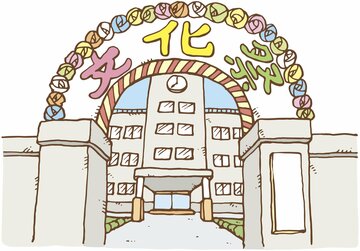写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
2025年の首都圏中学受験は、受験者数・受験率ともに大きな変化はなかったものの、最難関校の一部では受験者減少の動きが見られた。その背景には、志望校選びの新たな傾向や、受験を取り巻く環境の変化が関係しているようだ。一方で、中学受験のあり方そのものも少しずつ変わりつつある。連載第14回では、大手塾の分析とは異なる視点から今年の入試を振り返り、26年入試に向けて注目すべきポイントを探る。(国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー 渋田隆之)
「最難関校」の受験者数
減少の理由は?
毎年2月末から3月初旬にかけて、大手塾各社で中学受験の入試報告会が実施されます。2025年の入試は、どの塾も首都圏の中学受験者数は約5万2300名(24年は5万2400名)、受験率は18.1%(同18.3%)〈いずれも首都圏模試センター調べ〉と、前年比横ばいか微減という分析でした。今回は、大手塾では得られない視点からの入試分析と26年度入試に向けての留意事項をお伝えしたいと思います。
今年、受験者数を増やしたことで注目を集めたのは聖光学院(神奈川)です。この学校は、昨年度の東大合格数が100名を超えたことと、入試日程が2月2日と4日という同じくらいの偏差値帯の学校と併願しやすい日程でもあることから受験者数を増やしました。
しかし、首都圏の他の最難関私立中学校の多くは受験者数を減らしました。最難関校の中には「校則がほとんどない」と言われるなど自由な校風の学校が多いものですが、それよりも面倒見の良さをアピールしている学校の人気が高まっているように思います。
また、昨今の中学受験関連情報は「受験率最高!」など過熱感を訴えるものが多かったため、それらを目にした家庭が“安全志向”になったとも考えられます。
また、最難関校の先生の一部から「出願者数は例年と変わらないものの当日の欠席者数が多かった」という話を聞きました。これは、1月の受験結果を見て、より合格可能性の高い学校へ切り替える人が多かったことの現れだと考察できます。
さまざまな理由の中で、私が受験生減少の一番の要因となったのではないか?と考えているのは「人気の分散」です。20年前と比べると、同じような偏差値帯の中に魅力のある学校が増えたため、価値観の多様化とともに学校の選択肢は広がりました。
「偏差値にとらわれない学校選びをしましょう」という教育関係者がいますが、実際には受験する家庭はもっと賢く、もっとシビアに学校選択をしているというのが私の実感です。一般的な教育関係者よりも、生徒も保護者の方がシビアさも含め「日本社会の現実」をより理解していると思うからです。
では、受験者数が横ばいか微減であり、大きく減らなかった背景には何があるのでしょうか。