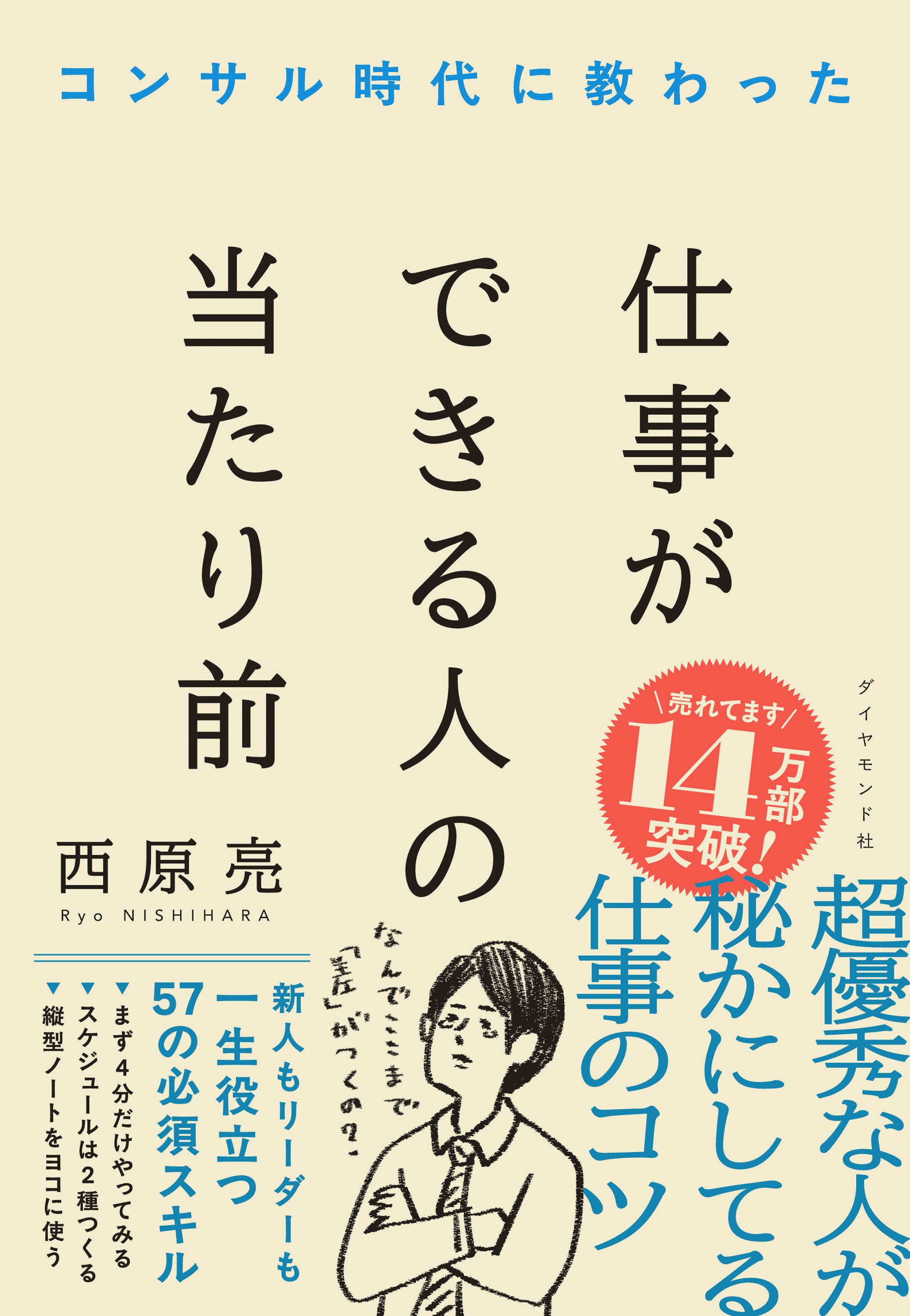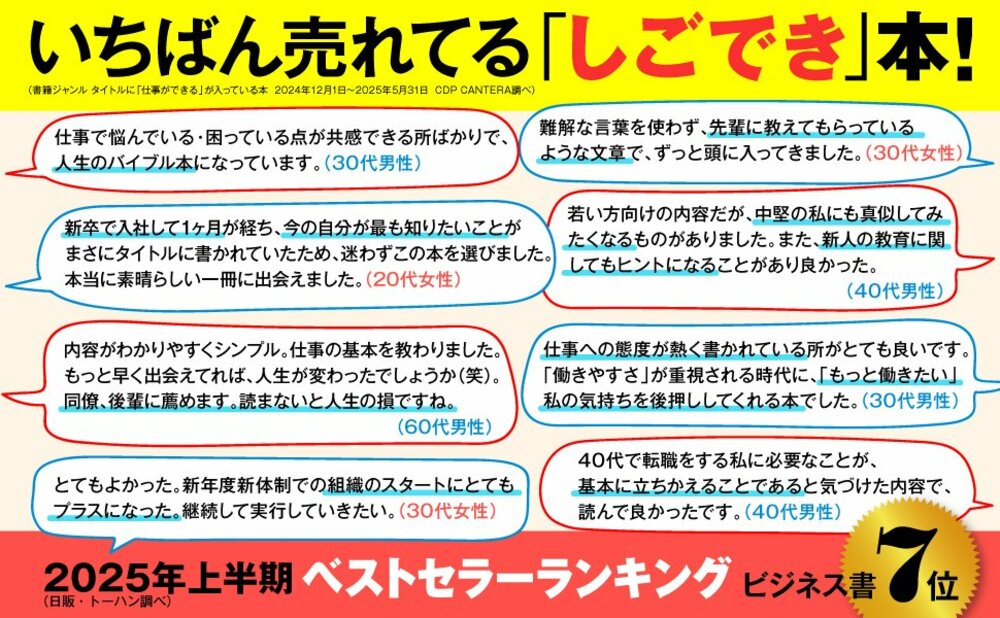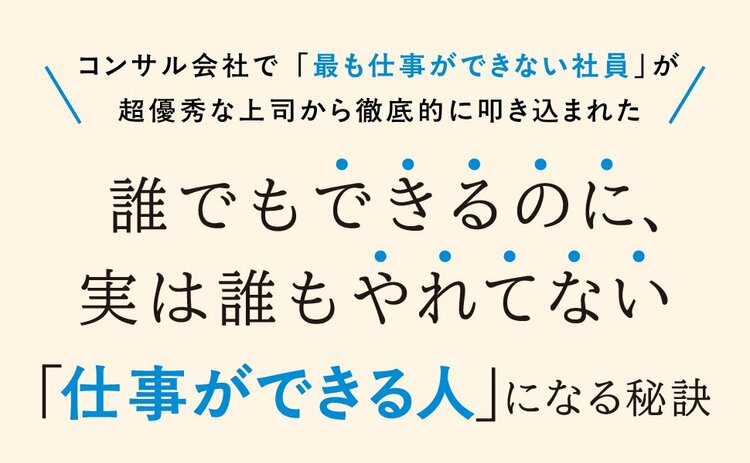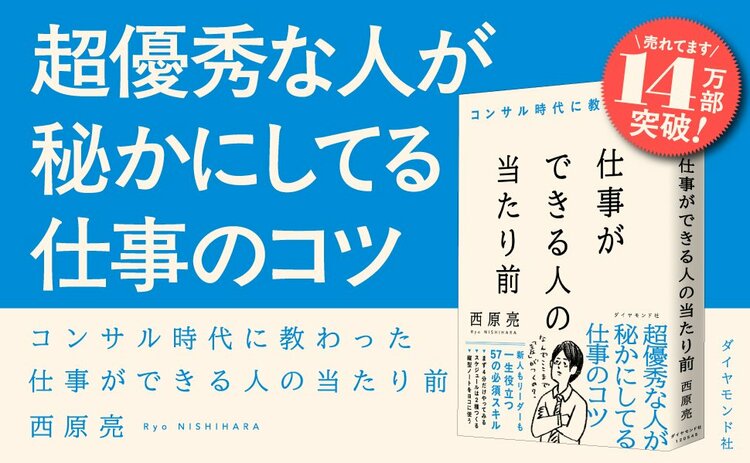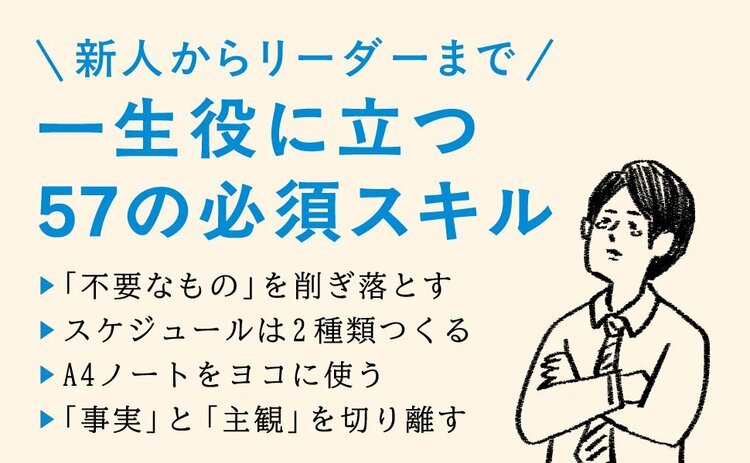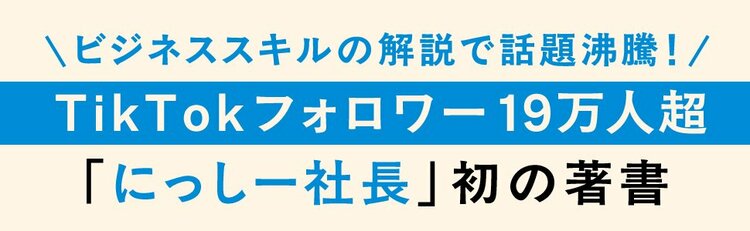「頑張っているのに、結果がついてこない」「必死に仕事をしても締め切りに間に合わない」同僚は次々と仕事を片付け、成果を出し、上司にも信頼されているのに、「なんでこんなに差がつくんだ……」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが20万人を超え『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている仕事のコツ」を本記事で紹介します。(構成/ダイヤモンド社・林拓馬)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
使える「メモの取り方」3ステップ
仕事をする上で、メモを取る機会は非常に多くなります。
しかし、ここに一つ大きな罠があります。
それは、ほとんどの人が「メモを取った」という事実に満足してしまい、結局そのメモが活かされないまま終わってしまうという点です。
実際には、「何を書いたのか分からない」「どこに書いたのか分からない」「見返すことができない」といった状況になりがちで、せっかく取ったメモが結果的に何の役にも立たなくなってしまうのです。
つまり、なんとなくメモを取って「仕事している風」にはなるのですが、そのメモが実際の業務に結びついていないというのが問題です。
本来、メモはその後に自分がアクションを起こすために取るものです。
メモによって具体的な行動を導き出す、これが最も大切なポイントです。
したがって、振り返ることができないメモには意味がありません。
では、明日から実践できる「使えるメモの取り方」について、具体的に説明していきます。
たとえば、上司とのやり取りの中で「法人営業資料にイメージ図を差し込んで、サービス内容を分かりやすくする」といった指示を受けたとしましょう。
この内容をそのままメモに書いたとします。
しかし、これだけでは具体的な行動にはつながらず、結局何も実行できないまま終わってしまいます。
経験や知識が豊富な人であれば、こうした抽象的な指示を聞いた瞬間に、どういったイメージで、どのようにサービス内容を変えればいいのかが分かるため、具体的なアクションにつなげることができます。
しかし、ほとんどの人にとっては、それだけでは十分に理解できないのが現実です。
そこで大切になるのが、次の3ステップです。
1つ目のステップは、「まずは一旦、そのままメモを取る」ということです。
2つ目のステップでは、そのメモの中にある不明点を1つずつ上司に確認していきます。
たとえば「イメージって、どういうイメージですか?」「差し込むとは、どこに差し込むのでしょうか?」「サービス内容とは、具体的に何を変えればよいのですか?」「『分かりやすくする』とは、どういう状態を指しているのですか?」といった具体的な質問を投げかけていくことが重要です。
3つ目のステップでは、それらの確認結果をもとに「自分の言葉でメモを書き直す」ことが必要です。
このプロセスを経ると、最終的に次のようなメモに仕上がります。
「個人営業のXX社向けの資料を3ページ目に、ポスト削減の事例図を差し込み、導入後の具体的効果を数字で入れる」
ここまで内容が具体的になれば、アクションが非常に取りやすくなります。
同じ指示でも、こうして一度しっかりメモを取り、不明点を明確にし、それを自分の言葉で整理し直すことで、まったく異なる質のメモになります。
このようなメモの取り方を実践すれば、仕事に迷わず取り組むことができるようになります。ぜひ実践してみてください。
(本記事は『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者、西原亮氏が特別に書き下ろしたものです)