マイクロソフトCEOのサティア・ナデラやグーグルCEOのサンダー・ピチャイがインド系アメリカ人であることはよく知られているが、それだけでなく、近年のアメリカではインド系のイデオローグやインフルエンサーの活躍が目立つようになった。
1980年生まれのバーラジ・スリニヴァサン(Balaji Srinivasan)もその一人で、ベンチャー企業の創業者からベンチャーキャピタリストになり、2022年に“The Network State; How To Start a New Country(『ネットワーク国家 新しい国をどのように創業するか』)”を自費出版してシリコンバレーのテクノ・リバタリアンたちから熱烈な支持を受けた。
インド系のソートリーダー(thought leader)に共通するのは、シリコンバレーで成功したエリートであることと、アメリカを「支配」しているリベラルな価値観(ウォークやキャンセルカルチャー)への反発だ。
これまでアメリカのリベラルは、BLM(Black Lives Matter)などに対する保守派からの批判を「人種主義(レイシズム)」として黙らせてきた。だがインド系のイデオローグは、自身が有色人種(POC=People of Color)であることから、白人とちがって「レイシスト」のレッテルを貼られることはない。これが、インド系アメリカ人の成功者が「アンチ・リベラル」の先頭に立つようになった背景だろう。
そこで今回は、スリニヴァサンの「ネットワーク国家」がどのような構想なのかを見てみよう。なお、本書はAmazonでも販売されているが、本人のサイト(https://thenetworkstate.com/)に全文がアップされている。
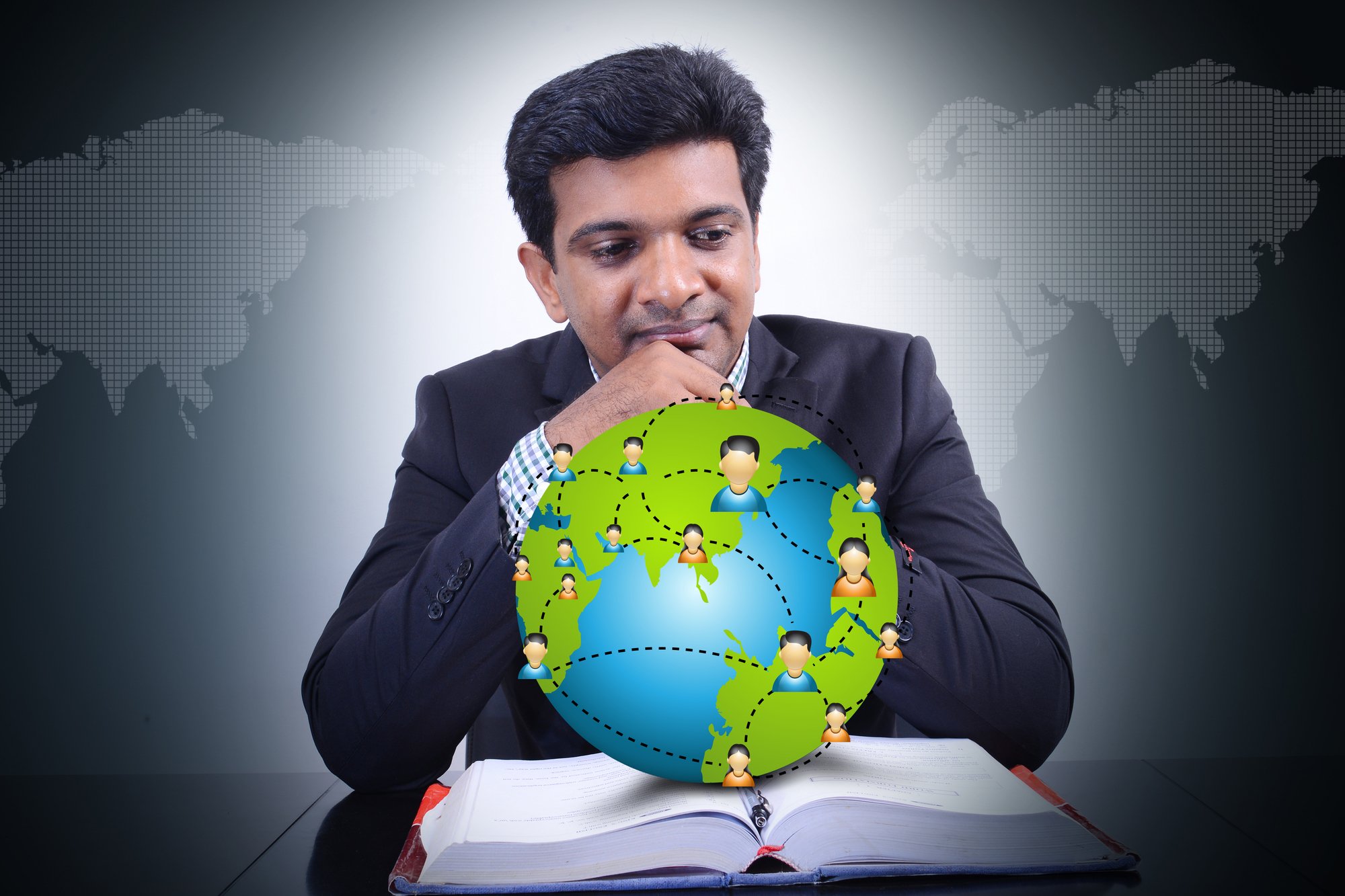 Photo/cuteimage / PIXTA(ピクスタ)
Photo/cuteimage / PIXTA(ピクスタ)
テクノ・リバタリアンの代表であるピーター・ティールはシースティング・プロジェクトこそがリバタリアンの目標になると論じた
テクノ・リバタリアンの代表であるピーター・ティールは、2009年にウェブメディアに発表した“The Education of a Libertarian(あるリバタリアンが学んだこと)”で、「自由(Liberty)と民主政(Democracy)が両立するとは考えていない」と述べた。リバタリアンは「自由」という聖杯を手放すことはできないのだから、残された道は愚民政となった民主政を拒絶し、「自由な共同体」を最初からつくりあげることしかない。
この論文でティールは、(1)サイバースペース、(2)アウタースペース(宇宙)、(3)シーステディング(海上自治都市)の3つの候補を挙げ、サイバースペースは個人の自由の領域を拡張したものの、それはしょせんヴァーチャルなものでしかなく、アウタースペース(イーロン・マスクが進める火星移住計画)のフロンティアはリアルな自由を実現できるかもしれないが、それにはまだ時間がかかるとして、パトリ・フリードマン(経済学者ミルトン・フリードマンの孫)が手掛けるシーステディング・プロジェクト(どこの国にも属さない公海上に巨大な船を浮かべ「独立自由国家」を樹立する)こそがリバタリアンの目標になると論じた。
だがこの論文から何年たっても「リバタリアンのための自由国家」は建設の兆しすらなく、ティールは2014年時点で、これ(シーステディング)は「ごくささやかなプロジェクト」であり、実現は「はるか遠い将来になるでしょう」と述べざるを得なくなった。こうしてティールは、現実の政治に介入してテクノロジーを“加速”させるために、16年の大統領選挙でトランプを支持するという“逆張り”をしたのだろう。
これに対してスリニヴァサンは、新しい国を立ち上げる方法として、ティールの三択に「選挙」「革命」「戦争」「マイクロ国家」の4つを加える。まずはその評価を簡単に見てみよう。
(1)選挙:体制を変える手段としてもっとも広く議論されているが、なんの成果もあげていない。
(2)革命:新しい政府を生み出すことはできるが、膨大な流血と犠牲をともない、ロシア革命やポルポトの革命のように、その結果はしばしば悲惨なものになる。
(3)戦争:戦争に勝利すれば、敗者の国に新しい政府をつくることができる。ロシアによるウクライナ侵攻はこれを目的としたが、国際社会の強い反発を受け、双方の犠牲に対して得るものはほとんどない。
(4)マイクロ国家(ミクロネーション):イギリスの沖合(公海上)に遺棄された第二次世界大戦時代の要塞に移住し、「独立宣言」したシーランド公国が有名。興味深い試みではあるものの、マイクロ国家は(その名のとおり)規模が小さすぎて社会的影響力がない(どの国からも相手にされない)。
(5)海上自治都市:実現可能性はあるものの、具体的なプロジェクトとして進んでいるわけではない。人間が長期にわたってクルーズ船で暮らせるかどうかもわからない。
(6)宇宙:現時点では、技術的に実現不可能と考えられている。
(7)ネットワーク国家:「新しい国」をつくる7つの選択肢のうち6つが否定されたのだから、残された唯一の選択肢であるネットワーク国家の可能性を追求すべきだ。
ネットワーク国家は、ユーザーが好きなオンラインコミュニティを選ぶように、国民が自分の価値観に合った国家を選択することができる
「ネットワーク国家」とは何か? それはたんにオンラインで仲間を集め、一方的に「国家」を名乗って「独立」を宣言することではない。これだと、ソーシャルゲーム(ソシャゲ)やネットワークゲーム(ネトゲ)のユーザーのコミュニティと変わらなくなってしまう。
スリニヴァサンは、ネットワーク国家を「世界中でクラウドファンディングによって領土を獲得し、最終的には既存の国家から外交的承認を得る、集団的行動能力を備えた高度に連携したオンラインコミュニティ」と定義する。この「国家」の基盤になるのが暗号(クリプト)とブロックチェーン(スマートコントラクト)で、独自の暗号経済と暗号歴史をもつ。
といっても、これではなんのことかわからないだろうから、私が理解できた範囲で順に説明していこう。
ネットワーク国家の大きな特徴は、たんなるオンラインコミュニティではなく、物理的な「領土」をもつことだ。この領土は、人里離れた土地のこともあるが、住宅地の一戸建てや都市部のマンションの一室でもいい。それぞれの国家の「国民」は、こうした領土を自分の財産で購入することもできるし、クラウドファンディングで購入資金を募ってもいい。
この構想が実現すると、住宅地にはそれぞれのネットワーク国家の旗が掲げられ、大規模なマンションには、いろいろな国の国旗がドアに貼られることになる。すなわち、隣近所に住んでいても、ちがう国の国民になるのだ(現実的には、ひとつの区画や一棟のマンションに同じ「国民」が集まることになるだろう)。
これを荒唐無稽と感じるかもしれないが、アメリカの現状を考えればそうともいえない。2016年以来の3度の大統領選で明らかになったように、アメリカでは共和党支持者と民主党支持者が政治イデオロギーで対立し、心の底から憎み合っている。それにもかかわらずリベラルは、同じ「アメリカ人」として、やることなすことすべて気に食わない大統領の下で生きていくことを「強要」されているのだ。
それに対してSNSでは、好きなひととつながり、嫌いな人間をブロックすることが簡単にできる。だとしたら、「なぜ同じことが現実世界でできないのか」というのは当然の疑問だろう。そうしたひとびと(ユーザー)の要望に応えるもっとも効果的な方法が、ネットワーク国家なのだ。
アメリカ社会が分断され、アナーキーに陥るのを防ぐには、保守派とリベラルが住宅地によって住み分け、ちがう国の「国民」として、相手の政治的主張や文化的態度に煩わされることなく、自分の同類たちと楽しく暮らしていけるようにすればいい。
近代国家は領土によって国民を規定するため、わたしたちは「日本人」や「アメリカ人」を選択して生まれてくることはできない。それに対してネットワーク国家は、ユーザーが好きなオンラインコミュニティを選ぶように、国民が自分の価値観に合った国家を選択することができる。この発想の逆転(コロンブスの卵)がスリニヴァサンの提案の最大の魅力だろう。







