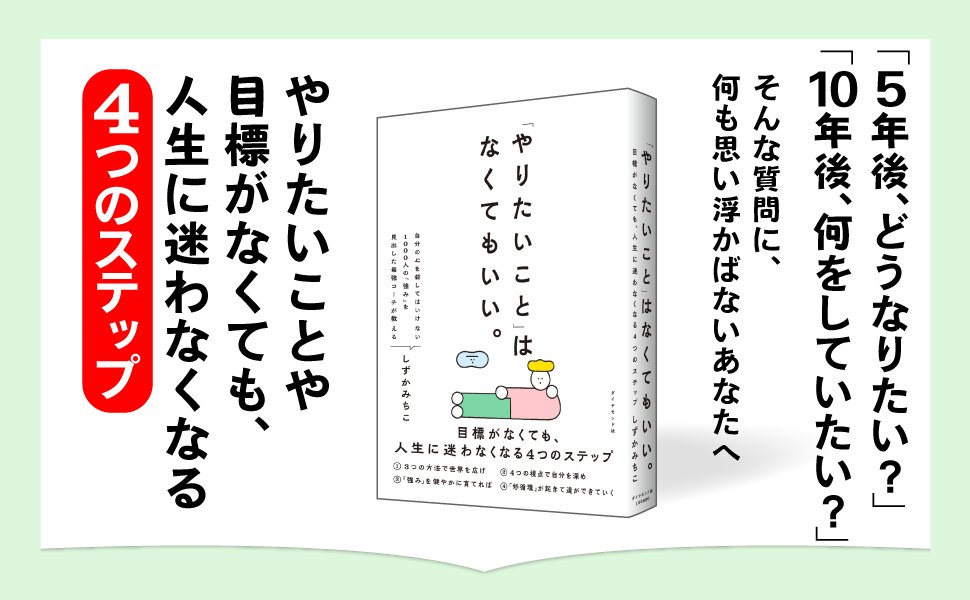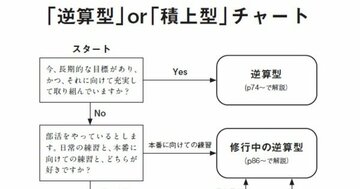社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
自分と同じ場所にいる人の、違う価値観に気付くこと
本書では自分の道が見えてくるためのSTEP1は「世界を広げる」こと、その中でも「世の中の仕組みを知る」ことから始めると書きました。
さて、「世の中の仕組みを知る」ことが世界を広げるための「座学」だとしたら、次は実際に世界を広げるための「行動」をしていきます。
それが世界を「縦」と「横」に広げる挑戦です。
まず「縦」の挑戦について説明します。
これは、「自分と同じ場所にいる人でも、違う価値観を持っている」と知ることで視野を広げることです。
明らかに違う環境で育った人、例えば自分とは違う国で生まれ育った人と価値観が違うことはイメージしやすいのですが、同じ場所や環境にいる人でも、実は違う価値観や異なる考えを持っていることは見落としがちです。
同じ大学にいてもまったく想像もつかないこともある
私が最初にこのことを意識したのは、大学生の頃でした。
私は青森県の大学の出身なのですが、りんご台風と呼ばれる青森の農家に甚大な被害をもたらした台風の翌々年の入学だったこともあって、様々な経済的事情を抱えた学生、例えば兄弟で話し合った末に、自分だけ進学できたという学生もいました。
最初は「授業料が出せないなら、奨学金を借りればいいのに。生活費はアルバイトで稼ぐこともできるのに」と思ったのですが、その思考回路が「縦」の世界を知らないということだと気づいたのです。
彼らにとっては、奨学金やアルバイトで稼ぐことは大前提で、本当に問題なのは「家業の働き手」の頭数でした。
家が第一次産業を営んでいると、働き手の確保が重要となります。高校生の時点で既に立派な働き手として頭数に入っていた彼らは、働き手が減るという理由で家を離れることができなかったのです。授業料を借りることはできても、農業の働き手を雇うお金は足りません。
そういうギリギリの状況で進学することを選んだ彼らと、高校卒業後、すぐには就職したくないからと進学し、授業には出ず、サークルやバイトに勤しんでいた学生とでは、同じ場所にいても価値観は大きく違います。
どちらがいいとか悪いとかではなく、同じ場所にいる同じ年齢の学生であっても、そこにいる理由は様々あるということに気がついたのです。
幼い頃は、サラリーマンの息子ののび太と、町の商売人の息子のジャイアンと、セレブリッチなスネ夫が同じクラスにいたように、比較的、様々な環境の子と交わる機会があります。
ところがそこから年齢を重ねていくに従い、一緒にいる人は似た生活環境の人になりがちで、価値観も同じだと思い込みがちです。
しかし、同じ場所にいても、違う価値観を持つ人がいて、違うものが見えていることを頭の片隅に入れておかないと、思考が浅くなってしまいます。じわじわと広がる変化も見逃してしまいがちになります。
*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。