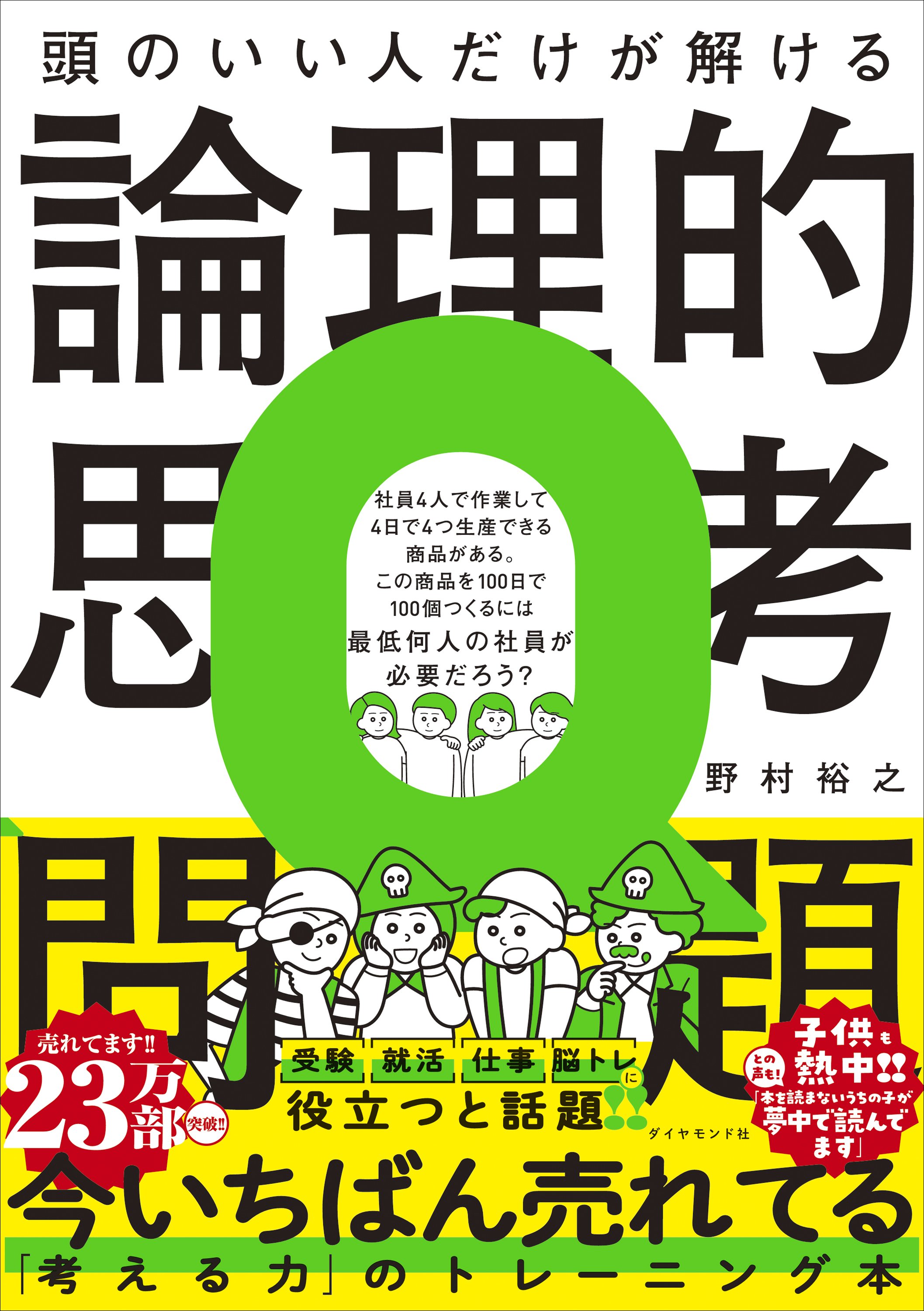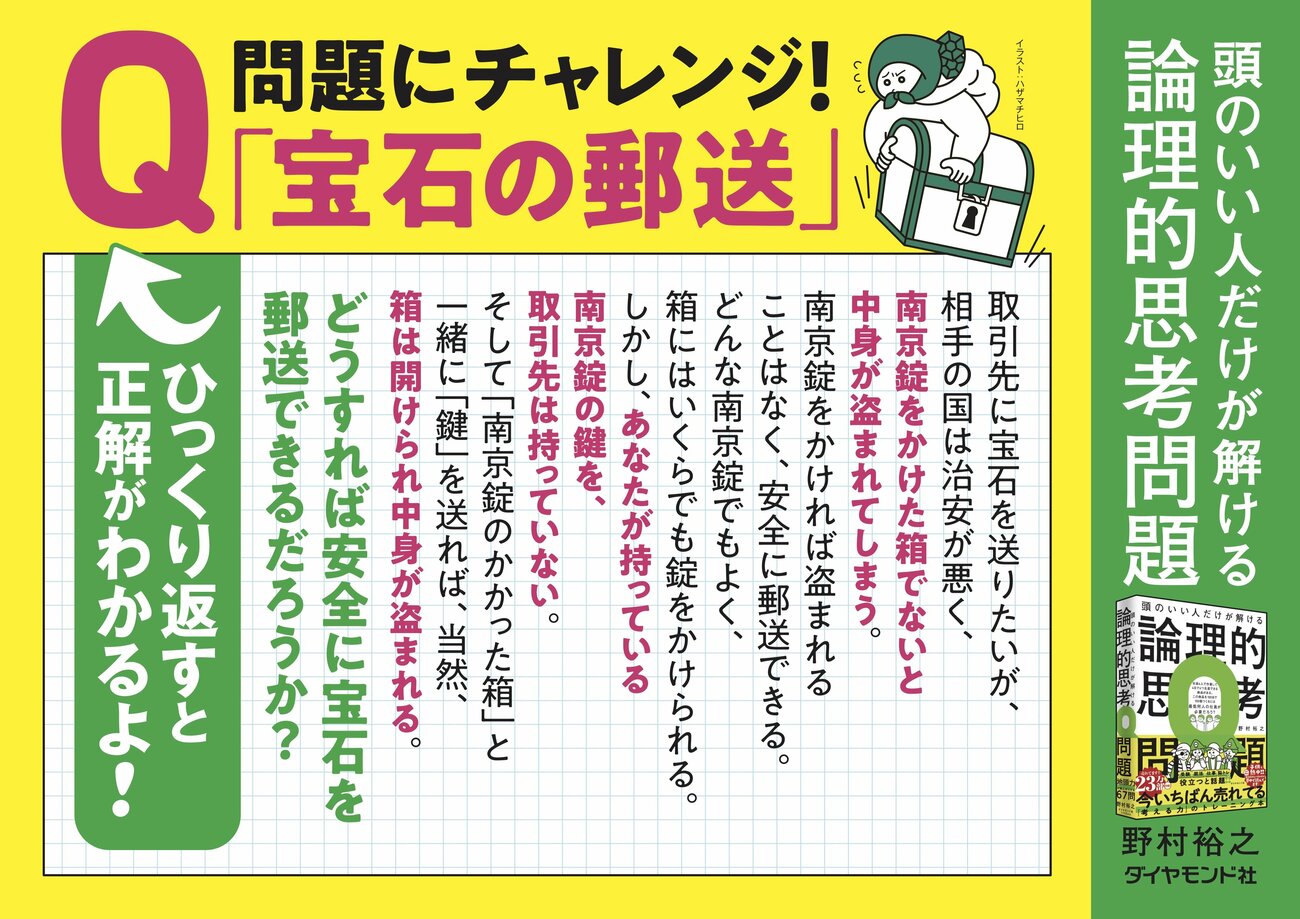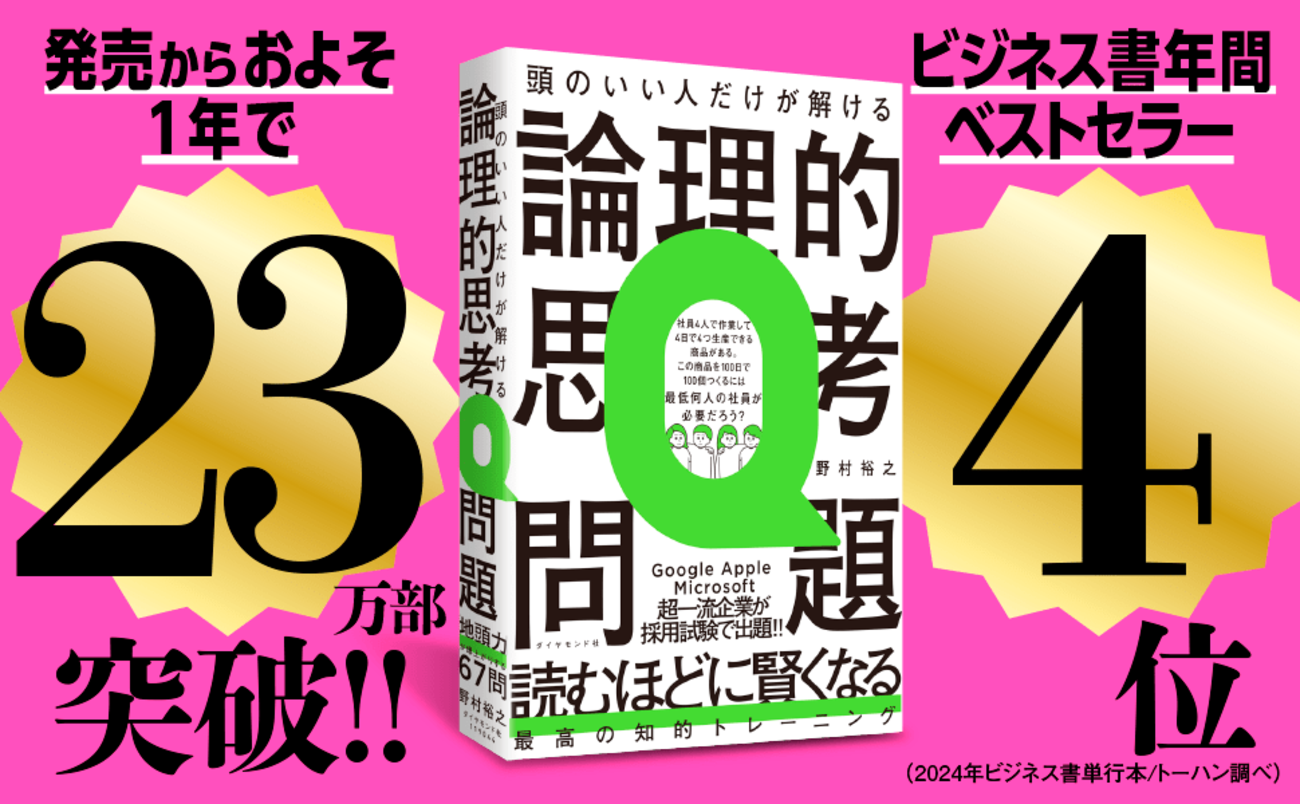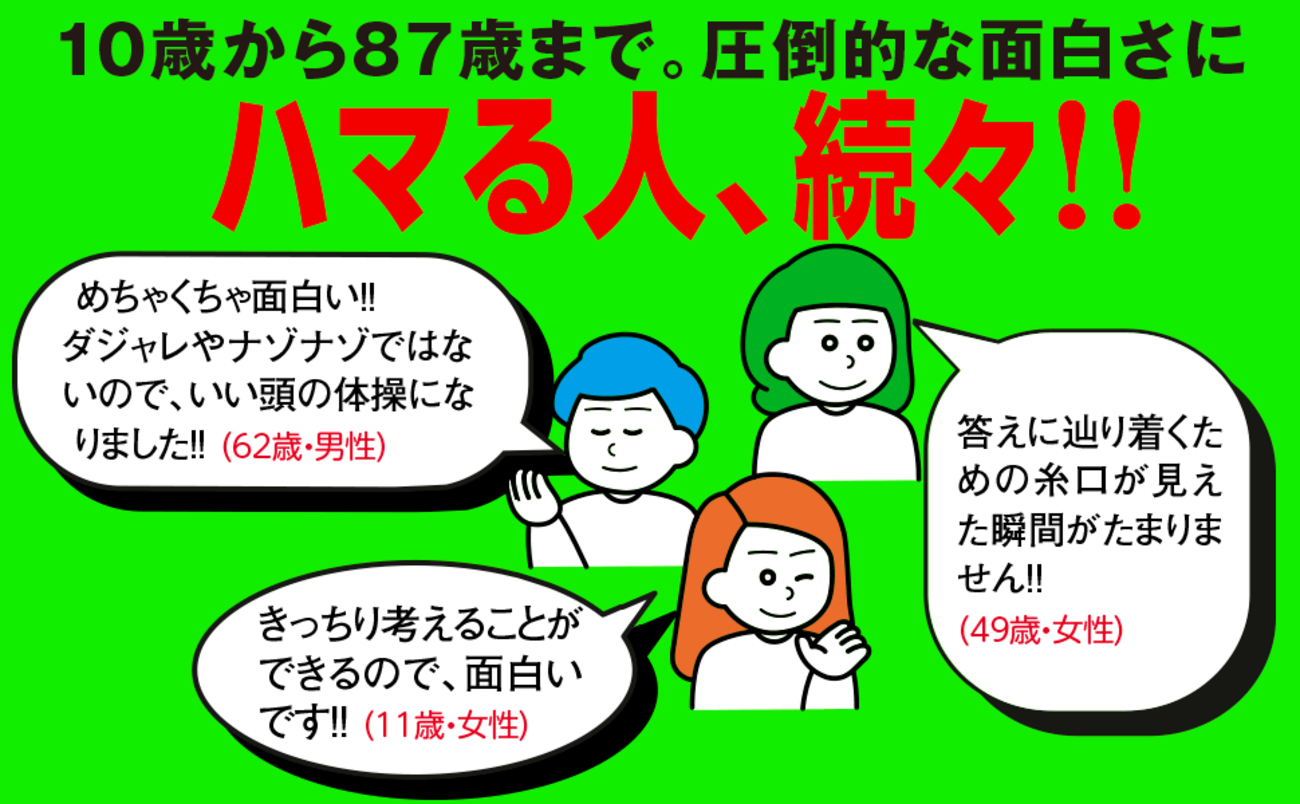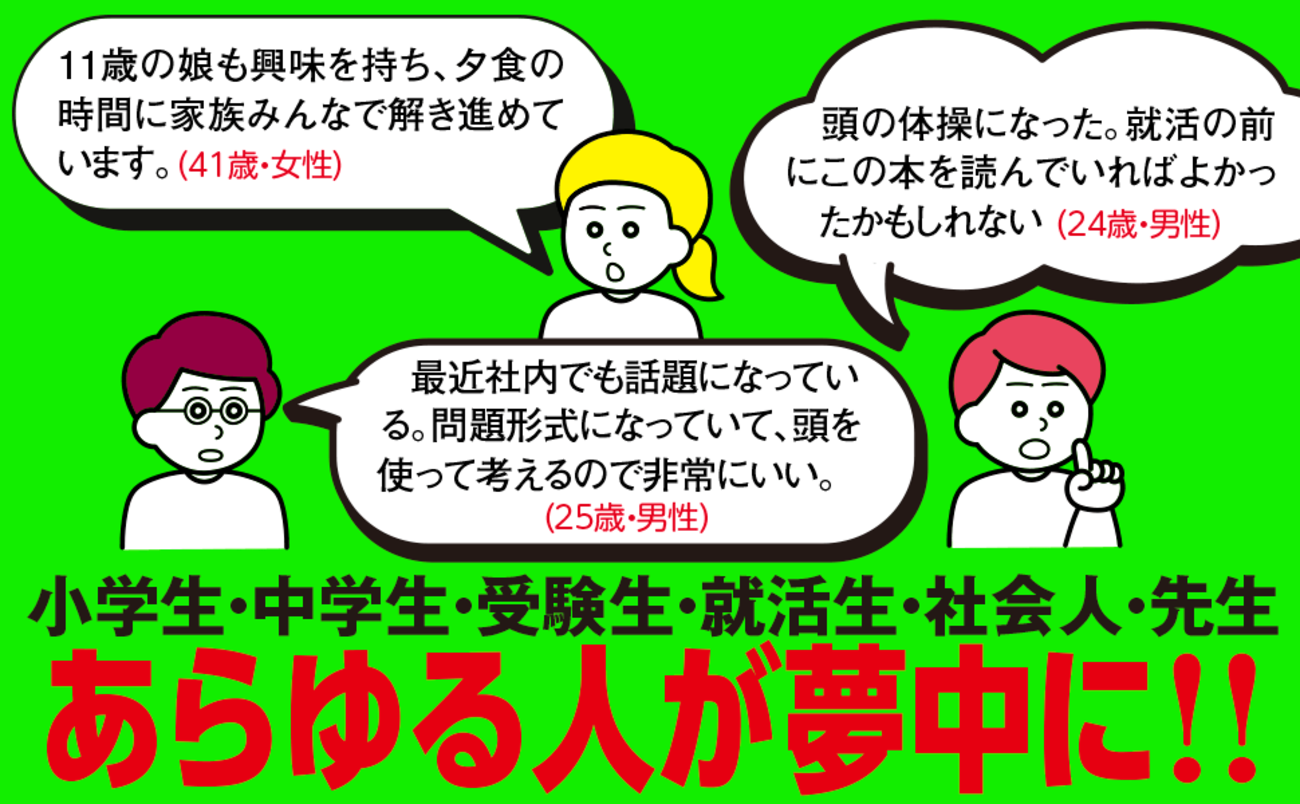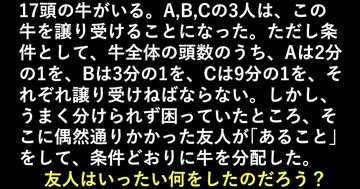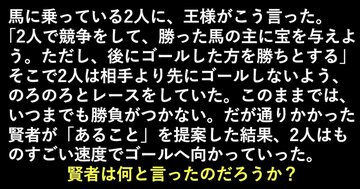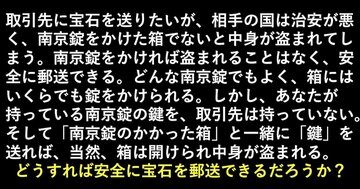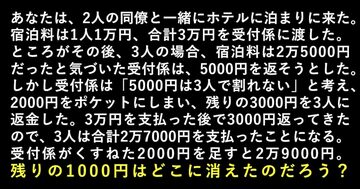以下が、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』で紹介している解説と回答です。
AIの回答は正しいのか、確認してみましょう。
意外と単純な状況
手を挙げるべきかどうか判断するには、2人がおかれた状況を把握する必要があります。
ありうる状況は次の3つのパターンです。
② 兄のみに泥がついている
③ あなたと兄の両方に泥がついている
どの状況におかれているのか、考えていきましょう。
「どちらか」の顔にしか泥がついていないとき
もし兄の顔に泥がついていないなら、あなたはこう考えるはずです。
これは兄から見た場合も同じです。
もし、あなたの顔に泥がついていないなら、兄は即座に「泥がついているのは自分だ」とわかります。
つまり、どちらか片方だけに泥がついている場合は、泥がついている人は、すぐに「泥がついているのは自分だ」とわかるわけです。
しかし、2人とも1回目の問いかけでは答えられなかった。
よってこの状況は、
のパターンしかありえません。
兄の顔には泥がついているけれど、「自分の顔に泥がついているかどうか」はわからなかったため、あなたは手を挙げられなかったのです。
兄はなぜ、手を挙げなかったのか
兄が手を挙げなかった理由を、兄の視点もふまえて考えてみるとこうなります。
「ということは、私の顔にも泥がついていて、私と同じように答えを出せなかったということだ」
こうして、あなたの顔には泥がついているとわかりました。
あなたは手を挙げるべき
ということで、AIの回答は正解でした。
この問題からの「学び」は?
この「泥のついた2人」の問題からは、日常の意思決定やチームでのコミュニケーションにも応用できる、論理的思考の本質や他者の視点に立った思考が学べます。
以下、この問題から「学べること」を紹介します。
①「自分が知らないこと」を他者の行動から推論できる
この問題では、「自分の顔が見えない=自分には直接の情報がない」状態です。しかし、相手が行動しなかったという「他者の判断」をもとに、自分の状態を論理的に推論することができます。
自分に見えない情報も、他者の反応を手がかりに考えられる。これは、ビジネスや交渉の場でも活きる考え方です。たとえば、「相手がこの提案に即答しなかった → 何かしら懸念材料がある」といった背景を読む力につながります。
②「沈黙」や「何もしないこと」も、重要な情報である
この問題では、1回目に誰も手を挙げなかったこと自体が、新たな情報として意味を持ちます。つまり、行動しないことが、情報を発信する手段になるというわけです。
「発言しない・動かない=情報がない」のではなく、逆に意味を持つことがある。これは、人間関係でも組織でも重要な視点です。たとえば、「なぜあの人はこの話題に対して何もコメントしなかったのか?」を考えることが、深い洞察につながる場合があります。
③「相手も考えている」という前提で考える力(再帰的思考)
この問題の核心は、「自分が兄の顔を見ているように、兄も自分の顔を見ているはずだ。そして、兄もそう考えているはずだ……」という入れ子構造の思考です。
他者の思考を想像する「再帰的思考」は、複雑な状況での推論に不可欠です。これは「メタ認知」や「共感的想像力」にも通じ、リーダーシップ、交渉、教育、プレゼンなどでとても重要な能力です。
このように、「自分からは見えない真実も、他者の視点に立って考えることで糸口が見える」という学びを、楽しみながら得られる問題でした。
※本記事の問題は書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から抜粋しています。同書ではこういった「考える力が高まる問題」を67問紹介しています。