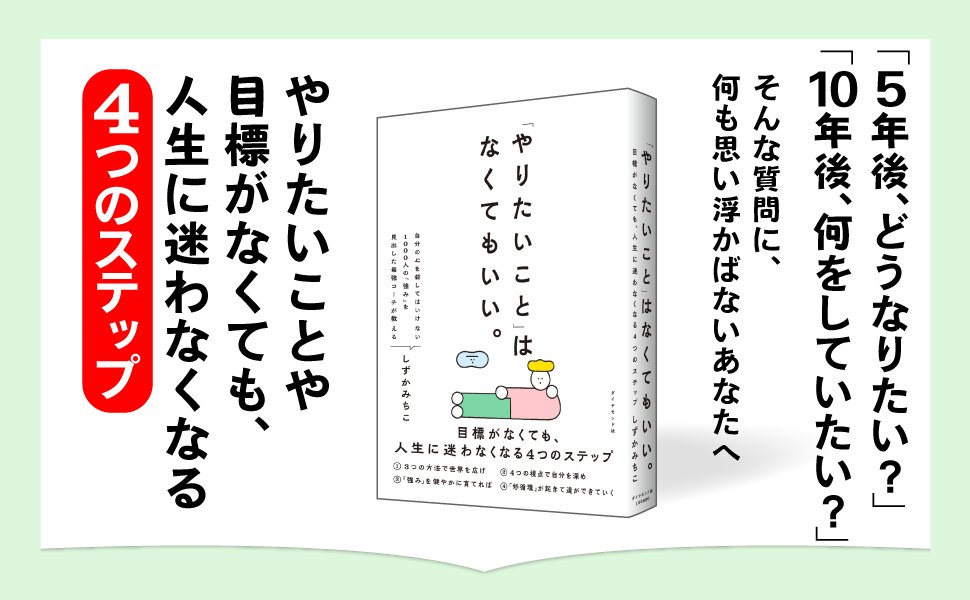社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。
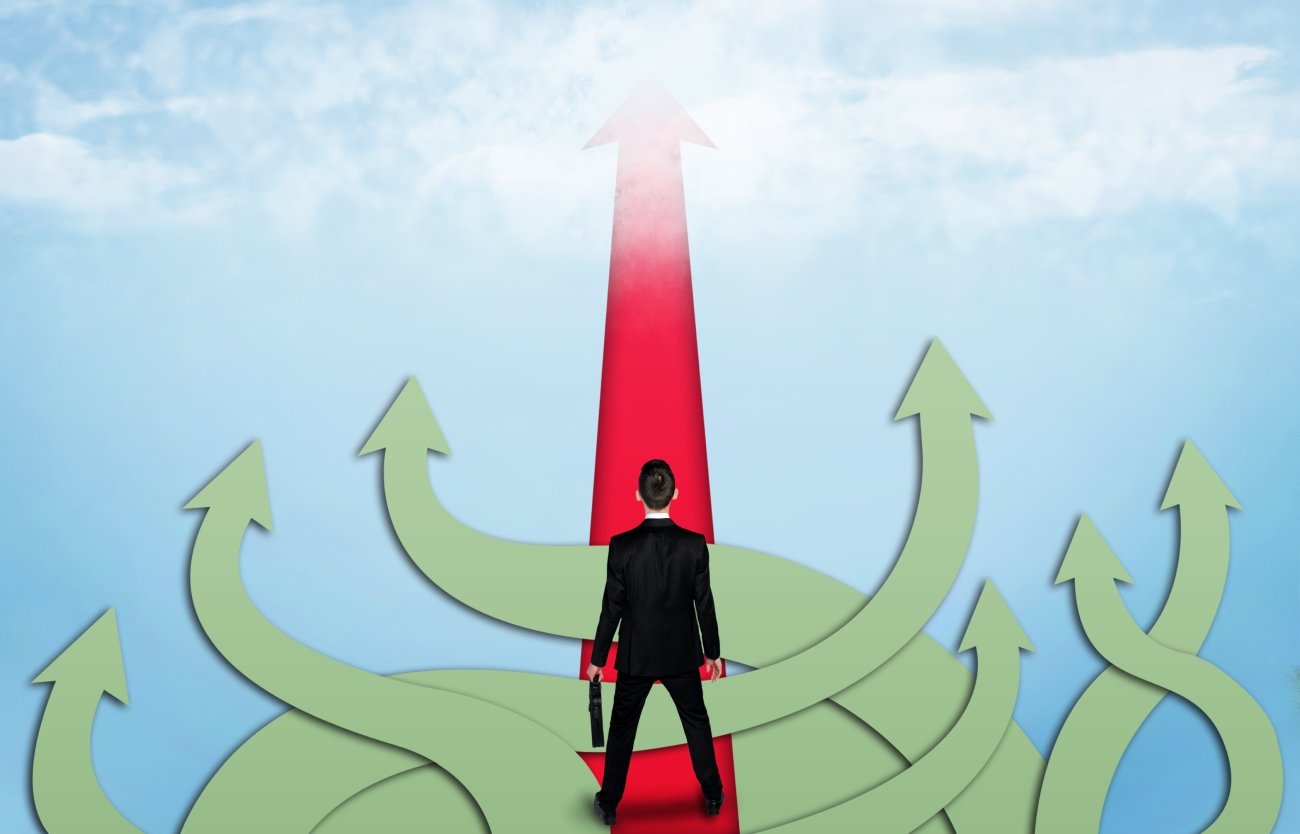 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「近道」が決して近道ではないとわかるラーメン店主のたとえ話
自分の道を見つけるためのファーストステップで、様々な経験をしながら世界を広げていると、正解への近道が欲しくなる瞬間もあるでしょう。けれども、回り道をしたからこそ、身につくものがあります。
例えば「究極のラーメン」を求める2人のラーメン店主がいるとしましょう。
Aさんは他店で修業した後に独立し、試行錯誤し、お客様からの酷評に悔し涙を流しつつ、回り道をした末に、自らが納得できる「究極の味」を見つけ出しました。
もう1人のBさんは、Aさんのレシピを手に入れて、すぐにお店を出しました。結果として、AさんとBさんのお店のラーメンの味は、全く同じです。
もし、AさんとBさんが、自分のラーメンの味に不満を漏らすお客様に出会ったとき、どういう対応になるでしょうか。
Aさんは試行錯誤しつつ作り上げた自分の味に自信があるので、自分とお客様では求める味が違ったのだと理解して、受け止めることができます。
残念に思いつつも、自分の味を堂々と貫くことができます。
一方、Bさんは、Aさんのレシピに問題があるのではとAさんに怒りを感じたり、このレシピを使い続けることに不安になったり、レシピを盲信するあまり「お前の舌のほうが間違っている!」とお客様に怒りを感じたりしてしまうでしょう。
Aさんは回り道をしたことで、自分が心の底から自信を持てる自分の味を見つけました。
お客様に「もっと麺を細くして縮らせたほうが」とご意見をいただいても、既に試行錯誤の段階で試し済みなので、自分のやり方が揺らぎはしません。
でも、Bさんは、お客様に「もっとこうしたら~」と言われたときに、それを試したことがないので、自分の腕に自信がなくなり不安になってしまいます。
自分の「道」と言い切れるためには試行錯誤が必要
試行錯誤をしつつ真剣に自分と向き合った時間は、自分の「味」への信頼の土台です。この信頼がなければ、ちょっと壁にぶつかっただけで揺らいでしまいます。
自分の「味」は自分の「道」とも言い換えられます。
これこそが自分の道だと言い切れるものを見つけるためには、迷い、悩み、試行錯誤する時間が必要なのです。
*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。