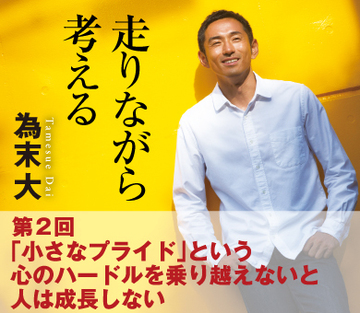撮影:今井一詞
撮影:今井一詞
陸上スプリント種目の世界大会で日本人初のメダル獲得者の為末大さんは、3大会連続でオリンピックに出場し、男子400mハードルの日本記録保持者でもある。陸上競技では「10年で一定のピークに到達する」というが、自分のスキルが伸び悩んだ時、どうすればいいのか。ノンフィクション作家の笹井恵里子さんが聞いた。(ノンフィクション作家・ジャーナリスト 笹井恵里子)
陸上競技では10年でピークに
研究者も40代でピークを迎える
仕事で経験を積み、さまざまな結果を残してきた。けれども、ベテランになって若い時の「結果」を超えられない――。そのように悩んでいる人もいるかもしれません。
陸上競技では「10年で一定のピークに到達する」というロジックがあります。自己ベストは、13歳から始めると23歳がピークということです。長くても、競技を始めて15年くらいでピークがくる。
研究者の世界でも、例えばノーベル賞は20~30年前の研究成果が評価され、60歳以降に受賞することが多いといわれます。つまり研究者としては30代、40代でピークを迎えているわけですね。
ですからビジネスでもスキルにはおそらくピークがあるでしょう。
ピークを過ぎても
「消化試合」ではない
ピークを過ぎた時、二つの道があると私は考えます。
ひとつは、それでも「スキルの道」を徹底的に突き進む形です。アスリートや芸能人、俳優の方にはよくみられますが、“技を極める”ということですね。この場合、評価方法も非常にシンプルで、売れるか売れないかです。
もうひとつは「複合的な技の道」。例えば経営者の方は、何かのスキルが突き抜けているよりも、判断力やマネジメント能力、人柄などさまざまな要素がからみあい、複合的な技で勝負できますよね。
スポーツにも、この道があります。もちろん選手は個人の能力が評価されるスキルの道。しかも単独のスキルほどピーク年齢が若いですから、一個の技だけに取り組む100m走のような世界は、年をとると非常に厳しい。
一方でチームで取り組んだり、駅伝チームの監督のような戦略的な業務になるほど複雑性が増し、年を重ねることが不利でなくなります。過去の経験が活きたり、幅広い年代とのコミュニケーションを必要としたりするなど、監督やコーチは「複合的な技の道」といえるでしょう。
研究者もピークをすぎたら「消化試合ですか」と言ったらそんなことはありません。多くの研究者は「次を育てる」「役割を変える」という言い方をして、後進につなげていくのです。
ですから、たとえビジネスの世界でピークを過ぎても、仕事以外の地域コミュニティーの活性化など、自分を活かせる場を見つけられればいいと思うんです。
-------------------
「後進を育てる」「仕事以外での居場所を見つける」というと聞こえがいいが、実際に自分ごとに置き換えると、組織内での居場所が脇に追いやられていくようで悲しい。
-------------------
アスリート引退後のセカンドキャリアにも似ているのですが、一番自分を苦しめるのは「自分が持っている物差し」だと思うんです。