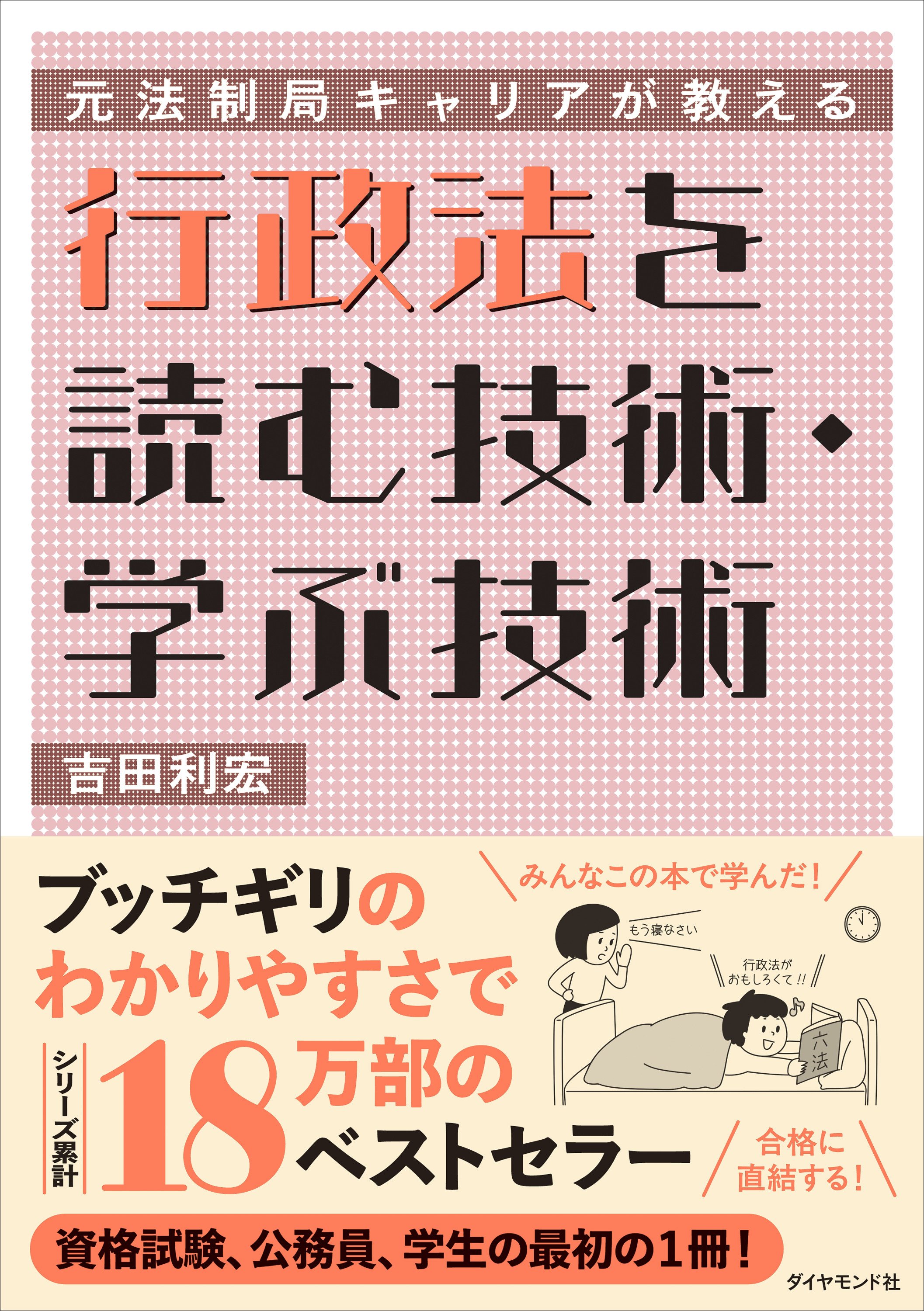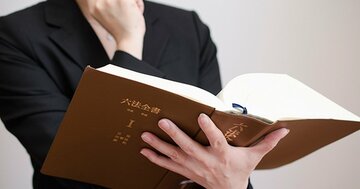累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。
 イラスト:草田みかん
イラスト:草田みかん
行政法は行政の道具ではありません
「行政法というのは公務員が国民(住民)の幸せを実現するための道具だ」。公務員はそう考えがちですが、そうではないのです。
行政法は公務員の仕事のための道具ではなく、「国民(住民)の自由を守るためのもの」としての面があります。
なるほど、行政法は行政に権限を与えています。たとえば、「○○してはいけない」という場合には、取締りの権限を与えていますし、「××するには許可を得なければならない」という場合には、許可権限を与えています。
しかし、見方を変えれば違ったものが見えてきます。たとえば、「××するには許可を得なければならない」という法律には、同時に許可を与えるための条件(要件)も書かれていることがあります。
実はこの部分は「行政を縛る」意味があります。行政に許可の権限を与えるとともに、行政が好き勝手に許可を与えたり、与えなかったりするような事態を防ぐ意味です。
行政作用法は行政に権限を与えると同時に、行政の権限を法で定めた「檻」のなかに閉じ込めておく意味があります。
「契約」と「行政行為」の違い
山田さんが吉田さんに飼っていたカピバラを売ったとします。カピバラはそんなに安くはありません。中古の軽自動車ぐらいの値段はします。
ところが、吉田さんはカピバラの引き渡しを受けたのに、なかなかその代金を支払おうとしません。
山田さんは我慢できなくなり、裁判所に吉田さんを訴えたとします。この裁判を通じて、債務の存在が確認されても、吉田さんが債務を履行しない(代金を支払わない)場合はどうでしょう。山田さんは、さらに裁判所に申し立て、吉田さんの財産を差し押さえてもらうこともできます(強制執行)。
一般の人どうしの関係です。それなのに、どうして国(裁判所)が後ろ盾になって、債権の存在を認めてあげたり、回収の手伝いをしてくれるのでしょうか。
それは、社会の秩序、特に経済活動の秩序を守るということがあります。そして、その秩序は誰が作り出したのかといえば、山田さんと吉田さんです。
契約書があろうとなかろうと、2人の間では「このカピバラを売ろう」「そのカピバラを買おう」という意思の合致があったのです。まさしく売買契約が成立していたといえます。値段についても、当然、やり取りがあって合意に至ったことでしょう。
契約の効果として、権利(債権)や義務(債務)が生じます。売り手の山田さんはカピバラを吉田さんへ引き渡す義務を負いますし、吉田さんは代金を支払う義務を負います。そして、それぞれが義務の裏返しとなる権利を手にします。
自らの意思で負った義務については徹頭徹尾、果たさなければならないものとして、国はその実現を手助けするのです。
行政行為の特徴
ところが、行政行為(行政処分)となるとそうではありません。
行政行為というのは、許可とか、許可の取消しなどを思い浮かべてもらえばいいのですが、行政の行為であって次のような特徴をもったものです。
行政の私人(一般の人や会社)への働きかけの中心はこの行政行為によります。行政処分(処分)もほぼ、同じ意味だと思ってください。
・特定の者を狙い撃ち
・具体的に権利を制限したり、権利を与えたりなどする
・法的に裏付けされたもの
・一方的な行為
具体例で考えてみよう:課税処分
課税処分も行政行為のひとつですので、これを例にとって考えてみましょう。
家に帰ったら、見慣れた市役所の封筒がポストに入っていたとします。開けてみると「本書のとおり市民税を決定しましたので、通知します」と税額が書かれた文書が入っていました。これはまさしく課税処分されたことにほかなりません。
課税処分に対しては、「今年はマンションの頭金を払ったので来年にしてくれないか」とか「隣の市より高いので3割引きにしてくれないか」など交渉することはできません。
行政処分なのですから一方的に行われるものです。こちらに交渉する権限も機会もありません。
ここで疑問が生じます。カピバラの代金を払わなければならないのは分かります。自分がカピバラを欲しい(買う)といったのですから……。
しかし、市税を「払いたい」とか「払ってもいいよ」などと一度たりとも市と合意したことはありません。そう考えると不本意な気持ちが込み上がってきます。
なるほど、自分が個人的に「市税を払ってもいいよ」とはいっていません。しかし、自分の代わりに国会が、自分の代わりに市議会が「こうした場合には○○円の市税を課す」ことに「うん」といっているのです。
国会は地方税法という法律を制定し、それに基づいて市は市税条例を定めて課税を行います。こうした法(行政作用法)に基づき市は課税処分を行うのです。
法律による行政の原理
行政作用法においての大事な考え方に「法律による行政の原理」というものがあります。簡単にいえば、「行政の活動には法律による根拠が必要である」というのがこの考え方です。
行政が好き勝手にふるまうこと、特に好き勝手にふるまって国民の権利や自由を踏みにじることは認められないとしています。後で詳しくお話ししますが、行政法を学ぶ意味がここにあります。
※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。